結論ですが
PFCを実践する流れとして「PFCを記録する」「PFCの目標設定をする」「PFCを変えてみる」があります。
この記事は「マラソンを趣味にしている」ヒトに向けて書いています。
マラソン競技に対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「PFCを実践する流れ」についてわかります。
PFCを実践するには、どのような流れになりますか?
このような疑問にお答えします。
自分自身、ランニングが趣味で、マラソン大会によく出場しています。
タイムを上げるために日々トレーニングに励んでいます。
マラソン競技において、タイムを少しでも上げるために、日々の練習をがんばっているランナーは多いかと思います。
マラソン競技でタイムを少しでも上げるために、様々な要素が重要になります。
トレーニングは勿論、休養、そして日々の食事もとても大切です。
食事、栄養を考える上で、主にエネルギーとなる三大栄養素であるPFCが特に重要です。
PFC、つまり「タンパク質」「脂質」「炭水化物(糖質)」のバランスが競技パフォーマンスに直結すると言っても過言ではありません。
では、PFCを実践するには、どのような流れになりますか?
ということで、今回は「PFCを実践する流れ」について説明していきます。
PFCを記録する
PFCを実践する流れとして「PFCを記録する」ことがあります。
まずは、ご自身が毎日食べている食事内容のPFCが、どのようなものなのか現状把握しましょう。
食事の内容を記録するのに、今では便利なアプリがたくさんあります。
とくに、
ダイエットする方向けのアプリ
ボディメイクをしている方向けのアプリ
生活習慣病の治療で使われるアプリ
などで、アプリに特徴があります。
アプリの操作性、使い勝手、目的に応じて、色々とあるため、自分にあったものが見つかるように試してみると良いでしょう。
以前であれば、料理ごと、そして食材までさかのぼってPFCを記録していたようです。
大変、手間と時間がかかるかと思いますが、今は便利になりましたね。
食事の内容を記録する時には、できるだけ自分で行わず誰かにやってもらうと良いでしょう。
というのも、食事の内容をつけるだけで、自分が意外とカロリーを沢山とっている、栄養バランスが偏ってるなど途中で分かってしまうため、それを修正する方向に無意識のうちに働いてしまいます。
ちなみに、レコードダイエットという言葉がありますが、食事の内容をつけるだけで、ダイエットが成功しやすくなるのも、この作用のためです。
自分で食事内容をつけると、正しい現状把握が出来なくなることにつながりますので、出来るだけ誰かにやってもらいましょう。
クラブチーム、部活動などに入っている方であれば、二人一組になって、お互いの食事内容を記録し合うなんていうのも良いでしょう。
PFCを実践する流れとして「PFCを記録する」ことがあります。
栄養成分表示を利用する
PFCを記録するコツとして「栄養成分表示を利用する」ことがあります。
スーパーマーケットやコンビニで売られている食品のほとんどには、栄養成分が表示されています。
とくに、加工食品には、使用されている材料や栄養成分の表示が義務化されているので、必ず記載されています。
ご自身が食べる食品の栄養成分表示をみて、記録するといいでしょう。
ちなみに、栄養成分表示では、熱量(kcal)・タンパク質・脂質・炭水化物・ナトリウムの順に必ず記載しています。
気の利いた場合では、炭水化物の詳細が「糖質」と「食物繊維」に分けて書いてあります。
PFCとは関係ないですが、ナトリウムの量は、「食塩相当量」(g)で記載するように決まっています。
栄養成分表示があれば、食事を記録するのがすごく楽ですね。
PFCを記録するコツとして「栄養成分表示を利用する」ことがあります。
はかりを利用する
PFCを記録するコツとして「はかりを利用する」ことがあります。
外食するときにチェーン店などでは、栄養成分の表示がされている場合が多く、記録するのが楽です。
しかし、個人で営んでいる飲食店では、残念ながら栄養成分表示がない場合がほとんどです。
そして、料理の重さなども規格が統一されていないので、バラバラです。
そこで登場するのが、はかり(計量器)です。
料理の全体の重さを測り、後から「その料理の標準的な栄養成分」を調べてPFCがどのくらいになるか計算しましょう。
より正確に計算したいのであれば、材料毎に重さを測定しましょう。
全部を測定するのは大変だと思うので、PFCのメインとなるような
米・パン・めんなどの糖質
肉・魚・豆・などのタンパク質
などに絞って測るといいでしょう。
野菜などは、PFCとあまり関係ないので(ビタミン・ミネラルは豊富ですが…)、個人的には、大雑把に記録しています。
そして、可能であれば、取り皿をもらって、測定します。
今のはかりは、「0(ゼロ)設定」できるものがほとんどで、皿の重さを差し引いた重さが分かるので便利です。
雰囲気的に取り皿をもらうのが厳しければ、「料理を食べる前の全体の量」と「その食材を食べた後の量」を引いて計算します。
脂質が多いドレッシングなどは正確に測りたいので、可能であれば、別皿に載せてもらうようにしています。
PFCを記録するコツとして「はかりを利用する」ことがあります。
写真を活用する
PFCを記録するコツとして「写真を活用する」ことがあります。
毎日の食事をしっかりと記録するのは、結構大変だと思います。
そこで、ズボラなあなたは、食べる食事を写真に撮影するという方法があります。
写真に撮影しておけば、後から時間があるときに、栄養成分を調べて記録することができます。正確性には欠けますが、大きく把握したいときには良い方法になります。
できれば、料理の重さも同時に測っておきたいところですが、いつでも「はかり」があるとは限らないため、ある程度の量が分かるようにしておくといいでしょう。
ちなみに「しゃもじ一杯」のごはんの量は「おおよそ90g-110g」くらいになります。
お茶碗一杯のごはんの量は、普通で「150-180g程度」、大盛で「200-250g程度」。
コップ一杯の牛乳の量は「180ml-200ml程度」
肉・魚など、手のひらサイズで「100g程度」で「タンパク質20g程度」になる
刺身は一切れ「15-20g程度」などです。
食事の量を測るクセがつくと、重さの感覚も自ずとわかってきます。
PFCを記録するコツとして「写真を活用する」ことがあります。
2.PFCの目標設定をする
PFCを実践する流れとして「PFCの目標設定をする」ことがあります。
ご自身のPFCの現状把握が出来たら、目標とするPFCを設定するようにしましょう。
PFC摂取量の目標を計算する上で、まずは「除脂肪体重」を計算します。
除脂肪体重とは、脂肪の重さを除いた体重のことをいいます。
これを測定するためには、体脂肪も計測できる体重計が必要です。
仮に体脂肪率が20%で、体重が60kgだった場合は…
60kg*0.2(20%)=12kg(脂肪の重さ)
60kg-12kg=48kg(除脂肪体重)
と計算されます。
次に「摂取カロリー」の目標を計算します。
1日に摂取すべきカロリーは「除脂肪体重」に「40kcal」を掛けます。
先ほどの計算の場合では、
48kg*40kcal=1920kcal
と計算されます。
ただし、身体活動レベルに応じて摂取カロリーを付加する必要があります。
Ⅱだと1.15~1.2倍
Ⅲだと1.3~1.4倍 程度が目安になります。
ちなみに、ランナーの場合、
走行距離km×体重kg=消費カロリーkcal
となるため、これが付加カロリーの目安になります。
最後に、PFCバランスの割合を目標設定します。
ここで、フルマラソンにおいて、脂質代謝をメインにする、糖質代謝をメインにするなど目的に応じて、目標は異なってきます。
そして、何が最適なPFCバランスなのか、定まっているものは実はありません。
一応の目安としては
Pタンパク質→12-20%程度、体重*1-2g程度
F脂質→15-30%程度
C炭水化物→50-65%程度
となります。
ご自身の現状から、あまりにかけ離れている目標にしてしまうと、目標達成が難しくなるため、初めのうちは緩やかな目標にしてみましょう。
慣れてきたら、色々と実験して、ご自身の調子と合わせて最適なPFCバランスを見つけると良いでしょう。
PFCを実践する流れとして「PFCの目標設定をする」ことがあります。
PFCを変える
PFCを実践する流れとして「PFCを変えてみる」ことがあります。
PFCの現状把握、目標設定が出来たら、最後に目標が達成出来るように毎日食べる食事のPFCを変えてみましょう。
現状と目標のズレを分析して
PFCの何が足りていないのか
PFCの何が多いのか
PFCの何がちょうどいいのか
認識しましょう。
そして、足りなければ補い、多ければ減らすようにします。
といって、毎日食べる食事は同じようで、実は微妙に違っている場合が多々あります。
その調整を行うのは難しいかと思います。
結局、目標達成だけに目がいって、毎日同じ食事になってしまうケース、サプリメントや準備が楽な加工品に頼りすぎてしまうケースもあり注意が必要です。
個人的に気をつけていることとして…
様々な食材を取り入れる
なるべく加工品をとらない
旬の食材を取り入れる
野菜を多めにとる
不要な添加物は極力とらない
サプリメントは最低限にする
食に感謝して楽しく食べること
などを心がけています。
どうしても目標となるPFCバランスとならないケースが出てきます。
ご自身で、Pが多めの食材、Fが多めの食材、Cが多めの食材などを把握して、PFCの帳尻を合わせて、うまく調節出来るようにしましょう。
PFCを実践する流れとして「PFCを変えてみる」ことがあります。
食事のPFCを把握する
PFCを変えるコツとして「食事のPFCを把握する」ことがあります。
いつもの食事の内容からPFCを変える場合、どの食事の内容において「P」「F」「C」が多く含まれているか把握する必要があります。
たとえば、P(タンパク質)の多い食品として
肉
魚
たまご
大豆・大豆製品
牛乳・乳製品
などがあります。
F(脂質)の多い食品として
青魚
ドレッシング
チーズ
オイル
洋菓子
などがあります。
C(炭水化物・糖質)の多い食品として
白米
パン
パスタ
そば
和菓子
などがあります。
PFCを微調整したいときに、PFCそれぞれどのような量が含まれているかも、大まかでいいので把握しておくと便利です。
また、PとFが多い食品、PとCが多い食品、FとCが多い食品など組み合わせて食品を把握しておくと、色々なバリエーションの食事で調整することができます。
色々な食事・食品・材料を把握すると、食べる料理のレパートリーも自ずと増えるため、食事がますます楽しくなるでしょう。
PFCを変えるコツとして「食事のPFCを把握する」ことがあります。
食事から差引・追加する
PFCを変えるコツとして「食事から差引・追加する」ことがあります。
PFCを変えるには、ふだんのいつも食べている食事の内容を変える必要があります。
どのように変えるかというと、「いつもの食事のPFC」と「目標とする食事のPFC」を比較して、差し引きや追加する形になります。
いつもの食事でPFCいずれか多い項目があれば、差し引きします。
反対に、PFCいずれか少ない項目があれば、追加します。
このときも、PFC多く含まれている食品などを把握しておくと調整がスムーズにいきます。
さらに、食品のバリエーションも増えて、より楽しく食事メニューを決めることができます。
いつもの食事から、足し算・引き算する思考が大切になるのです。
PFCを変えるコツとして「食事から差引・追加する」ことがあります。
好きな食品を取り入れる
PFCを変えるコツとして「好きな食品を取り入れる」ことがあります。
何事も楽しくないと長続きしないです。
ご自身が好きな食品を是非とも取り入れましょう。
まずは、自分がいつも食べている食事で絶対にはずしたくないものを選びます。
自分の大好きな食事メニューは絶対に入れておきましょう。
そして、それ以外のメニューでPFCのバランスをうまく調整するようにします。
個人的には、納豆が大好きなのと、どら焼きが好きなので…
毎日の朝食は「納豆ごはん」で定番にして、C(炭水化物・糖質)が足りない時には間食で「どら焼き」を食べたりしています。
どら焼き以外にも和菓子は好きなので、ようかん・大福などで糖質を補給しています。
自分の好きな食品を取り入れて、毎日の食事を楽しみましょう。
PFCを変えるコツとして「好きな食品を取り入れる」ことがあります。
定番メニューをつくる
PFCを変えるコツとして「定番メニューをつくる」ことがあります。
ご自身が普段とっている食事の内容の定番メニューはありますか?
よく一流アスリートなどでは、朝ごはんを定番化しているケースが多いです。
たとえば、野球選手のイチローは、朝はカレーライスにしています。
自分は、個人的には、朝は納豆ご飯・味噌汁が定番です。
また、昼ご飯・夕食も、主食・主菜・副菜・汁ものを定番化しておけば、大きくPFCバランスが崩れることはなくなります。
ただし、さまざまな食材を取り入れなければ栄養バランスが偏ってしまったり、微量栄養素が不足してしまうケースもあるため、定番化する部分と自由に決めていい部分も決めておきましょう。
準備する手間もかかるため、現実的には1週間ごとに食事のメニューをおおまかに決めておくといいでしょう。
PFCを変えるコツとして「定番メニューをつくる」ことがあります。
似ている食品を把握する
PFCを変えるコツとして「似ている食品を把握する」ことがあります。
PFCを変えるには定番メニューを作ることが重要です。
しかし、現実的には、思わぬことによって、食べるものが変わる可能性があります。
たとえば、
いつもの定食屋が休みだった
お土産で美味しいスイーツをもらった
近所の方から、野菜をおすそ分けしてもらった
飲み会があった
いつもの食材が売り切れだった
など定番メニューが食べられない、もしくは定番メニュー以外を食べなければならない場面が多々あります。
そんなときには、代わりになる同じようなPFCバランスの似ている食品を把握しておくことが大事です。
たとえば、お土産で和菓子のようかんをもらった場合。
糖質が多めに入っているため、いつものご飯の量は少なめにして調整することができます。
また、お土産で洋菓子のチーズケーキをもらった場合。
脂質が多めに入っているため、サラダのドレッシングは少なめにして調整することができます。
このように、PFCの似ている食品を把握することで、臨機応変に対応することができます。
さらに、いつもの食事メニューを決めるときにも便利になり、料理のバリエーションが増えて、ますます食事が楽しみになるでしょう。
PFCを変えるコツとして「似ている食品を把握する」ことがあります。
大まかな栄養素を把握する
PFCを変えるコツとして「大まかな栄養素を把握する」ことがあります。
PFCバランスが似ている食品を把握することに加えて、その食品の大まかな栄養素も把握することも大切です。
たとえば、
白米だったら、糖質はもちろん豊富ですが、タンパク質やビタミン・ミネラルも含まれています。
肉類だったら、タンパク質は豊富なのは当然ですが、牛肉は鉄分も含まれていて貧血予防に効果があり、豚肉はビタミンも含まれているため三大栄養素の代謝を促してくれます。
なお、鶏肉は低脂質であり、タンパク質をメインに補給するときに役立ちます。
野菜であれば、アボカドは良質な脂質が豊富に含まれており、ブロッコリーはタンパク質が含まれており、にんじん・たまねぎ・コーンなどは糖質が比較的多めです。
PFCバランスを整える場合に、意外と「主食」以外からも糖質が摂取されていたり、「主菜」「副菜」でもタンパク質や脂質が思いのほか多くなるケースもあります。
また、PFC以外の栄養素のバランスも大切になるため、食品毎の大まかな栄養素を把握することが重要です。
PFCを変えるコツとして「大まかな栄養素を把握する」ことがあります。
まとめ
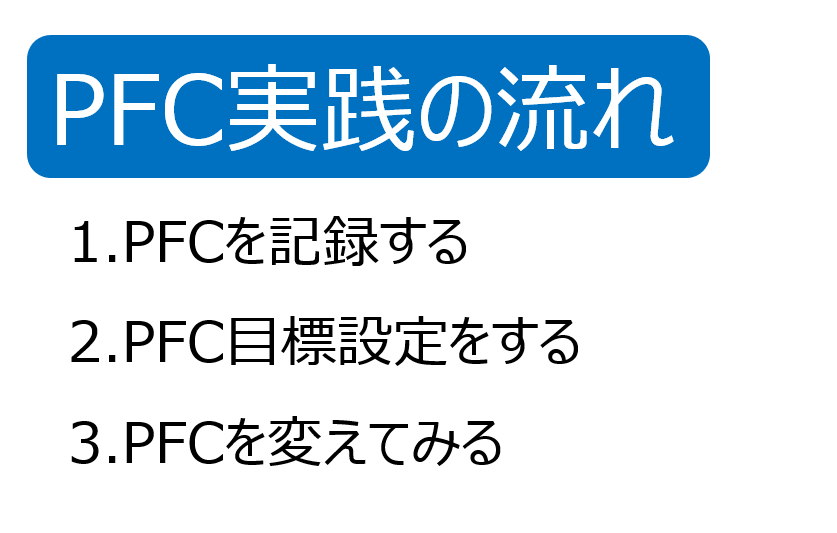
今回は「PFCを実践する流れ」について説明しました。
マラソン競技においてトレーニングだけでなく、食事栄養もとても重要です。
ご自身の日々の食事を見直して、食を味方につけて、競技パフォーマンスを高めて頂ければ幸いです。
この記事によって「PFCを実践する流れ」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/



