結論ですが
ファットアダプトとは、脂質が多い食事を、長期的に食べ続けることで、脂質をエネルギー源として多く利用できるように適応させる方法です。
この記事は「スポーツを趣味にしている」ヒトに向けて書いています。
食事・栄養に対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「ファットアダプト」についてわかります。
ファットアダプトって何ですか?
このような疑問にお答えします。
三大栄養素である「タンパク質」「脂質」「炭水化物」のことを「PFC」といいます。
タンパク質(Protein)
脂質(Fat)
炭水化物(Carbohydrate)
スポーツ選手やアスリートの場合、厳しいトレーニングに耐えうる体作りなどのために、食事・栄養がとても重要になります。
そして、この「PFC」がエネルギー源となるため重要となります。
マラソンなどの持久系競技において、とくに「炭水化物・糖質」(C)や「脂質」(F)が大切です。
今回は、そのうち「脂質」(C)についてピックアップします。
エネルギー源として「脂質」(F)をうまくエネルギー源として使うために、「ファットアダプト」という方法があります。
では、ファットアダプトとは何ですか?
ということで、今回は「ファットアダプト」について説明していきます。
ファットアダプトとは
ファットアダプトとは、脂質が多い食事を、長期的に食べ続けることで、脂質をエネルギー源として多く利用できるように適応させる方法です。
運動時のエネルギー源として、糖質や脂質が重要な働きをします。
とくにマラソンなどの持久系競技であれば、糖質・脂質ともにエネルギー源として大切です。
糖質は、エネルギー源としてすぐに利用されやすく、出力が高い運動で優先的に使われます。
短時間の運動であれば、酸素を利用しないでエネルギーを生み出す「無酸素代謝」
において、糖質はエネルギー源としておもに使われます。
長時間の運動において、酸素を利用してエネルギーを生み出す「有酸素代謝」
においては、糖質だけでなく脂質もエネルギー源として使われます。
糖質は、万能なエネルギー源です。
その場で使われない糖質はグリコーゲンとして、筋肉や肝臓に蓄えられます。
しかし、グリコーゲンとして貯蔵される量は「約1600kcal」程度と少ないです。
一方、「脂質」は「1gあたり約9kcal」のエネルギーがあります。
脂質は、出力が低い運動や、長時間持続するような運動をするときに安定的にエネルギーを供給してくれます。
マラソン競技では、2時間以上にわたる長時間の運動になるので、糖質だけでなく脂質もエネルギー源として利用することが大事になります。
強度の高めの運動において、糖質が少なくなってきたときに、脂質がエネルギー源として使われるようになります。
そのため、エネルギー源として利用されるまでに比較的時間がかかります。
また、出力が低いような運動をするときに、脂質がおもにエネルギー源として使われます。
脂質は、出力が比較的少ない、長時間の運動をするときのエネルギー源として活躍してくれるのです。
なお、これまで発表されてきたスポーツ栄養ガイドラインによると、脂質量はエネルギー摂取量全体の「25%程度」が望ましいとされてきました。
しかし、ファットアダプトでは、脂質が多い食事(エネルギー摂取量の70~80%程度)を、長期的に食べ続けることになります。
ファットアダプトでは、脂質を多く摂取することによって、脂質をエネルギー源として、より利用しやすくするために適応させる方法です。
ファットアダプトとは、脂質が多い食事を、長期的に食べ続けることで、脂質をエネルギー源として多く利用できるように適応させる方法です。
ファットアダプトの効果
ファットアダプトの効果として「持続的なエネルギー補給」「脂肪燃焼」「記憶保持効果」「抗炎症作用」「神経細胞の死滅抑制」「セロトニン機能を高める」「脳血流量の増加」などがあります。
ファットアダプトによって、脂質が使えるようになると、長時間の運動が可能になります。
脂質が利用されやすくなり、体脂肪などの燃焼効果も高まります。
ただし、脂質を利用するときにも糖質の存在が必要になります。また、脂質のみでは出力を上げるのが難しいとされています。
なお、脂質をエネルギー源として利用するときに、ケトン体という物質が産生されます。
一時期、脳のエネルギー源は「ブドウ糖」のみと言われていましたが、「ケトン体」もエネルギー源として利用することができます。
ケトン体は、「記憶保持効果」「抗炎症作用」「神経細胞の死滅抑制」「セロトニン機能を高める」「脳血流量の増加」などの効果があります。
ケトン体は、「難治性てんかん」の治療に用いられたり、アルツハイマー型認知症の改善効果が報告されています。
ファットアダプトの効果として「持続的なエネルギー補給」「脂肪燃焼」「記憶保持効果」「抗炎症作用」「神経細胞の死滅抑制」「セロトニン機能を高める」「脳血流量の増加」などがあります。
ケトン体とは
ケトン体とは
ケトン体とは、脂質をエネルギー源として利用するときに生み出される物質であり、アセト酢酸、3-ヒドロキシ酪酸、アセトンなどがあります。
通常時では、ケトン体は脂肪の合成や分解における中間代謝産物 であるため、血液中にはほとんど存在しません。
しかし、糖尿病、糖質制限、絶食など、脳や筋肉のエネルギー源である糖質(グルコース)が利用できない時に、脂質が代わりのエネルギー源として使われるため、その時にケトン体は産生されます。
脂肪細胞に蓄えられている中性脂肪はそのままだとエネルギー源として利用できません。
そこで、中性脂肪から脂肪酸が切り離されて血液中のアルブミンと結合し、肝臓に運ばれ「アセチルCoA」という物質にまで分解されます。
「アセチルCoA」から作られるのがケトン体で、ケトン体にはアセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸といった種類があります。
肝臓で作られたケトン体は、肝臓から放出されて血液の流れに乗り、筋肉や脳などのエネルギー源として働くのです。
ケトン体とは、脂質をエネルギー源として利用するときに生み出される物質であり、アセト酢酸、3-ヒドロキシ酪酸、アセトンなどがあります。
ケトン体の効果
ケトン体の効果として「細胞のエネルギー源」「脂肪燃焼」「記憶保持効果」「抗炎症作用」「神経細胞の死滅抑制」「セロトニン機能を高める」「脳血流量の増加」などがあります。
繰り返しですが、脂質をエネルギー源として利用するときに生み出される物質です。
赤血球・網膜以外の細胞のエネルギー源として使われます。
一時期、脳のエネルギー源は「ブドウ糖」のみと言われていましたが、ケトン体もエネルギー源として利用することが出来ます。
また、ケトン体は脂質を原料に産生されるため、必然的に脂肪が燃焼されますので、ダイエットで体脂肪を落としたい方に最適になります。
また、ケトン体には、「記憶保持効果」「抗炎症作用」「神経細胞の死滅抑制」「セロトニン機能を高める」「脳血流量の増加」などの効果があります。
ケトン体は、「難治性てんかん」の治療に用いられたり、アルツハイマー型認知症の改善効果が報告されています。
また、スポーツにおける競技パフォーマンスを向上させる効果などあります。
ケトン体の効果として「細胞のエネルギー源」「脂肪燃焼」「記憶保持効果」「抗炎症作用」「神経細胞の死滅抑制」「セロトニン機能を高める」「脳血流量の増加」などがあります。
ケトン体を生み出すには
ケトン体を生み出すには「低糖質」「高脂質」の食事を摂る方法があります。
繰り返しですが、糖尿病、糖質制限、絶食など、脳や筋肉のエネルギー源である糖質(グルコース)が利用できない時に、脂質が代わりのエネルギー源として使われ「ケトン体」は産生されます。
食事において低糖質のものを心がけましょう。
とくに、主食となる「白米」「パン」「パスタ」などの摂取は控えるようにしましょう。
厳格な糖質制限では、糖質摂取量は「1日で糖質50g以下」となっております。
ただし、糖質制限に慣れていないと、低血糖やエネルギー不足のため体調が悪くなることもあります。
ご自身の体調をみて無理のない範囲で行いましょう。
エネルギーが少なくなるため、代わりに脂質を多めに摂取しましょう。
肉・魚・植物油・乳製品などからバランス良く良質な脂質を摂取します。
ただし、オメガ6系脂肪酸・飽和脂肪酸の摂り過ぎや、トランス脂肪酸に注意しましょう。
個人的には、亜麻仁油・えごま油・オリーブオイル・青魚の油などの脂質がオススメです。
ケトン体を生み出すには「低糖質」「高脂質」の食事を摂る方法があります。
ファットアダプトの方法
ファットアダプトの方法は、糖質摂取量を少なくし、脂質摂取量を増やし、タンパク質摂取量を確保します。
これまで発表されてきたスポーツ栄養ガイドラインによると
糖質摂取量は「60%以上」
脂質摂取量は「15~20%程度」
タンパク質摂取量は「20%~25%程度」
が望ましいとされています。
しかし、ファットアダプトでは、脂質が多い食事を、長期的に食べ続けることになります。
糖質摂取量は「10%以下」
脂質摂取量は「70~80%程度」
タンパク質摂取量は「20%~30%程度」
摂取するようにします。
また、食事をしない状態を作り出すことによって、脂質代謝が促されます。
一日のうちに10時間以上の空腹時間を設ける(プチファスティング)とともに、間食を控えるようにします。
また、MCTオイルなどのすぐにエネルギー源として使われやすい脂質を摂取することによって、脂質代謝を促すようにします。
エネルギーになりやすい脂質
飽和脂肪酸
エネルギーになりやすい脂質として「飽和脂肪酸」があります。
飽和脂肪酸は、エネルギーとして使われやすく、体内で合成することができる脂肪酸です。
主に、パルミチン酸・ステアリン酸・ミリスチン酸などの脂肪酸があります。
飽和脂肪酸は、一般的に過剰摂取されやすく、健康への悪影響が知られています。
とくに運動不足な現代人は、飽和脂肪酸をエネルギーとして使われず、余ってしまう傾向にあります。
飽和脂肪酸を摂りすぎると、血液中の「中性脂肪」や「LDLコレステロール」(悪玉コレステロール)を増加させ、「脂質代謝異常症」や「動脈硬化」につながります。
飽和脂肪酸は動物性の食品に多く含まれます。
「肉類」「バター」「ラード」「生クリーム」「牛乳」「乳製品」「チョコレート」「ケーキ」などに多く含まれます。
中鎖脂肪酸
エネルギーになりやすい脂質として「中鎖脂肪酸」があります。
なお、MCTは「Medium Chain Triglyceride」(中鎖脂肪酸)の略です。
中鎖脂肪酸は、ココナッツやパーム種子などのヤシ科の植物に含まれており、その天然成分である「中鎖脂肪酸」(MCT)のみを抽出してMCTオイルが作られます。
中鎖脂肪酸は、「多価不飽和脂肪酸」の中でも「オメガ3系脂肪酸」に分類されている脂肪酸で構成されています。
「中鎖脂肪酸」は、一般的な植物油に含まれる「長鎖脂肪酸」と比べて、消化吸収が早いです。
また、通常の脂質の代謝経路とは異なり、効率よく分解されて、エネルギー源として使われやすいです。
そのため、内臓脂肪や皮下脂肪などの体脂肪に蓄積されにくいという特徴があります。
中鎖脂肪酸は、素早くエネルギーに変換されるため、体脂肪として蓄積されにくく、体脂肪を燃やして作るケトン体の生成を促してくれます。
また、空腹を感じにくくなり、食べ過ぎを予防する効果もあります。
そのため、ダイエットの際に取り入れると良いと注目されています。
ファットアダプトの注意点
カロリーを十分摂取する
ファットアダプトの注意点として「カロリーを十分摂取すること」があります。
ファットアダプトでは、糖質の量をおさえて、脂質の量を増やすことになります。
通常の食事の主食では、炭水化物・糖質がメインでありますが、その摂取量をおさえるため、摂取カロリーが不足しがちです。
摂取カロリーが不足すると、エネルギー不足のため、全身倦怠感や疲労感などによって、日常の活動に影響を及ぼす可能性があります。
また、トレーニングにおいて、出力がうまく出せずに、トレーニングの質が上がらないなんてことにつながります。
糖質をおさえた分、脂質やタンパク質をしっかりと摂取して、カロリーをしっかりと補いましょう。
ファットアダプトの注意点として「カロリーを十分摂取すること」があります。
便秘予防をする
ファットアダプトの注意点として「便秘予防をすること」があります。
ファットアダプトでは、糖質を制限することになります。
ちなみに、炭水化物は、「糖質」と「食物繊維」に分かれますが、糖質を制限すると、必然的に、食物繊維も不足してしまいます。
食物繊維が不足すると、便が硬くなり、便秘気味になります。
また、食物繊維は、善玉菌などの腸内細菌のエサにもなるため、食物繊維が不足すると腸内環境は悪化してしまいます。
便秘予防するために、水分を積極的に摂取するとともに、糖質をおさえて食物繊維をメインにした炭水化物を摂取するようにしましょう。
食物繊維をメインに摂取するのが難しければ、サプリメントなどを活用してもいいでしょう。
また、基本的な部分ですが、よく噛んで食べること、適度な運動をすること、十分な睡眠をすることによって、消化管の運動が促されるため、便秘予防にもなります。
ファットアダプトの注意点として「便秘予防をすること」があります。
脂質の質を意識する
ファットアダプトの注意点として「脂質の質を意識すること」があります。
脂質にはさまざまな種類がありますが、その中でも健康にとって「良い脂質」と「悪い脂質」があります。
大きく分けて「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の二つに分けられます。
「飽和脂肪酸」は、エネルギー源として重要な脂質です。
以前は、動脈硬化の原因と言われて、悪い脂質として知られていましたが、最近では摂取量が少ないと反対に心血管疾患のリスクが高まるといわれており、適度に摂取することがすすめられます。
不飽和脂肪酸には、「一価不飽和脂肪酸」である「オメガ9系脂肪酸」、「多価不飽和脂肪酸」である「オメガ3系脂肪酸」や「オメガ6系脂肪酸」、「トランス脂肪酸」などがあります。
「オメガ3系脂肪酸」は、調理油などに含まれる「アルファリノレン酸」の他、魚類に含まれる「ドコサヘキサエン酸」(DHA)、「エイコペンタエン酸」(EPA)などがあり、健康にとって良い脂質です。
また、「オメガ6系脂肪酸」のほとんどは「リノール酸」であり、体内では合成されない必須脂肪酸です。
「オメガ6系脂肪酸」は、血液中の余分な「中性脂肪」や「総コレステロール」「LDLコレステロール」(悪玉コレステロール)を下げる作用があり、「脂質代謝異常症」や「動脈硬化」などの予防につながり、「心疾患」のリスクを下げる効果があることが知られています。
ただし、「オメガ6系脂肪酸」を多くとりすぎると、炎症反応を誘発したり、「HDLコレステロール」(善玉コレステロール)も低下してしまいます。
「トランス脂肪酸」は、常温で液体である植物油に水素添加させて、人工的につくられた脂肪酸です。
トランス脂肪酸は、一般的に健康に悪い脂質として知られており、「食べるプラスチック」とも呼ばれています。海外では食品への「トランス脂肪酸」の使用が規制されている地域もあります。
トランス脂肪酸を摂りすぎると、血液中の「LDLコレステロール」(悪玉コレステロール)を増加させるだけでなく、「HDLコレステロール」(善玉コレステロール)を低下させます。
「脂質代謝異常症」や「動脈硬化」につながり、「心疾患」のリスクを高めます。
ファットアダプトに限りませんが、「オメガ3系脂肪酸」は積極的に摂取し、「オメガ6系脂肪酸」「飽和脂肪酸」は適量を意識し、「トランス脂肪酸」は極力摂取しないようにしましょう。
ファットアダプトの注意点として「脂質の質を意識すること」があります。
ファットアダプトの注意点として「カロリーを十分摂取する」「便秘予防をする」「脂質の質を意識する」などがあります。
ファットアダプトでは、糖質の量をおさえて、脂質の量を増やすことになります。
通常の食事の主食では、炭水化物・糖質がメインでありますが、その摂取量をおさえるため、摂取カロリーが不足しがちです。
摂取カロリーが不足すると、エネルギー不足のため、全身倦怠感や疲労感などによって、日常の活動に影響を及ぼす可能性があります。
また、トレーニングにおいて、出力がうまく出せずに、トレーニングの質が上がらないなんてことにつながります。
糖質をおさえた分、脂質やタンパク質をしっかりと摂取して、カロリーをしっかりと補いましょう。
ファットアダプトでは、糖質や炭水化物の摂取を制限することになり、食物繊維も不足してしまいます。
食物繊維が不足すると、便が硬くなり、便秘気味になります。
また、食物繊維は、善玉菌などの腸内細菌のエサにもなるため、食物繊維が不足すると腸内環境は悪化してしまいます。
便秘予防するために、水分を積極的に摂取するとともに、糖質をおさえて食物繊維をメインにした炭水化物を摂取するようにしましょう。
食物繊維をメインに摂取するのが難しければ、サプリメントなどを活用してもいいでしょう。
また、基本的な部分ですが、よく噛んで食べること、適度な運動をすること、十分な睡眠をすることによって、消化管の運動が促されるため、便秘予防にもなります。
ファットアダプトで摂取する脂質の質にこだわりましょう。
脂質には、健康にとって「良い脂質」と「悪い脂質」があり、大きく分けて「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の二つに分けられます。
「飽和脂肪酸」は、エネルギー源として重要な脂質です。
以前は、動脈硬化の原因と言われて、悪い脂質として知られていましたが、最近では摂取量が少ないと反対に心血管疾患のリスクが高まるといわれており、適度に摂取することがすすめられます。
「不飽和脂肪酸」は、「一価不飽和脂肪酸」である「オメガ9系脂肪酸」、「多価不飽和脂肪酸」である「オメガ3系脂肪酸」や「オメガ6系脂肪酸」、「トランス脂肪酸」などがあります。
「オメガ3系脂肪酸」は、調理油などに含まれる「アルファリノレン酸」の他、魚類に含まれる「ドコサヘキサエン酸」(DHA)、「エイコペンタエン酸」(EPA)などがあり、健康にとって良い脂質です。
また、「オメガ6系脂肪酸」のほとんどは「リノール酸」であり、体内では合成されない必須脂肪酸です。
「オメガ6系脂肪酸」は、血液中の余分な「中性脂肪」や「総コレステロール」「LDLコレステロール」(悪玉コレステロール)を下げる作用があり、「脂質代謝異常症」や「動脈硬化」などの予防につながり、「心疾患」のリスクを下げる効果があることが知られています。
ただし、「オメガ6系脂肪酸」を多くとりすぎると、炎症反応を誘発したり、「HDLコレステロール」(善玉コレステロール)も低下してしまいます。
「トランス脂肪酸」は、常温で液体である植物油に水素添加させて、人工的につくられた脂肪酸です。
トランス脂肪酸は、一般的に健康に悪い脂質として知られており、「食べるプラスチック」とも呼ばれています。海外では食品への「トランス脂肪酸」の使用が規制されている地域もあります。
トランス脂肪酸を摂りすぎると、血液中の「LDLコレステロール」(悪玉コレステロール)を増加させるだけでなく、「HDLコレステロール」(善玉コレステロール)を低下させます。「脂質代謝異常症」や「動脈硬化」につながり、「心疾患」のリスクを高めます。
ファットアダプトに限りませんが、「オメガ3系脂肪酸」は積極的に摂取し、「オメガ6系脂肪酸」「飽和脂肪酸」は適量を意識し、「トランス脂肪酸」は極力摂取しないようにしましょう。
まとめ
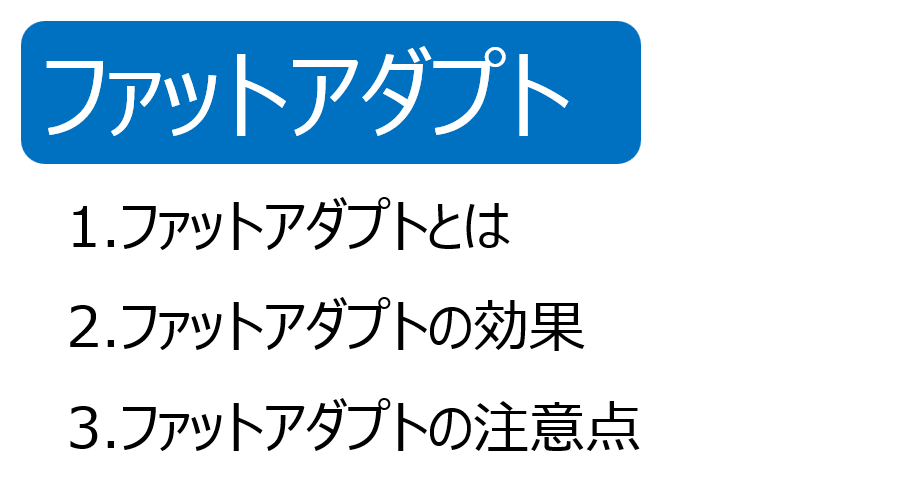
今回は「ファットアダプト」について説明しました。
この記事によって「ファットアダプト」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/


