結論ですが
代謝を促すポイントとして「材料を増やす」「酵素が必要である」「適度な温度である」などがあります。
この記事は「スポーツをしている人」に向けて書いています。
栄養に対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「代謝をまわすポイント」についてわかります。
スポーツをしていますが、エネルギーを多く生み出すために、何をすればいいですか?
このような疑問にお答えします。
三大栄養素である「タンパク質」「脂質」「炭水化物」のことを「PFC」といいます。
タンパク質(Protein)
脂質(Fat)
炭水化物(Carbohydrate)
スポーツ選手やアスリートの場合、厳しいトレーニングに耐えうる体作りなどのために、食事・栄養がとても重要になります。
そして、この「PFC」がエネルギー源となるため重要となります。
エネルギーを生み出すために、タンパク質・糖質・脂質などを体の中で利用するため「代謝」を促すことが重要になります。
では、代謝を促すために、どうすればいいですか?
ということで、今回は「代謝を促すポイント」について説明していきます。
代謝を促すポイント
材料を増やす
代謝を促すポイントとして「材料を増やすこと」があります。
たとえば、Aという物質からBという物質をつくるような代謝経路を考えます。
「A→B」
Aの量が多くなると、「A→B」の代謝経路は促されることになります。
これを応用すると、糖質や脂質などのエネルギー源からエネルギーを生み出す代謝経路を促したいときには、材料となる「糖質」や「脂質」を体に多く摂取することが重要です。
ちなみに、「タンパク質」は、体の構造をつくる材料として有名ですが、エネルギー源としても利用される場合があります。
とくに、タンパク質を多く摂り過ぎた場合、糖質や脂質などの他のエネルギー源が不足している場合などに、タンパク質がエネルギー源として利用されます。
注意点として、タンパク質はエネルギー効率が悪いですし、タンパク質の代謝産物であるアンモニアが発生するため解毒するために肝臓に負担がかかったりしてしまいます。
なので、出来るだけエネルギー源としては「糖質」や「脂質」をメインにした方が効率は良いと考えられます。
代謝を促すポイントとして「材料を増やすこと」があります。
酵素が必要である
代謝を促すポイントとして「酵素が必要であること」があります。
Aという物質からBという物質をつくるような代謝を行うためには、ただ単にAという物質があるだけではダメです。
「A→B」に変換する作用のある「酵素」の存在が必要不可欠です。
たとえば、唾液や膵液に含まれる「アミラーゼ」という酵素は、ブドウ糖が多数つながって出来ているデンプンを麦芽糖などに分解する働きをします。
「マルターゼ」の作用によって麦芽糖はブドウ糖に変換されて小腸から体内に吸収されます。
体内には様々な種類の酵素が存在しています。
代謝を促す酵素は、主にタンパク質を材料にして出来ているため、必要な量のタンパク質を摂取することが大切です。
また、発酵食品や肉・魚・野菜・果物などの食品にも酵素が含まれていますので、代謝を促すために積極的に摂取したいです。
代謝を促すポイントとして「酵素が必要であること」があります。
適度な温度である
代謝を促すポイントとして「適度な温度であること」があります。
繰り返しですが、代謝を促すためには酵素の働きが不可欠です。
酵素はタンパク質であるため、温度が低すぎると働きが低下します。
反対に温度が高すぎると変性して働きが失われてしまい、失活します。
タンパク質である酵素が働くには適度な温度があります。
おおよそ37度くらいの体温に近い温度において、働きが活発になります。
代謝を促すために、冬の寒い日など体の冷えを防いで、体を温めるようにするのが良いでしょう。
また、筋肉量が増えると、体の熱をより多く生み出してくれます。適度な運動を行って、適度な筋肉をつけることが大切です。
そして、栄養バランスの良い食事を心がけ、三大栄養素で熱エネルギーにもなる「糖質」や「脂質」、酵素の材料になる「タンパク質」をバランス良く摂取することが重要です。
代謝を促すポイントとして「適度な温度であること」があります。
産生物が少ない
代謝を促すポイントとして「産生物が少ないこと」があります。
たとえば、Aという物質からBという物質をつくるような代謝経路を考えます。
「A→B」
材料である「A」の量が多くなると、「A→B」の代謝経路は促されることになります。
そして、産生物である「B」の量が少ないと、「A→B」の代謝経路は促され、足りないBを作ろうとします。
長時間の運動などによってエネルギーが不足すると、糖質や脂質などの「A」という物質を材料にして、エネルギーである「B」を作ろうとして、「A→B」の代謝経路は促されます。
代謝を促すポイントとして「産生物が少ないこと」があります。
補酵素が必要である
代謝を促すポイントとして「補酵素が必要であること」があります。
Aという物質からBという物質をつくるような代謝を行うためには、ただ単にAという物質があるだけではダメです。
「A→B」に変換する作用のある「酵素」の働きが必要不可欠です。
そして、酵素がしっかりと働くために「補酵素」という物質も必要になります。
補酵素は、酵素のタンパク質部分に結合して、酵素活性を発現させる低分子有機化合物のことをいい、「コエンザイム」や「助酵素」などとも呼ばれます。
補酵素の働きによって、酵素の活性を高めたり、反対に酵素の活性を抑えたりと調整することができます。
タンパク質で出来ている酵素とは違い、補酵素は熱に強く、酵素と可逆的に結合する性質があります。
補酵素の多くは生体内でビタミンから作られており、ビタミンB群やナイアシンなどが代表的です。
ビタミンB群やナイアシンの欠乏は補酵素の欠乏を引き起こし、代謝がうまくいかない原因になります。
代謝を促すポイントとして「補酵素が必要であること」があります。
優先順位がある
代謝を促すポイントとして「優先順位があること」があります。
三大栄養素である「糖質」「脂質」「タンパク質」はエネルギー源となります。
運動において、エネルギーが必要になる場合、これらを利用してエネルギーを生み出すことになります。
優先順位として、一番エネルギーとして利用しやすいのが「糖質」になります。
とくに、短時間で多くの出力が必要な瞬発系の運動を行う場合に、メインのエネルギー源となります。
次に「脂質」が利用されます。
とくに、出力が低い低強度の運動や、長時間の持久系の運動をする場合に、脂質がメインに利用されます。
ちなみに、「タンパク質」は、体の構造をつくる材料として有名ですが、エネルギー源としても利用される場合があります。
とくに、タンパク質を多く摂り過ぎた場合、糖質や脂質などの他のエネルギー源が不足している場合などに、タンパク質がエネルギー源として利用されます。
ただし、タンパク質がエネルギー源として利用されると、体の代謝に必要な酵素や筋肉や臓器などの体の構造を作るのに回せなくなってしまうおそれがあります。
とくにトレーニングを行う場合は、エネルギー源が不足して、タンパク質が使われるようになると、トレーニング効果が低下したり、リカバリー不足につながります。
糖質や脂質などのエネルギー源を十分確保して、トレーニングすることが重要です。
代謝を促すポイントとして「優先順位があること」があります。
まとめ
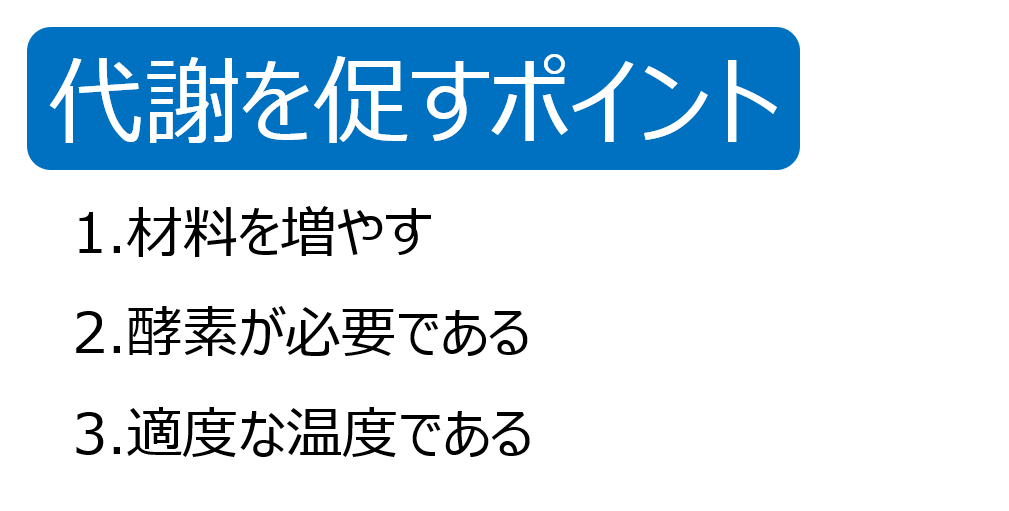
今回は「代謝を促すポイント」について説明しました。
この記事によって「代謝を促すポイント」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者




