結論ですが
乳酸性作業閾値とは、運動強度が高まるにつれて血中乳酸濃度が急激に上昇し始めるポイントのことです。
この記事は「マラソンを趣味にしている」ヒトに向けて書いています。
マラソントレーニングに対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「乳酸性作業閾値」についてわかります。
乳酸性作業閾値ってなんですか?
このような疑問にお答えします。
自分自身、ランニングが趣味で、マラソン大会によく出場しています。
タイムを上げるために日々トレーニングに励んでいます。
マラソン競技において、タイムを少しでも上げるために、日々の練習をがんばっているランナーは多いかと思います。
マラソン競技でタイムを上げる上で、様々な要素が重要になります。
トレーニング、運動、スポーツ、マラソン競技において、さまざまな「3大要素」というものがあります。
マラソン競技の3要素の一つに「乳酸性作業閾値」という考えがあります。
では、乳酸性作業閾値ってなんですか?
ということで、今回は「乳酸性作業閾値」について説明していきます。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
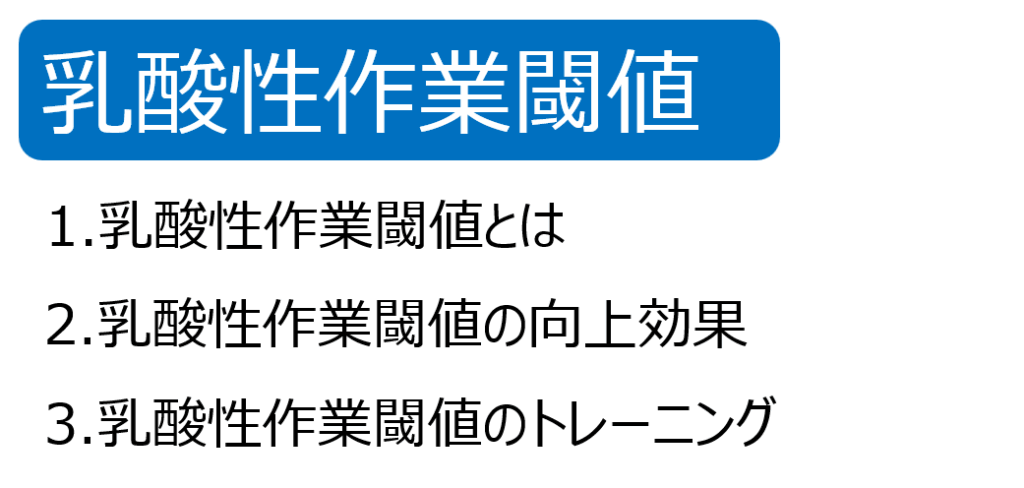
1.乳酸性作業閾値とは
乳酸性作業閾値とは、運動強度が高まるにつれて血中乳酸濃度が急激に上昇し始めるポイントのことです。
運動負荷が一定のレベルに達すると、乳酸の産生量が消費量を上回るようになり、血中乳酸濃度が急激に上昇し始めます。この上昇が始まるポイントが「乳酸性作業閾値(LT)」になります。
運動強度が高まっていくと、エネルギー源は、糖質だけでなく脂質も利用できる「有酸素性エネルギー代謝」から、糖質のみ利用できる「無酸素性エネルギー代謝」へと変化します。
乳酸性作業閾値は、「有酸素性エネルギー代謝」から「無酸素性エネルギー代謝」への切り替えのポイントでもあります。
つまり、酸素供給が間に合わないにも関わらず、筋肉を動かし続ける能力が乳酸性作業閾値に反映されます。
ちなみに、乳酸は「原因」ではなく「結果」です。
血中の乳酸濃度が高まると、疲労していることから、以前は「乳酸が疲労物質の原因」だと考えられていました。
しかし、代謝経路の中で「乳酸」はエネルギーを産生するために重要な物質です。
乳酸を利用してエネルギーを生み出しますが、運動の強度が高くなると、その対応が追いつかず、血中の乳酸濃度が高まる「結果」になるのです。
そのため、強度の高い激しい運動をすると、疲労するとともに乳酸濃度が高まる状態になるのです。
乳酸性作業閾値とは、運動強度が高まるにつれて血中乳酸濃度が急激に上昇し始めるポイントのことです。
2.乳酸性作業閾値の向上効果
乳酸性作業閾値が向上すると、ミトコンドリア増加、毛細血管の発達、脂質代謝の向上などの効果が期待できます。
トレーニングによって、乳酸性作業閾値が向上すると、酸素をより効率的に利用できるように、そして乳酸をエネルギーとしてより利用できるように「ミトコンドリア」が増えます。
また、全身の毛細血管は発達し、酸素や乳酸がより効率的に運ぶことができるようになります。
さらに、脂肪をエネルギーとして利用する能力が向上することで、乳酸が産生される糖代謝を抑えることにつながり、乳酸濃度の上昇を抑えてくれます。
乳酸性作業閾値が向上すると、ミトコンドリア増加、毛細血管の発達、脂質代謝の向上などの効果が期待できます。
3.乳酸性作業閾値のトレーニング
乳酸性作業閾値のトレーニングとして「高強度インターバル」「Tペース付近のランニングトレーニング」などがあります。
乳酸性作業閾値を高めるためには、「有酸素性エネルギー代謝」から「無酸素性エネルギー代謝」に移行するような運動強度の高いトレーニングが必要です。
ただし、運動強度が高すぎると、運動時間が短くなるため、トレーニングに落とし込むにあたって工夫する必要があります。
高強度インターバルトレーニングは、名前の通り強度の高い運動になり、乳酸性作業閾値を高めてくれます。
「強度の高い運動」と「休息」を繰り返して行われます。
インターバルトレーニングとして、短い休息をはさむことによって、高強度の運動を断続的に続けることができ、乳酸性作業閾値を高めてくれます。
逆説的ですが、高い運動負荷を、より長い時間かけるために「インターバル」という手法を用いているのだと理解しております。
高強度インターバルトレーニングの有名なものとして「タバタ式トレーニング」があります。
これは、「20秒間の高強度運動」と「10秒間の休息」を1セットとして、8セット行います。
高強度運動として、ランニングをターゲットとして「全力ダッシュ」でも良いですし、バイクで「全力こぎ」でも良いでしょう。
また、「バーピー」「ランジジャンプ」「マウンテンクライマー」「なわとび」などの種目もオススメです。
高強度運動の時間や休息時間を変えて、自分のキャパに見合った負荷設定にして取り組みましょう。
なお、ダニエルズ式の5つのペースとして
「E(Easy)ペース」
「M(Marathon) ペース」
「T(Thresold)ペース」
「I(Interval)ペース」
「R(Repetition)ペース」
があります。
そのうち、「Tペース付近」の比較的強度の高いトレーニングを行うことによって、乳酸性作業閾値を高めてくれます。
また、「Iペース」や「Rペース」などの強度の高いトレーニングによっても、乳酸性作業閾値を高めてくれますが、運動時間は短くなってしまうので、他の目的にも応じて計画を立てると良いかと思います。
ちなみに、血中乳酸値(2.0mmol)あたりの運動強度である「LT1」では、無酸素性エネルギー代謝への刺激は不十分かもしれません。
血中乳酸値(4.0mmol)あたりの運動強度である「LT2」(OBLA)では、無酸素性エネルギー代謝に十分刺激を与えられ、乳酸性作業閾値を効率的に高めてくれるでしょう。
LT1は、60分間走り続けられる運動強度
LT2は、45分間走り続けられる運動強度
が目安になります。
個人的には、VDOT64くらいであり、LT1あたりは「Tペース付近より遅め」(3’35”/kペース)、LT2は「Tペース(3’29”)付近」(3’30”/kペース)くらいが目安になります。
乳酸性作業閾値のトレーニングとして「高強度インターバル」「Tペース付近のランニングトレーニング」などがあります。
まとめ
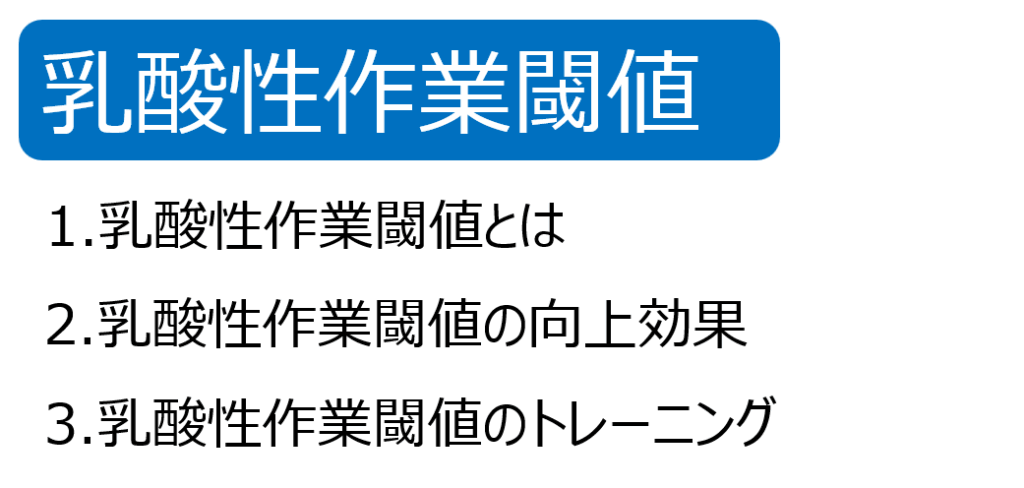
今回は「乳酸性作業閾値」について説明しました。
この記事によって「乳酸性作業閾値」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/


