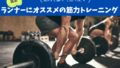・速く走るための練習メニューが知りたいです。
・マラソントレーニングにはどのようなものがありますか?
・具体的にどのような練習をすればいいですか?
この記事を読むことによって、速く走るためのトレーニングメニューが分かり、マラソンのタイムを伸ばすことができます。
私はドクターランナーの立場として、マラソンのトレーニングメニューに関して、スポーツ科学とメディカル科学の両面から調べてきました。
速く走るためには、トレーニングの目的を理解した上で行うことで、より効率的に速く走ることができます。
反対に、トレーニングを理解せずに練習をおこなっても、せっかくのトレーニング効果を無駄にしてしまう可能性があります。

トレーニングの目的を理解した上で、日々の練習をおこなうことが大切です。
「ランニングフォーム」はとても大切です。
トップランナーでは、見ていてキレイな走りをするかと思います。
マラソン競技において、理想的なランニングフォームを手に入れることによって、より少ないエネルギーでより速く走ることができます。
では、理想的なランニングフォームってどんなものでしょうか?
また、理想的なランニングフォームのために、どのようなトレーニングを行えばいいですか?
ということで、今回は「ランニングフォームのポイントとトレーニング」について説明します。
ランニングフォームのポイント
効率の良いフォーム

ランニングフォームのポイントとして「効率の良いフォーム」があります。
消費されるエネルギーが最小限で、最大限の推進力を生み出すようなランニングフォームが理想的です。
ランニング動作において、最も力を発揮するのは、地面と接地する局面です。
接地する局面で、伸張反射をうまく利用し、タイミングよく力を発揮し、全身の筋肉の協調運動によって、効率的に前に進む方向にもっていくことがポイントになります。
反対に、力を発揮しないで良いときには、余計な力を抜いて、無駄なエネルギーを消費させずにするようにします。
・接地局面で足関節の角度を固定する
・膝を前に出す
・地面からの反発を推進力に変える
・重心の上下動やブレを少なくする
・余計な力を抜く
など意識するといいでしょう。
大きな筋力を動員する

ランニングフォームのポイントとして「大きな筋力を動員すること」があります。
小さな筋肉に比べて、大きな筋肉の方が発揮される筋力が高いです。
大きな筋力をしっかりと使って、より速く、より長く走り続けることができます。
とくに、ランニングにおいて、体幹の筋肉や、肩関節・股関節まわりの大きな筋肉を使うことが重要です。
脚先ばかりの「ちょこちょこ走り」ではなく、全身の筋肉をダイナミックに動員した「大きくコンパクトな走り」が理想的です。
・適切に腕振りをして推進力を生み出す
・股関節まわりの大きな筋肉を使う
・地面からの反発を利用する
などが重要です。
ストレスの少ない動き
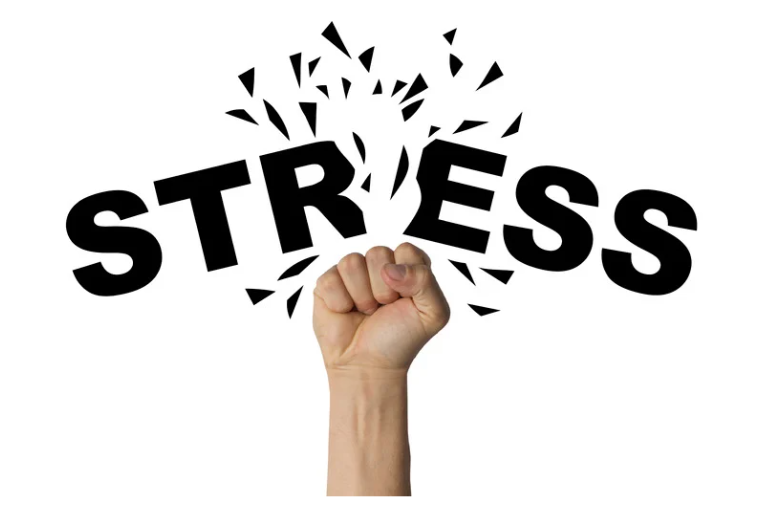
ランニングフォームのポイントとして「ストレスの少ない動き」があります。
今まで体に身に染みたフォームだったり、自分の体の筋肉や骨のバランス、生活動作でのクセなど、一人一人に個人差があります。
そして、その人にとって「最適なフォーム」は違います。
いくら良いフォームで、エネルギー効率が良くても、自分の中で違和感があれば長続きしません。
その違和感が脳でストレスと感じ取るため、エネルギーが消耗されてしまい「42.195km」という長い距離を走ることは難しくなるでしょう。
反対に、トレーニングによる反復練習によって、「理想的な効率の良いフォーム」を叩き込むことができます。
キーワードは「楽に前に進む感覚」が大事だと感じます。
自分の中でしっくりとくる、ストレスの少ないフォームを追い求めていくことが大切です。
効率的に進むこと

ランニングフォームのポイントとして「効率的に進むこと」があります。
マラソン競技の目標は単純です。
42.195kmという距離を走るタイムを競うことになります。
走る動作によって、体をより速く移動させることが大切です。
人の体を物体に置き換えると、「物体の重心」をロスなく、最短距離で移動させることが必要とされます。
・上下動が激しい
・グネグネと蛇行する
・体がぶれてしまう
このような動きが入ると、重心が無駄に移動する「ロス」が発生してしまうため、その分効率が低下します。
なるべく、前にスムーズに、無駄な動きを最小限に抑えて、重心移動させると、効率的に前に進むことができます。
最適なランニングフォームの条件として「効率的に進むこと」があります。
余計なエネルギーを使わないこと

ランニングフォームのポイントとして「余計なエネルギーを使わないこと」があります。
同じペースで走るにしても、消費されるエネルギーを少なくおさえることによって、体力を温存しながら走ることができます。
・肩に力を入れすぎている
・地面からの反発を殺してしまう
・キツイ場面で上体がぶれてしまう
このような動きでは、エネルギーを無駄に使ってしまいます。
基本的には、余計な力を抜いてリラックスした状態で走るといいでしょう。
着地局面では足関節の角度を固定し、全身の筋肉の協調運動によって、地面からの反発を推進力に変えることで省エネで走ることができます。楽に前に進む感覚が重要です。
呼吸が荒くなって、キツイ場面でも、しっかりと耐えて上体をブレないでフォームを維持することで、余計なエネルギーを消耗せずに済みます。
最適なランニングフォームの条件として「余計なエネルギーを使わないこと」があります。
違和感がないこと

ランニングフォームのポイントとして「違和感がないこと」があります。
いくら理想的なフォームだといっても、自分の中で違和感を感じていたら、42.195kmという長い距離をそのフォームで走ることができません。
ケニア人の速い人のフォームを真似しても、残念ながら違和感があって走れないなんてことも多々あります。
日本人との骨格の違いなどがあったり、今まで走ってきて作られてきたフォームなどがあります。
脳にインプットされているフォームと離れていては、脳にストレスがかかってしまい、無駄にエネルギー消費されてしまい、残念ながらうまく走れないでしょう。
もちろん、ドリルなど動き作りを取り入れて、理想的なランニングフォームを追求していくことも重要ですが、自分にとって違和感がないことが大切です。
反対に、違和感がなくなるまで、しっかりと理想的なランニングフォームを作っていくことが重要になります。
最適なランニングフォームの条件として「違和感がないこと」があります。
上半身との連動

ランニングフォームのポイントとして「上半身との連動」があります。
ランニングにおいて、走る動作をおこなうとき、脚が動いているので下半身のみに注目しがちです。
体全体をより効率的に前に進めることを考えると、実は上半身も使うことが大切です。
とくに、体幹と四肢をつないでいる「股関節」だけでなく「肩関節」の動作も重要です。
体幹の力を四肢に伝えるために、「股関節」の運動だけでなく、「肩関節」つまり肩甲骨周囲の運動も大切になります。
下半身と上半身の連動がうまくいかないと、上体のブレにつながり、重心移動がスムーズにいかず、エネルギーロスが発生してしまいます。
個人的には、股関節から脚が生えているのではなく、肩関節から脚が生えているイメージをしています。
肩から脚が生えていると、脚が長くストライドが長くなるような感覚になります。
自然と、肩甲骨周りの筋肉も動員することができて、上半身と連動させて、体幹ふくめ全身を使って走ることができます。
最適なランニングフォームの条件として「上半身との連動」があります。
協調運動

ランニングフォームのポイントとして「協調運動」があります。
ランニングの走る動きにおいて、ずっと力を入れっぱなしではありません。
力を入れる局面もあれば、力を抜く局面もあります。
とくに地面に足をつく「接地局面」では、地面からの反発を前に進む推進力にうまく変えるように発揮します。このときに、反対側の脚は、膝から前にしっかりと進むような動作を行います。
このときに、全身の筋肉を駆使して、接地時間をより短く、そして最大のエネルギーが発生するように動員すると、より大きな力を利用して走る動作をおこなうことができます。
このときに、全身の筋肉の力が分散されると、エネルギーがロスが生じてしまうため、「協調運動」をしてタイミング良く力を発揮することが大切になります。
反対に、接地局面以外の場面では、うまく力を抜いて、エネルギーを温存させるといいでしょう。
このような動きを覚えるには、頭で考えてもうまくいかないため、コツコツと動き作りを行うとともに実際の自分の走りで少しずつ変えていくしかありません。
最適なランニングフォームの条件として「協調運動」があります。
伸張反射を利用すること

ランニングフォームのポイントとして「伸張反射を利用すること」があります。
伸張反射とは、筋肉が引き伸ばされることによって、力を入れる意識をしなくても自然と筋肉が収縮する現象のことを言います。
筋肉の中でも「筋紡錘」という構造がある筋肉において起こります。
とくに、走る動作において、股関節の屈曲に関係する「大腿四頭筋」、股関節の伸展に関係する「ハムストリングス」、足関節の屈曲に関係する「下腿三頭筋」(ヒラメ筋・腓腹筋)などの伸張反射をうまく利用することが重要です。
伸張反射にともなう筋収縮に対して対抗せずに、前に進める推進力につなげるようにすることが大切です。
とくに、プライオメトリック運動という、ジャンプ系を中心とした運動によってトレーニングすることができます。
筋肉の伸張反射を利用できると、短時間で最大限の力を発揮することができます。
最適なランニングフォームの条件として「伸張反射を利用すること」があります。
ランニングフォームのトレーニング
ドリル

マラソンフォームのトレーニングとして「ドリル」があります。
ドリルでは、様々な動きを取り入れて、自分にとって最適な走るフォームを身につけるためのトレーニングです。
・もも上げ
・バウンディング
・トロッティング
・スキップ
・ハイニースキップ
・ギャロップ
などの種目があります。
走る動作の要素を分解して確認することができます。
さらに、足の動かし方・さばき方・反発の感覚など脳に様々な刺激が入るため脳神経系を研ぎ澄まされる効果があります。
ランニングエコノミーのトレーニングとして「ドリル」があります。
坂ダッシュ

マラソンフォームのトレーニングとして「坂ダッシュ」があります。
坂ダッシュでは、上り坂をダッシュして駆け上がります。
平地と違って、走りの動きにロスがあると、うまくスピードにのせて走ることができません。
・重心移動をスムーズにする
・腕振りをしっかりとする
・膝を上げるイメージでダッシュする
などを意識すると良いでしょう。
坂ダッシュは、だいたい、50m~150mくらいの距離を、3~10本程度おこないます。
追い込む練習ではなく、あくまで走りのフォームを確認するのが目的なので、しっかりとリカバリーして一本一本集中して取り組みましょう。
ランニングエコノミーのトレーニングとして「坂ダッシュ」があります。
ジャンプトレーニング

マラソンフォームのトレーニングとして「ジャンプトレーニング」があります。
ジャンプトレーニングでは、ジャンプをするトレーニングです。
地面からの反発を利用するとともに、伸張反射を活用することがコツです。
伸張反射とは、筋肉が引き伸ばされることによって、力を入れる意識をしなくても自然と筋肉が収縮する現象のことを言います。
筋肉の中でも「筋紡錘」という構造がある筋肉において起こります。
・股関節の屈曲に関係する「大腿四頭筋」
・股関節の伸展に関係する「ハムストリングス」
・足関節の屈曲に関係する「下腿三頭筋」(ヒラメ筋・腓腹筋)
などの筋肉が走る動作において重要です。
ジャンプトレーニングでは、接地局面で伸ばされた筋肉が、伸張反射によって収縮し飛ぶ動作をすることができます。
とくに、ランニングにおける接地局面のトレーニングになります。
伸張反射による筋収縮や、全身の筋肉の協調運動などを利用して、より高く飛ぶようにすることで、接地局面の感覚を磨くことができます。
ジャンプトレーニングは、足への衝撃がくるため、できるだけ土や芝の上で行いましょう。
また、ボックスジャンプや、ハードルジャンプ、ラダーなどを使用してアレンジしてもいいでしょう。
ランニングエコノミーのトレーニングとして「ジャンプトレーニング」があります。
ウインドスプリント

マラソンフォームのトレーニングとして「ウインドスプリント」があります。
ウインドスプリントは、8割くらいの力で、気持ちいいと感じる心地の良いスピードで走ることです。流しなどとも呼ばれます。
ウインドスプリントでは、だいたい50m-150mくらいの距離を走ります。
余裕のあるスピードで、フォームを意識して走ることができます。
追い込む練習ではなく、あくまで、走りのフォームを確認するのが目的なので、しっかりとリカバリーして一本一本集中して取り組みましょう。
本番のトレーニングの前のウォーミングアップとして取り入れてもいいですし、
トレーニングの最後に、動きの確認をするために行ってもいいでしょう。
ランニングエコノミーのトレーニングとして「ウインドスプリント」があります。
ラダー

マラソンフォームのトレーニングとして「ラダー」があります。
ラダートレーニングでは、ラダーという「はしご状」になったものを置いて、様々な動きをします。
・両足ジャンプ
・スラロームジャンプ
・ツイストジャンプ
・ももあげ
・サイドステップ
・ステップ
・アウトインインアウト
などの種目があります。
上半身との連動、足の動かし方、さばき方などを様々な動きを習得することができます。
ランニングエコノミーのトレーニングとして「ラダー」があります。
ミニハードル

マラソンフォームのトレーニングとして「ミニハードル」があります。
ミニハードルトレーニングでは、背の低いハードルを何個か置いて、様々な動きをします。
両足ジャンプ
片足ジャンプ
抱え込みジャンプ
バウンディング
ホッピング
などの種目があります。
ハードルを使用して、主にジャンプするトレーニングになるため、プライオメトリック運動になります。伸張反射の利用なども促すことができます。
コツとしては、なるべき短い接地時間で、より高く飛ぶように意識することです。
また、足への衝撃がくるため、できるだけ土や芝の上で行いましょう。
ランニングエコノミーのトレーニングとして「ミニハードル」があります。
まとめ
今回は「マラソンフォームのトレーニング」について説明しました。
この記事によって「マラソンフォームのトレーニング」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者