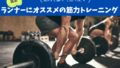・速く走るための練習メニューが知りたいです。
・マラソントレーニングにはどのようなものがありますか?
・具体的にどのような練習をすればいいですか?
この記事を読むことによって、速く走るためのトレーニングメニューが分かり、マラソンのタイムを伸ばすことができます。
私はドクターランナーの立場として、マラソンのトレーニングメニューに関して、スポーツ科学とメディカル科学の両面から調べてきました。
速く走るためには、トレーニングの目的を理解した上で行うことで、より効率的に速く走ることができます。
反対に、トレーニングを理解せずに練習をおこなっても、せっかくのトレーニング効果を無駄にしてしまう可能性があります。

トレーニングの目的を理解した上で、日々の練習をおこなうことが大切です。
では、マラソントレーニングのメニューにはどのようなものがありますか?
その目的を明らかにしながら「マラソントレーニングの具体的メニュー」について説明したいと思います。
レペティション

レペティションとは
レペティションとは、一定の距離を全力に近いペースで繰り返し走るトレーニングです。
全力に近いスピードで走り、休息をはさんで、次の疾走につなげていき、
「全力疾走→休息→全力疾走→休息→…」と繰り返す練習です。
不完全な休息でつなぐインターバルトレーニングとは違い、レペティションでは、しっかりと休息をとって体を回復させてから、次の疾走へとつなげます。
レペティションの目的
・最大スピード
・無酸素性作業能力
・ランニングエコノミーの向上
レペティションでは、速いスピードが出るので、速筋が刺激されて「スピード」が磨かれます。
また、酸素の供給が間に合わない状態で動くので「無酸素性作業能力」も鍛えられます。
さらに、速いランニングの動作によって、効率の良いフォームが身につき「ランニングエコノミー」が向上します。
レペティションのメニュー
・200m(r200mjog)*4-12本 1-3set
・400m(r400mjog)*4-10本 1-3set
・200m-200m-400m(r200mjog)*4-8本 1-2set
疾走時間は、「2分間をこえない時間」で行うため、距離は「200m~800m」が目安になります。
疾走距離と同じくらい(それ以上)のjogを入れて、休息を十分にとって、一本一本ほぼ全力で走り切るようにしましょう。
レペティションのポイント
・ペースは全力疾走
・レストは十分とること
・疾走時間は2分以内
インターバルトレーニング

インターバルトレーニングとは
インターバルトレーニングとは「速く走ること」と「ゆっくり走ること」を、くりかえし行うトレーニングです。
しっかりと休息をとるレペティションとは違い、インターバルトレーニングでは、不完全な休息をとって次の疾走につなげます。
ジョグでつないで、不完全な休息で、心拍数が戻りきる前に次の疾走へとつなぎます。
インターバルトレーニングのペースは、3kmから5kmのレースペースくらいが目安になります。
インターバルトレーニングの目的
・最大酸素摂取量の向上
・乳酸作業閾値の改善
・解糖系代謝の促進
インターバルトレーニングでは、とくに「最大酸素摂取量」(VO2max)が鍛えられ、単位時間あたりに取り込む酸素の量が増え、有酸素能力が向上します。
また、乳酸を処理して耐えられる能力である「乳酸性作業閾値」(LT値)の向上が期待できます。
さらに、解糖系という糖質を酸素なしでエネルギーを生み出す代謝経路が促進され、酸素が体内に足りない状況でも、運動を持続させる能力が向上します。
インターバルトレーニングのメニュー
・400m(r200mjog)*5-12本 1-3set
・1000m(r200mjog)*3-8本 1-2set
・3分間(r1-2分間jog)*3-8本 1-2set
インターバルトレーニングでは、速く走る区間が長くなるほど、ゆっくり走る区間が短くなるほど、運動強度は上がります。
また、疾走区間のペースや緩走区間のペースや距離、本数などを工夫することで、トレーニングの難易度を調整することができます。
インターバルトレーニングのポイント
・キツイと感じるペースで
・目安は10-12分間走のペースで
・レストは不十分な休息で
閾値走

閾値走とは
閾値走とは、乳酸閾値あたりのペースで走るトレーニングです。
ランニングのペースを上げていくと、血液中の乳酸の濃度が急に上昇するポイントがあります。
この地点が「乳酸閾値」であり、閾値走という名前がついています。
なお、閾値(Threshold)から「Tペース」や、乳酸閾値(Lactate Threshold)から「LT」などと呼ばれます。
閾値走のペースは、ハーフマラソンのレースペースくらいが目安になります。
閾値走の目的
・乳酸性作業閾値の改善
・乳酸の除去能力の向上
閾値走によって、発生する乳酸を除去できる能力が向上し、乳酸性作業閾値(LT値)が改善します。
他にも、LT値は「乳酸の発生をおさえること」によって改善します。
乳酸は、酸素が不足した状態でエネルギーを産生するときに発生します。
「最大酸素摂取量の向上」や「毛細血管の発達」など有酸素能力が高まると、乳酸の発生が抑えられます。
また、糖質がエネルギー利用すると乳酸が発生しますが、「脂質代謝の促進」によって乳酸の発生を抑えることができます。
閾値走のメニュー
・20分間走 (テンポ走)
・6km走 (テンポ走)
・5~6分間走(r1分jog)*4-8本 (クルーズインターバル)
・10~15分間走(r2分jog)*2-5本 (クルーズインターバル)
閾値走の方法は、「テンポ走」と「クルーズインターバル」の二つです。
テンポ走は、20分間程度の持続走です。
クルーズインターバルは、Tペースのランを短い休息をはさんで何本か繰り返します。
走行時間の目安は30分程度になります。
閾値走のポイント
・快適なキツさのペースで(ハーフマラソン程度)
・テンポ走は20分間走り切る
・クルーズインターバルは短い休息で
ペース走

ペース走とは
ペース走とは、一定の距離を決められたペースで走るトレーニングです。
ペース走は、同じペースで走る練習です。
ちなみに、ペース設定という観点から以下のようなトレーニング方法もあります。
・ペースを徐々にあげていく「ビルドアップ」
・ペースを徐々にさげていく「ビルドダウン」
・ペースを上げたり下げたりする「変化走」
ペース走の目的
・ペースコントロール力の向上
・レースペースの走動作の適応
ペース走の主な目的は、ペースを意識してトレーニングすることによって、ペースコントロール力が養われます。
また、レースペースに近いペースで行うことによって、本番のレースにおける「走る動き」に慣れることができます。
ペース走のメニュー
・5km~12km (ハーフマラソンペース)
・10km~16km(マラソンペース)
・15km~30km(やや遅めのマラソンペース)
トレーニングにおいては、実際のレースペースで走り切るのは難しいかと思います。
本番のレースより距離を短めに設定して、ペースを守って走り切るようにしましょう。
ペース走のポイント
・速めのペースを叩き込みたい場合はハーフマラソンペース
・レースが近いときには、マラソンペース
・距離を稼ぎたいときは、やや遅めのマラソンペース
などトレーニングの目的に応じて、ペース設定を工夫するようにしましょう。
距離走

距離走とは
距離走は、長い距離を走るトレーニングです。
20kmから30km程度の長い距離を走ります。
トップ選手だと、40km以上の長い距離を走ることもあります。
なお、ゆっくり長く走る「LSD」(Long Slow Distance)も距離走に入れる場合もありますが、ゆっくりペースでおこなうのが特徴になります。
距離走の目的
・長い距離に慣れること
・脂質代謝の促進
・長い時間走り続けるアシ作り
フルマラソン本番では「42.195km」というとても長い距離を走ることになります。
距離走によって長い距離に慣れておくと、距離に対する自信をもって本番にのぞむことができます。
なお、長い時間、運動し続けることになるため、糖質だけでなく脂質代謝も促されます。
また、長い距離を走ることで、高回数の筋トレになるため、走りに関係する筋肉が強化されます。
レース後半もバテない「アシ作り」につながります。
距離走のメニュー
・10km~15km(初心者)
・15km~30km(中級者)
・30km~40km(上級者)
距離走は、まずは呼吸が上がらない程度のゆっくりペースで、短い距離から始めます。
1~2週間に1回のイメージで、最初は10km、次は15km、その次の週は20kmという具合に、徐々に距離を伸ばしていきます。
最終的に40kmまでいけたら完璧ですが、初心者は20~30kmまでこなせれば十分でしょう。
距離走のポイント
・長い距離を走ること
・少しずつ距離を伸ばしていく
・余裕のあるペースで
タイムトライアル

タイムトライアルとは
タイムトライアルとは、ある距離をタイムを測って全力で走るトレーニングです。
距離を決めて、全力で走り切ることになります。
「タイムトライアル」略して「T.T.」などと言われます。
練習でタイムトライアルが行われる場合がありますが、マラソン大会などをタイムトライアル代わりに利用する場合もあります。
そして、究極のタイムトライアルは、レース本番ということになります。
タイムトライアルの目的
・今の実力を把握できる
・全力を出し切る力が身につく
・ペース感覚を養える
タイムトライアルを行うと、今の自分の実力を把握することができます。
現状を知ることで、本番に向けての課題や目標に対して足りない部分などが分かり、今後のトレーニング計画に活かすことができます。
レース本番に近い緊張感の中、タイムを少しでも縮めようと頑張って走るため、全力を出し切る力が身に付きますし、本番のペース感覚も養われます。
タイムトライアルのメニュー
・800m、1000m、1500m、1600m(最大スピード)
・3000m、5000m・10000m(スピード持久)
・12km・16km・20km(ペース走の要素)
以上のように、目的の応じて距離を設定し、全力を出し切って行いましょう。
走る場所は、陸上競技のトラックでもいいですし、公園の周回コース、河川敷の舗装路、不整地、土トラックを活用しましょう。信号などがなく、ノンストップで走れる環境で行いましょう。
タイムトライアルのポイント
・条件をなるべく同じにすること
・コンディションを把握しておくこと
・レースを活用すること
・気軽にチャレンジすること
タイムトライアルを定期的に行うと、自分の実力を把握することができます。
過去のデータと比較しやすいように条件をなるべく同じにしましょう。
気象条件(温度、湿度、風力など)のコントロールは難しいですが、自分のコンディション(疲労具合、カーボローディングなど)は合わせやすいかと思います。
タイムトライアルを行ったコンディションは記録しておくと、後から比較しやすくなります。
また、普段のトレーニングでは気合が入らないタイプでは、是非とも本番のレースを活用してみましょう。
変なプレッシャーを感じず、気軽にチャレンジして、今の実力を把握することは大切です。
まとめ
今回は「マラソントレーニングの具体的メニュー」について説明しました。
速く走るためには、トレーニングの目的を理解した上で行うことが大切です。
反対に、目的を理解せずに練習をおこなっても、せっかくのトレーニング効果を無駄にしてしまう可能性があります。
この記事によって「マラソントレーニングの具体的メニュー」についての理解が深まり、より速く走れるようになる人が一人でも多くなることを願っています。
この記事の著者