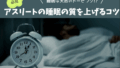マラソンのタイムを伸ばすために日々トレーニングを行っているランナー向けの記事です。
- すぐに疲れてしまう
- 朝起きるのがつらい
- いつものトレーニングがキツイ!!
その不調、じつは「リカバリー不足」が原因かもしれません。
私はドクターランナーの立場として、長年マラソン競技をおこなっており、日々トレーニング内容だけでなく、睡眠・食事内容などの記録をつけています。
その記録を見返してみると「リカバリー不足」で調子が悪くなるということを実感しております。

適切にリカバリーを促すことによって、競技パフォーマンスは上がります。
この記事を読むことによって、リカバリー力を高めることができ、日々のトレーニングの質を高め、自己ベストを更新することにつながります。
反対に「リカバリー」に関する知識がないと、慢性的な疲労によってトレーニングの調子が上がらず、せっかくのトレーニングが無駄になってしまう可能性があります。
さあ、「リカバリーを促す栄養素」について見ていきましょう。
リカバリーを促す三大栄養素
糖質

リカバリーを促す栄養素として「糖質」があります。
糖質は、体のエネルギー源となる栄養素であり、細胞レベルでリカバリーも促してくれます。
トレーニングによって枯渇した糖質を補給することで、エネルギーがチャージされてリカバリーが促されます。
また、糖質を摂取することによって、血糖値が上がり、「インスリン」というホルモンが分泌されます。インスリンの作用によって、血液中の糖は細胞内に取り込まれて、血糖値を下げてくれます。
このときに「アミノ酸」などの物質も一緒に細胞内に取り込まれるため、細胞レベルで修復が促されリカバリーが促されます。
タンパク質

リカバリーを促す栄養素として「タンパク質」があります。
タンパク質は、分解されてアミノ酸として、体内に消化吸収されて、筋肉などの材料となります。
トレーニングによってダメージを受けた筋肉などを修復してくれるため、リカバリーを促してくれます。
トレーニング後は、タンパク質を糖質と一緒に適度な量を摂取するとともに、アミノ酸スコアが良い食品を選んで摂取するようにしましょう。
肉、魚、たまご、大豆・大豆製品、牛乳・乳製品などがアミノ酸スコアが良い食品です。
脂質

リカバリーを促す栄養素として「脂質」があります。
脂質は、「エネルギー源」になるだけでなく、「細胞膜の成分」「脂溶性ビタミンの供給」などの働きをします。
脂質は悪者扱いされることが多いですが、「細胞膜の材料」であるため、トレーニングによって損傷した筋肉などを細胞レベルでリカバリーしてくれます。
また、脂溶性ビタミン(ビタミンD・A・K・E)の吸収も促してくれます。
リカバリーを促すビタミン
ビタミンは、生物の体にとって必要な有機物のうち、炭水化物・タンパク質・脂質以外のものをいいます。
ビタミンは、微量でもその役割は重要であり、ヒトの体の中で三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)の代謝を助ける働き、体の機能調整など行い、リカバリーを促してくれます。
ビタミンB群

リカバリーを促す栄養素として「ビタミンB群」があります。
ビタミンB群(B1, B2, B6)は、三大栄養素のエネルギー代謝をサポートする助ける働きがあります。
・ビタミンB1は「糖質」
・ビタミンB2は「脂質」
・ビタミンB6は「タンパク質」
のように、それぞれエネルギー代謝をサポートします。
ビタミンB群は、豚肉・うなぎ・まぐろ・かつお・大豆・えだまめ・玄米などに多く含まれています。
ビタミンC

リカバリーを促す栄養素として「ビタミンC」があります。
ビタミンCは、疲労や老化を引き起こす酸化ストレスをおさえる働きがあります。
炎天下で直射日光の強い環境の中、ランニングをすると、日光による紫外線・酸化ストレスなどのダメージが加わります。
ビタミンCの抗酸化作用でその修復してくれるため、リカバリーを促してくれます。
ビタミンCは、レモンやグレープフルーツなどの柑橘類、ブロッコリー・菜の花・レンコン・ほうれん草などに多く含まれています。
リカバリーを促すミネラル
ミネラルは、体を構成する「酸素・炭素・水素・窒素」の主要4元素以外のものをいいます。
ミネラルは、体の機能を維持したり、調整する働きをするため、リカバリーを促してくれます。
カルシウム

リカバリーを促す栄養素として「カルシウム」があります。
カルシウムは、骨をつくるだけではなく、細胞の機能を正常に保つ働きや筋肉の収縮・神経の働きに関係しております。
不足すると、筋肉や神経が正常に収縮しなくなり、リカバリーが遅れてしまいます。
カルシウムは、牛乳・乳製品、小魚・魚介類、小松菜などに多く含まれています。
鉄

リカバリーを促す栄養素として「鉄」があります。
鉄は、血液の中にある赤血球のヘモグロビンの材料になり、全身に酸素を送り届ける役割をします。
鉄が不足すると「鉄欠乏性貧血」につながり、競技パフォーマンスが低下するのは勿論、立ちくらみ・疲労感・食欲低下などの症状を起こします。
ランニング動作によって、鉄分が不足しがちなので、積極的に摂取したい栄養素です。
鉄は、動物性の豚レバー・鶏レバー・牛レバー・まぐろ・かつお、植物性の小松菜・ほうれんそう・春菊・大豆・ひじきなどに多く含まれています。
亜鉛

リカバリーを促す栄養素として「亜鉛」があります。
亜鉛は、古くから滋養強壮に良いとされており、疲労回復を促す栄養として有名です。
また、亜鉛が不足すると、味覚障害、免疫力低下、皮膚炎、口内炎、脱毛症、食欲低下、生殖機能の低下、慢性下痢などがおこります。
亜鉛は、カキ・ほたて・煮干しなどの魚介類、牛肩ロース・牛もも肉・鶏レバーなどの肉類、ナッツ類などの食材に多く含まれています。
リカバリーを促す栄養素
クエン酸

リカバリーを促す栄養素として「クエン酸」があります。
クエン酸は、柑橘類などに含まれる物質であり、体内の乳酸を分解してエネルギーを生み出すのに必要な成分です。
激しい運動を行うと、乳酸が蓄積し、体内が酸性に傾くため、疲労を感じます。
クエン酸を摂取することで、乳酸を分解し、エネルギーを生み出してくれて、リカバリーを促してくれます。
クエン酸は、レモンやグレープフルーツなどの柑橘類、キウイ、梅干し、お酢など、酸っぱい食品に含まれています。
オルニチン

リカバリーを促す栄養素として「オルニチン」があります。
オルニチンは、肝臓での解毒する作用を促し、リカバリーを促します。
肝臓の中で「オルニチン回路」というものがあり、アンモニアなどの解毒を促すとともに、エネルギー産生をスムーズにする働きがあり、リカバリーを促してくれます。
オルニチンは、とくにアルコールを摂取した後に伴う疲労感を回復させる効果があり、二日酔い防止効果が有名です。
オルニチンは、しじみが有名ですが、他にも、キハダマグロ・ひらめ、チーズ・パンなどの食品に多く含まれています。
アリシン

リカバリーを促す栄養素として「アリシン」があります。
アリシンは、滋養強壮や疲労回復で有名な「にんにく」に多く含まれています。
アリシンは、ビタミンB1の働きをサポートをし、糖質からエネルギーを生み出すのをスムーズにし、リカバリーを促してくれます。
他にも、免疫力アップ、がんの予防、動脈硬化・血栓症の予防効果などがあります。
アリシンは、にんにく以外にも、たまねぎ・ながねぎ・にら・らっきょうなどの食品に多く含まれています。
コエンザイムQ10

リカバリーを促す栄養素として「コエンザイムQ10」があります。
よくサプリメントなどで「コエンザイムQ10」を耳にするかと思います。
コエンザイムQ10は、ミトコンドリアの中でエネルギーを作り出す「補酵素」であり、「ユビキノン」や「コエンザイムQ」などとも呼ばれます。
コエンザイムQ10は、エネルギー代謝をスムーズにするためリカバリーを促してくれます。
他にも、皮膚のしわ・たるみなどを改善し、若々しい肌に保つ効果があり、美容目的で使用される場合が多いです。
コエンザイムQ10は、サプリメントだけでなく、いわし・さばなどの青魚、牛肉・豚肉、ナッツ類などの食品に多く含まれています。
GABA

リカバリーを促す栄養素として「GABA」があります。
GABAは、アミノ酸の一種であり、リラックス効果があるため、リカバリーを促してくれます。
GABAは、γアミノ酪酸(Gamma Amino Butyric Acid)の略称であり、アミノ酸の一種です。
興奮、緊張、イライラなどの交感神経の作用を落ち着かせる効果があり、「副交感神経優位」になり、リラックス効果があります。
トレーニングなどによるストレスが和らぎ、睡眠の質を上げたりするため、リカバリーが促されます。
GABAは、サプリメントだけでなく、トマト、発芽玄米、なす・ケール・パプリカなどの野菜類などに多く含まれています。
まとめ
今回は「リカバリーを促す栄養素」について説明しました。
三大栄養素はもちろん、さまざまな栄養素がリカバリーを促してくれます。
日々の食事を意識することによって、リカバリー力を高めることによって、より速く走れるようになり自己ベストを更新することにつながります。
われわれの体は「食べたもの」から出来ています。
そして、アスリートは「体」が資本です。
「医食同源」という言葉があるように「食」というものはとても重要です。
さらなる高みを目指しているランナーは、日々の食事を是非とも見直してみましょう。
この記事によって「リカバリーを促す栄養素」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことができれば幸いです。
この記事の著者