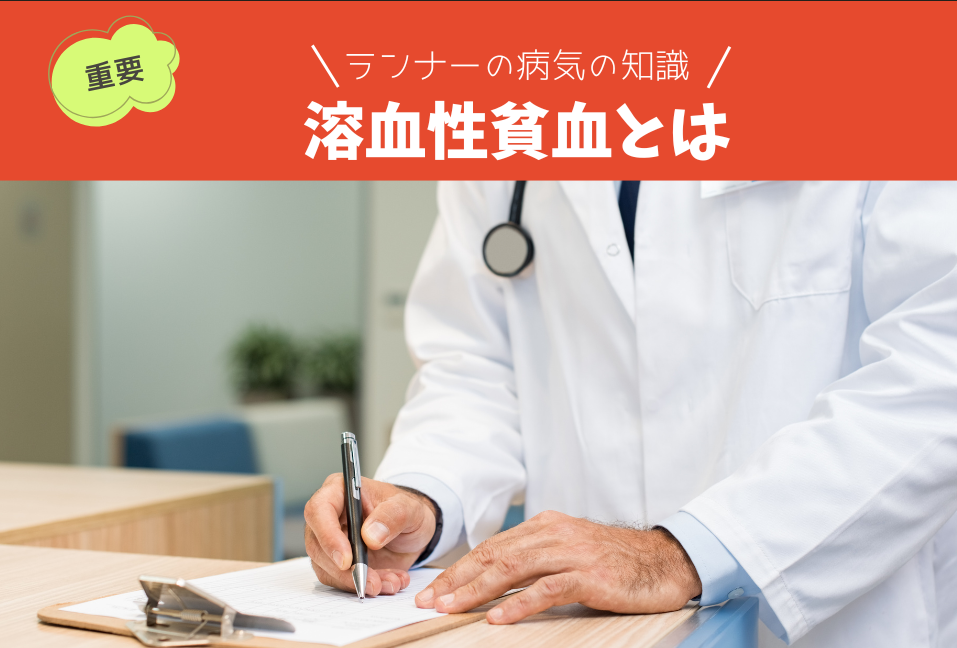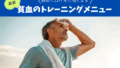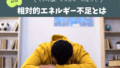溶血性貧血って何ですか?
このような疑問にお答えします。
スポーツ選手でパフォーマンスが上がらない
常に体がだるい感じがする
すぐに疲れを感じる
このような症状の場合、スポーツ貧血が隠れている場合があります。
血液検査をして、赤血球やヘモグロビンなどの項目を確認して、貧血なのか診断されます。
スポーツにおける貧血といえば、鉄欠乏性貧血を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実は溶血による貧血も無視できません。
とくにランナーの場合、溶血にともなう貧血に陥っているケースが多々あります。
では、溶血って何でしょうか?
ということで、今回は「溶血」について説明していきます。
溶血性貧血とは
溶血性貧血とは、溶血によって貧血をきたす病気です。
そもそも、溶血とは、寿命を迎える前の赤血球が、何らかの原因により破壊されることです。
赤血球は、血液中の細胞の一種であり、酸素を全身に運ぶ役割をします。
血液の中には、「赤血球」だけでなく「白血球」「血小板」などの細胞が含まれています。
そのうち赤血球は、酸素を全身に運ぶ役割をします。
なお、白血球は異物を除去する「免疫」の働き、血小板は出血したときに血液を止める「止血」の働きをします。
赤血球は、骨髄という場所で作られて、血管の中を「約120日間」循環した後、寿命がきたら脾臓や肝臓などで破壊されます。
寿命を迎える前の赤血球が、何らかの原因により破壊されることを「溶血」といいます。
溶血によって血液中の赤血球が低下する状態を「溶血性貧血」と呼びます。
「溶血性貧血」になると、全身への酸素を運搬する能力が低下します。
すると、運動を持続するのが困難となるため、マラソンなどの持久系競技のパフォーマンスが低下してしまうのです。
溶血とは、寿命を迎える前の赤血球が、何らかの原因により破壊されることです。
溶血性貧血の原因
血管内溶血
血管内溶血とは、血管内で赤血球が破壊される溶血がおこることです。
赤血球が壊される溶血が起こる場所として、「血管内」と「血管外」のパターンがあります。
血管内溶血は、血管の中において、赤血球が壊されます。
スポーツが原因の溶血においては、足裏への強い衝撃がかかると、赤血球が破壊されて貧血が起こります。
とくに、剣道での足の踏み込み、バレーボールなどジャンプ動作、マラソンなどの長時間の走る動作をおこなう運動によって、物理的な刺激によって血球が破砕されて「溶血」が起こります。
このときは「血管内溶血」が起こっています。
ちなみに、血液中の補体やリンパ球などの免疫細胞が赤血球の膜タンパクを攻撃してしまい、「血管内溶血」が起こる場合があります。
発作性夜間ヘモグロビン尿症、G6PD欠損症、ABO型不適合輸血などの疾患で「血管内溶血」が起こります。
血管内溶血とは、血管内で赤血球が破壊される溶血がおこることです。
血管外溶血
血管外溶血とは、血管内以外の場所で赤血球が破壊される溶血がおこることです。
赤血球が壊される溶血が起こる場所として、「血管内」だけでなく「血管外」のパターンがあります。
「肝臓」や「脾臓」「骨髄」などの場所で溶血が起こる場合があります。
赤血球は、骨髄という場所で作られて、血管の中を「約120日間」循環した後、寿命がきたら脾臓や肝臓などで破壊されます。
つまり、寿命を迎えた赤血球は、脾臓や肝臓などで自然と「血管外溶血」が起こります。
ちなみに、「肝臓」や「脾臓」「骨髄」内のマクロファージによって赤血球が貪食されてしまい、「血管外溶血」が起こる場合があります。
遺伝性球状赤血球症、自己免疫性溶血性貧血(AIHA)、ピルビン酸キナーゼ(PK)欠損症、鎌状赤血球症、サラセミアなどの疾患で「血管外溶血」が起こります。
血管外溶血とは、血管内以外の場所で赤血球が破壊される溶血がおこることです。
ランナーの溶血の原因
足裏への衝撃
溶血の原因として「足裏への衝撃」があります。
これは、足裏の衝撃によって赤血球が壊れやすくなることで、貧血です。
何度も足裏への衝撃が来るような「ランニング」だけでなく、剣道・バレーボール・ハンドボールなどの足裏に強い衝撃がかかるスポーツで起こりやすいです。
「運動性溶血性貧血」とも呼ばれます。
足裏への衝撃をおさえるために、トレーニング内容を工夫する必要があります。
たとえば、
筋力トレーニングを行う
エアロバイクを利用する
有酸素マシン(クロストレーナー、ステップヒル)を活用する
上り坂を利用してスピードをおさえる
アスファルトを避ける
などがあります。
アスファルトの上で、スピードを出すようなランニングトレーニングを行いたい場合には、短時間にとどめるようにしましょう。
溶血の原因として「足裏への衝撃」があります。
アシドーシス
溶血の原因として「アシドーシス」があります。
アシドーシスとは、体が酸性に傾いた状態のことをいいます。
血液が酸性に傾いた状態になると、酸によって赤血球がこわされやすい状態になって、溶血性貧血が起こりやすくなります。
「夜間発作性ヘモグロビン尿症」という病気がありますが、これは夜間睡眠中に呼吸が減少すると、血液中の二酸化炭素が増加して、軽度のアシドーシス状態になります。
すると、とくに夜間に赤血球が酸によって壊されてしまい、「溶血性貧血」が起こり、「ヘモグロビン尿」が認められるものです。
マラソントレーニングにおいては、とくに乳酸濃度が上がる領域「閾値」(LT値)といわれる以上のスピードで走ると、乳酸の蓄積によって体が酸性に傾き、溶血が起こりやすくなります。
アシドーシスによる溶血を防ぐために、「閾値」以下のスピードのランニングトレーニングを意識するといいでしょう。
また、「閾値」を越えるようなスピードのランニングトレーニングは短時間にとどめておくようにします。
ただし、自転車競技のアスリートにおいて、貧血になる選手は比較的少ないため、「アシドーシス」に加えて「足裏への衝撃」との組み合わせによって溶血性貧血につながるのではないかと個人的には考えています。
なので、「閾値」を越えるような負荷の高いトレーニングを行う場合には、エアロバイクなどを活用して代わりに行うのが良いかと考えております。
ちなみに、心拍数を目安に、エアロバイクの負荷や回転数の目安を決めて行っています。
溶血の原因として「アシドーシス」があります。
血流の増大
溶血の原因として「血流の増大」があります。
よく、採血するときに、シリンジを強く引いたときに溶血が起こることがあります。
これは、針の中で血液の流れが速くなってしまい、針の壁との摩擦によって赤血球が壊されてしまうためです。とくに、針の径が細い場合に起こりやすいです。
また、採取した血液の量が足りず、採血管の中が陰圧の状態だと、赤血球が壊されて溶血が進みます。
医療の現場では、このように赤血球は壊されやすいようなイメージがあります。
さて、激しい運動などを行うと、全身にエネルギー源や酸素をおくるため、心拍数は上がり、血液の流れは速くなります。
血流が速くなると、赤血球が血管の壁と擦れてしまい「溶血」につながります。
これをいうと、トレーニングをすること自体、怖くなってしまうかもしれません。
しかし、赤血球が壊されることもあれば、毎日新しい赤血球を作ることも行われています。
「赤血球の破壊」が「赤血球の産生」を上回ったときに、貧血(溶血性貧血)として現れてきます。
溶血性貧血になるには、長期間の血流のダメージだけでなく、足裏への衝撃・アシドーシスなど総合的なダメージの蓄積だと個人的には考えています。
自分のキャパシティーに見合ったトレーニング量を見定めること、しっかりとしたリカバリー計画を立てること、長いスパンで安全にトレーニングが継続できるように、トレーニング計画を見直すきっかけになるかと思います。
溶血の原因として「血流の増大」があります。
溶血を防ぐトレーニング
とくに、剣道・バレーボールなど足裏への強い衝撃がかかるスポーツや、マラソンなどの長時間の走る動作をおこなう運動によって、赤血球が破壊されて、「溶血性貧血」につながります。
なお、血液中のpHの変化によっても、赤血球が壊されてしまうと言われており、激しいトレーニングによって体が酸性に傾くと「溶血性貧血」につながります。
足裏への衝撃をおさえるために
- ランニング以外のトレーニング
- 足裏への衝撃を避けるトレーニング
- 踏み込み動作以外のトレーニング
- 短時間で集中してトレーニングする
- トレーニング量を落とす
- トレーニングの負荷を調整する
などの対策が考えられます。
赤血球を増やすポイントとして「溶血を防ぐこと」があります。
溶血を防ぐ医学的注意点
溶血を防ぐため「医薬品」に注意しましょう。
医薬品の中には、界面活性剤のような働きをして、赤血球の溶血を促してしまうものがあります。
とくに、高血圧の治療薬である「メチルドパ」、不整脈の治療薬である「キニジン」、血栓症予防薬である「チクロピジン」「クロピトグレル」などの医薬品に注意しましょう。
また、使用することは稀ですが、マラリアの薬である「キニーネ」などの医薬品によって溶血が起こる場合があり注意しましょう。
赤血球を強くするポイントとして「医薬品に注意すること」があります。
溶血を防ぐ食事
サポニン
赤血球を強くするポイントとして「サポニン」の過剰摂取に注意することがあります。
サポニンとは、植物の根や葉、茎などに含まれる成分であり、水と油を混ざり合わせやすくしてくれる「天然の界面活性剤」の成分です。
赤血球の膜は、リン脂質という油の成分で出来ています。
サポニンを過剰に摂取すると、サポニンの働きによって、赤血球の膜は不安定な状態となり、溶血を引きおこす場合があります。
ただし、サポニンには様々な健康効果があります。
血糖値の改善、血流の改善、むくみ・冷えの改善、コレステロールの除去、肝機能の向上、抗酸化作用などがあります。
サポニンは、大豆、高麗人参、ごぼう、アマチャヅル、緑茶、へちまなどに多く含まれています。
サポニンは健康効果があるため、適量を意識して、過剰摂取しないように摂取しましょう。
赤血球を強くするポイントとして「サポニン」の過剰摂取に注意することがあります。
亜鉛
赤血球を強くするポイントとして「亜鉛」の不足に注意することがあります。
亜鉛は、体内で生成できない必須微量ミネラルであり、体の代謝などを司っている酵素たんぱく質の構成要素として、さまざまな生体内の反応に関与している栄養素です。
亜鉛が不足すると、「溶血性貧血」だけでなく、「味覚・臭覚異常」「視覚の異常」「免疫力の低下」「脱毛」「粘膜障害」「生殖機能の低下」「創傷治癒の遅延」「骨粗しょう症」「糖尿病」「アレルギー疾患」などにつながります。
亜鉛は、牡蠣、あわび、たらばがに、するめ、かつお、さば、パプリカ、からすみ、牛肉、豚肉、大豆、エンドウ豆、小麦胚芽、卵、チーズなどの食品に多く含まれています。
赤血球を強くするポイントとして「亜鉛」の不足に注意することがあります。
ビタミンE
赤血球を強くするポイントとして「ビタミンE」の適量摂取があります。
ビタミンEは、脂溶性ビタミンの一つであり、強い抗酸化作用をもち、体内の脂質の酸化を防いだり、細胞膜を安定化する働きがあります。
ビタミンEが不足すると、赤血球の膜が不安定になるため、赤血球の膜が壊され「溶血」しやすい状態になると考えられます。
また、ビタミンE不足によって、動脈硬化や血栓症、高血圧、脂質異常症などになりやすく、神経や筋肉などの細胞が損傷され、冷え性・頭痛・肩こりなどの症状につながります。さらに、抗酸化力が低下するため、紫外線のダメージから守る力が弱くなり、シミやシワができやすくなります。
ただし、脂溶性ビタミンであるビタミンEは過剰摂取に注意が必要です。
ビタミンEの過剰摂取によって、血液が止まりにくくなることや骨粗しょう症リスクを高めることが言われているので注意しましょう。
ビタミンEは、アーモンドなどのナッツ類、ひまわり油・ベニバナ油・小麦胚芽油などの植物油、アボカド・キウイなどの果実類、子持ちがれい・はまち・ぎんだら・さばなどの魚介類、とうがらし・かぼちゃ・玉ねぎ・えだまめ・なすなどの野菜などの食品に多く含まれています。
赤血球を強くするポイントとして「ビタミンE」の適量摂取があります。
レシチン
赤血球を強くするポイントとして「レシチン」があります。
レシチンは、リン脂質の一種であり、細胞膜の主成分となります。
赤血球の膜は、リン脂質という油の成分で出来ています。
レシチンなどのリン脂質を摂取することによって、とくに神経細胞の細胞膜の材料となりますが、個人的には赤血球などの他の細胞の細胞膜を安定化する働きもあると考えております。
レシチンなどのリン脂質が不足すると、細胞膜の正常な働きを保つことができなくなります。とくに神経細胞において著明であり、脳や神経の疾患につながるおそれがあります。
また、レシチンは血液中のコレステロールを調整する働きがありますが、レシチンが不足すると、血管にコレステロールがたまるなど、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病につながります。
レシチンは、大豆、たまご、レバー、肉類などに多く含まれています。
赤血球を強くするポイントとして「レシチン」があります。
銅
赤血球を強くするポイントとして「銅」の不足に注意することがあります。
銅は、体内で生成できない必須微量ミネラルであり、さまざまな体の代謝や生体内の反応に関与している栄養素です。
銅は、赤血球の中にあるヘモグロビンに鉄を輸送する働きをしていますので、銅が不足すると「鉄欠乏性貧血」の原因ともなります。
他にも、銅が不足すると、「白血球数の減少」「易感染性」「骨の異常」「神経の異常」「毛髪の異常」などにつながります。
ただし、銅を大量に摂取すると、赤血球が壊れる「溶血」がおこったり「腎臓障害」など起こる可能性があり注意が必要です。
銅は、牡蠣、こむぎ、パプリカ粉、からすみ、スモークレバー、さば節、かたくちいわし、ココアなどの食品に多く含まれています。
赤血球を強くするポイントとして「銅」の不足に注意することがあります。
ビタミンK
赤血球を強くするポイントとして「ビタミンK」があります。
ビタミンKは、脂溶性ビタミンの一つであり、血液を固める作用や骨をつくるのに重要な役割をします。
血液を固めるときに「プロトロンビン」などの血液凝固因子が必要です。
その「プロトロンビン」が肝臓でつくられるときに、「ビタミンK」が補酵素として働きます。ビタミンKが不足すると、出血しやすい状態となり、鉄欠乏性貧血につながる可能性があります。
なお、「ビタミンK」は丈夫な骨づくりにも不可欠であり、骨に存在する「オステオカルシン」というたんぱく質を活性化し、カルシウムを骨に沈着させて骨の形成を促す作用があります。
なお、天然に存在するビタミンK1K2は過剰摂取による影響はないとされています。
しかし、合成されたビタミンK3を過剰摂取すると、溶血性貧血が起こる可能性があり注意が必要です。
ビタミンKは、納豆、わかめ、パセリ、しそ、ほうれん草、ブロッコリー、モロヘイヤ、小松菜、海苔、鶏もも肉・鶏胸肉などの食品に多く含まれています。
赤血球を強くするポイントとして「ビタミンK」があります。
良質なタンパク質
赤血球を強くするポイントとして「良質なタンパク質」があります。
赤血球の細胞膜は、タンパク質などで作られています。
さらに、赤血球の中にあるヘモグロビンは、「ヘモ」(鉄分)と「グロビン」(タンパク質)から構成されています。
つまり、タンパク質を材料にして、赤血球の膜構造や、ヘモグロビンなどが作られるのです。
良質なタンパク質を摂取することによって、赤血球の材料が増えて、赤血球の数を増やすことができます。
また、個人的な意見ですが、赤血球の膜は丈夫なものになり、溶血に強くなるでしょう。
赤血球を強くするポイントとして「良質なタンパク質」があります。
良質な脂質
赤血球を強くするポイントとして「良質な脂質」があります。
細胞膜は、タンパク質だけでなく、脂質などで作られています。
とくに、リン脂質という種類の脂質が赤血球の膜を構成しています。
個人的な意見ですが、赤血球の膜は丈夫なものになり、溶血に強くなるでしょう。
また、脂質を摂取することによって脂溶性ビタミンEが効率的に消化・吸収されます。
ビタミンEは、脂溶性ビタミンの一つであり、強い抗酸化作用をもち、体内の脂質の酸化を防いだり、細胞膜を安定化する働きがあります。
赤血球を強くするポイントとして「良質な脂質」があります。
まとめ
今回は「溶血性貧血」について説明しました。
この記事によって「溶血性貧血」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者