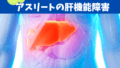マラソンのタイムを伸ばすために日々トレーニングを行っているランナー向けの記事です。
・いつものペースがキツイ!
・すぐに息が切れてしまう。。
・最近、疲れやすいです…
このようなランナーの不調、じつは「貧血」が原因かもしれません。
私はドクターランナーの立場として、長年アスリートの不調に携わってきました。
ランナーが調子が悪いときに、血液検査をするとじつは貧血だと判明するケースは少なくないです。

その不調、貧血が原因かもしれません!
早めに血液検査を受けるようにしましょう。
この記事を読むことによって、ランナーを苦しめる「貧血」について理解することができ、その治療法やご自身でできる対処法について知ることができます。
反対に「貧血」に関する知識がないと、慢性的な体調不良によってトレーニングの調子が上がらず、せっかくトレーニングをしても、伸びないどころか、タイムが悪くなっていくおそれもあります。
さあ、「ランナーの貧血」について一緒にみていきましょう。
貧血とは
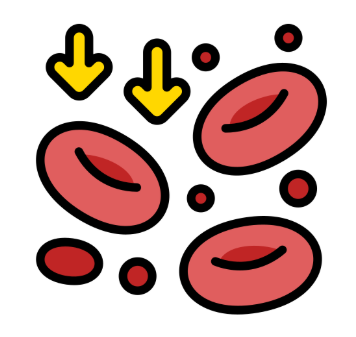
貧血とは、血液中のヘモグロビン濃度が低下した状態のことをいいます。
赤血球の中に含まれる「ヘモグロビン」という物質と酸素が結合することによって、全身に酸素が効率的に運ばれています。
そのヘモグロビン濃度が低下した状態のことを貧血といいます。
貧血の状態だと、全身に必要な酸素を十分運ぶことができず、疲労感・倦怠感・めまいなど様々な症状を引き起こします。
とくに、有酸素運動であるマラソン競技のパフォーマンスに対して重大な影響を与えます。
貧血の影響
一般的な症状

貧血の状態では、全身に必要な酸素が不足することから以下のような症状が起こります。
・動悸
・息切れ
・疲れやすい
・立ちくらみ
・めまい
・頭痛
ランナーの症状

貧血によって、運動に必要な酸素が不十分になると競技パフォーマンスが低下します。
・いつものペースがツライ
・序盤は問題ないが、勝負どころでキツイ
・最後まで粘り切れない
・ペースアップするのがツライ
・とにかく伸び悩んでいる
貧血の状態では、有酸素運動であるマラソンの競技パフォーマンスは確実に低下します。
運動強度が低下するため、毎日のトレーニングの質も思うように上がってこないです。
「トレーニング効果を十分得ることができず、必死にトレーニングをしてもタイムが伸びない」という、アスリートにとって地獄のような状態に陥ってしまいます。
メンタルの悪化

貧血の状態では、「筋肉」だけでなく「脳」への酸素供給も低下します。
また、鉄欠乏性貧血の場合、神経伝達物質の材料である「鉄」が不足するため、その合成がうまくいかず、以下のようなメンタル症状が起こります。
・気分が落ち込む
・思い悩みやすい
・イライラしやすい
・途中で起きてしまう
・寝起きが悪い
ただでさえ、貧血によって思うように走れない状態なので、メンタルは悪化しがちです。
貧血の原因
鉄分の不足
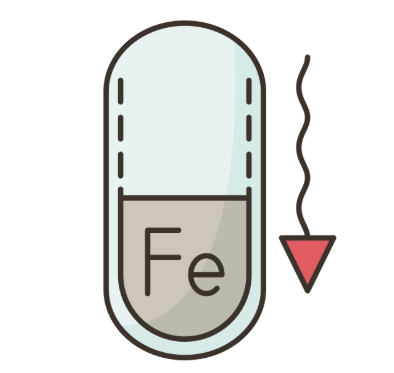
ランナーの貧血の原因として「鉄分の不足」(鉄需要の増加)があります。
「筋肉量の増加」や「成長期」で鉄の必要量が増えたり、食事から摂取する鉄分が不足すると「鉄欠乏性貧血」につながります。
鉄分は、赤血球のヘモグロビンだけでなく、筋肉中のミオグロビンなどに必要な成分です。
アスリートでは、筋肉の量が増えると、多くの鉄分が必要になり、鉄分不足になりやすいです。
なお、成長期にも鉄分の必要量は増加します。
また、ランナーが体重を落とそうとダイエットする場合には、食事から摂取する鉄分が不足しがちなので注意が必要です。
「筋肉量の増加」や「成長期」で鉄の必要量が増えたり、食事から摂取する鉄分が不足すると「鉄欠乏性貧血」につながります。

鉄分の喪失

スポーツ貧血の原因として「鉄分の喪失」があります。
汗や出血などによって鉄分が喪失すると「鉄欠乏性貧血」につながります。
・大量の汗(汗には鉄分が微量ながら含まれる)
・月経(女性の場合)
・消化管出血(ストレスなど)
激しいトレーニングなどをすると、大量の汗をかきます。
汗には、塩分だけでなく「鉄分」なども微量ながら含まれており、汗から失われます。
とくに夏場や長時間のトレーニングで鉄不足になりやすいです。
また、女性の場合は、毎月の月経による出血によって、鉄分が喪失してしまいます。
さらに、激しいトレーニングで、消化管にストレスがかかると消化管出血が起こり、鉄分が喪失する場合もあります。
汗や出血などによって鉄分が喪失すると「鉄欠乏性貧血」につながります。

足裏への衝撃

スポーツ貧血の原因として「足裏への衝撃」があります。
足裏への衝撃によって、赤血球は破壊され「溶血性貧血」につながります。
足裏への衝撃によって、血液中の赤血球が破壊されて、「溶血性貧血」につながります。
長時間走る動作を行うマラソンだけでなく、剣道・バレーボールなど足裏への強い衝撃がかかるスポーツで起こりやすいです。
また、激しいトレーニングによって、体液のpHが下がり、酸性に傾くと、赤血球が壊れやすくなります。
そこに足裏への衝撃などが加わると、赤血球は破壊されてしまい「溶血性貧血」につながります。
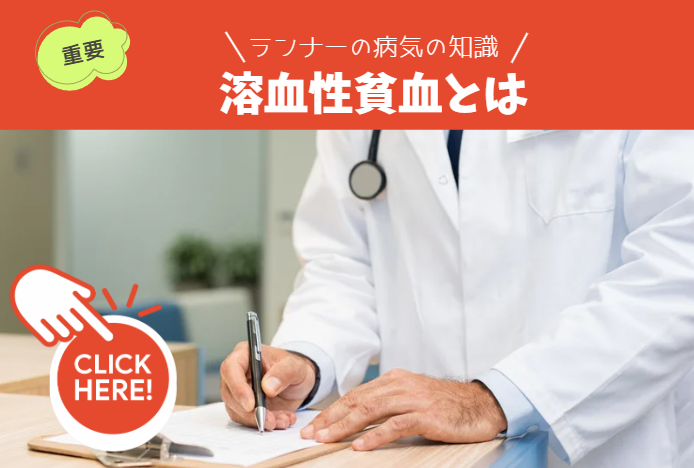
貧血治療の食事のポイント
鉄分を摂取する

貧血の治療として「鉄分を摂取すること」があります。
貧血には「鉄分」というイメージ通り、鉄欠乏性貧血に対して、鉄分を十分に摂取することが大切です。
鉄分を摂取する時には、
・吸収の良い「ヘム鉄」を積極的に摂取する
・ビタミンCと一緒に摂取する
・ビタミンB12・葉酸も摂取する
・タンニン・リン・不溶性食物繊維は避ける
などを意識しましょう。
タンパク質を適量摂取する

貧血の治療として「タンパク質を適量摂取すること」があります。
赤血球中の「ヘモグロビン」は、おもに「ヘム」(鉄を含む色素)」と「グロビン」(タンパク質)によって出来ています。
つまり、ヘモグロビンの材料となる「鉄分」だけでなく「タンパク質」も必要になります。
・赤血球中の「ヘモグロビン」
・鉄分を輸送するための「トランスフェリン」
・鉄分を貯蔵するための「フェリチン」
・遊離したヘモグロビンを運ぶ「ハプトグロビン」
いずれも「タンパク質」から出来ています。
「タンパク質」をしっかりと摂取することが貧血を改善する上で大切になります。
良質なタンパク質を、適度な量、摂取するようにしましょう。
相対的エネルギー不足を防ぐ

貧血の治療として「相対的エネルギー不足を防ぐこと」があります。
相対的エネルギー不足を防ぐために、「糖質」や「脂質」などを十分摂取するとともに、「タンパク質」を適量摂取するようにしましょう。
食事から摂取するカロリーが少ないと、エネルギー不足から体内の筋肉などのタンパク質がエネルギー源として使われてしまいます。
利用できるタンパク質が不足することから「貧血」につながってしまいます。
「運動による消費エネルギー」より「食事から生成されるエネルギー」が少ない状態が慢性的に続いて体調不良に陥ることを「相対的エネルギー不足」と呼ばれます。
相対的エネルギー不足を防ぐために、運動量に見合ったカロリーを摂取することが大事です。
とくに「糖質」や「脂質」などを十分摂取するとともに、タンパク質を適量摂取するようにしましょう。
なお、トレーニング量をおさえて、消費エネルギーを少なくすることも同時に大切になります。
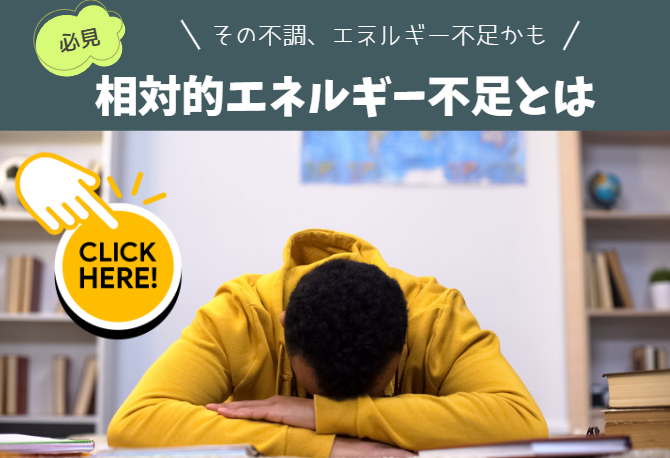
溶血を防ぐための食事
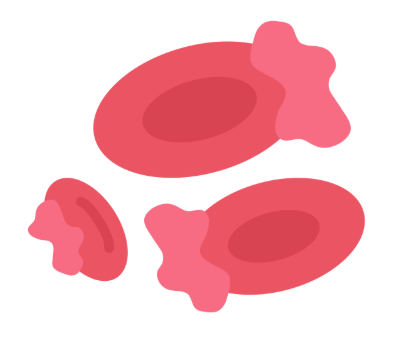
貧血の治療として「溶血を防ぐための食事」があります。
これは、一般的ではなく、やや私見も入るので参考までに。
食事の内容によって溶血しやすい状況があるのでないかと考えております。
- 良質なタンパク質
- 良質な脂質
- サポニンの過剰摂取に注意する
- 亜鉛不足、銅不足に注意する
- ビタミンE、ビタミンKの適量摂取
- レシチンの摂取
これらを意識することによって、溶血を少しでも抑えることができるのでないかと考えます。
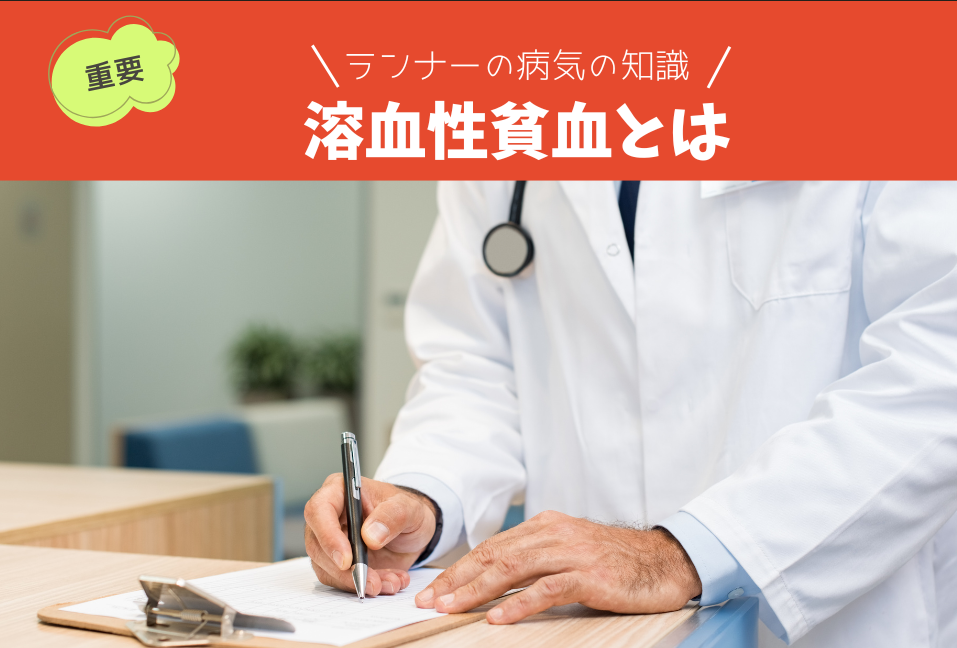
貧血治療のトレーニングのポイント
トレーニング計画を見直す
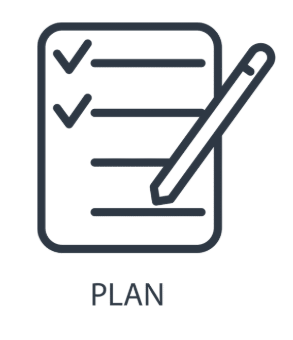
貧血の治療として「トレーニング計画を見直すこと」があります。
相対的エネルギー不足を防ぐために、食事だけでなく、運動による消費カロリーをおさえることも大事です。
・トレーニングの量をおさえる
・トレーニングの質は上げる
・短時間集中のトレーニングを意識する
などで、体力レベルを落とさず、全体的にトレーニングボリュームを抑えるように工夫しましょう。
それでも改善しないようであれば、トレーニングを一時中断する勇気も必要かもしれません。
足裏への衝撃をおさえる

貧血の治療として「足裏への衝撃をおさえること」があります。
足裏への衝撃から、溶血性貧血になるのを防ぐために、以下のような工夫をしましょう。
・不整地を走る
・ランニング以外のトレーニング
・足裏への衝撃を避ける
・踏み込み動作を控える
汗をおさえる

貧血の治療として「汗をおさえること」があります。
汗から「鉄分」が失われないように以下のような工夫をしましょう。
・涼しい環境で運動する
・涼しい時間帯、場所を選ぶ
・涼しい格好でトレーニングする
貧血治療のその他の注意点
溶血をきたす可能性のある医薬品があるので、以下に注意が必要です。
- 高血圧の治療薬である「メチルドパ」
- 不整脈の治療薬である「キニジン」
- 血栓症予防薬である「チクロピジン」「クロピトグレル」
- マラリアの薬である「キニーネ」
まとめ
今回は「ランナーの貧血」について説明しました。
伸び悩み、何か不調を感じるときには、「貧血」が隠れていることが少なくありません。
勇気をもって医療機関で血液検査を受けてみることをオススメします。
しっかりと貧血を治療することによって、今までの不調が嘘のようで、楽に走ることができるようになります。
症状が改善することによって、今までが調子悪かったことが分かるかもしれません。
この記事によって「ランナーの貧血」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者