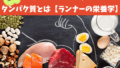・もっと速く走りたいです!
・速く走る体づくりにはタンパク質やアミノ酸が良いって聞きました。
・アミノ酸にはどのような種類がありますか?
この記事を読むことによって、食事を武器にして、マラソンのタイムを伸ばすヒントが見つかります。
私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく食事・栄養バランスなどを記録して研究してきました。
自分自身を実験台にした結果、食事の内容が「走りの調子」と強く関係することを改めて実感しました。
とくに、タンパク質・アミノ酸の摂取量や質によって、コンディションに明らかな違いが表れます。

体づくりの材料である「タンパク質・アミノ酸」を
適切に摂取することで速く走ることにつながります。
タンパク質を武器にできると、きっと自己ベスト更新につながるでしょう。

では、アミノ酸ってどのような種類がありますか?
ということで、今回は「アミノ酸の種類」について説明していきます。
必須アミノ酸(EAA)
アミノ酸には、体内で合成できない「9種類の必須アミノ酸」と体内で合成できる「11種類の非必須アミノ酸」があります。
体内で合成できない必須アミノ酸のことを「EAA」(Essential Amino Acids)と呼ばれます。
具体的にいうと、「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」、「メチオニン」「フェニルアラニン」「スレオニン」「トリプトファン」「リジン」「ヒスチジン」の9種類のアミノ酸です。
必須アミノ酸は体内で合成することができないため、食事などから摂取する必要があります。
BCAA
BCAAとは、運動時に筋肉のエネルギー源となる必須アミノ酸である「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」のことをいいます。
BCAAは「Branched Chain Amino Acid」の略であり、分岐鎖アミノ酸とよばれます。
アミノ酸には、体内では合成できない9種類の「必須アミノ酸」と、それ以外の11種類の「非必須アミノ酸」があります。
必須アミノ酸のうち、BCAAは「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」の3種類をいいます。
BCAAは筋肉中のタンパク質に多く含まれていることから、筋肉にとって重要なアミノ酸であり、アスリート・スポーツ選手や日頃から運動している方は積極的に摂取したい栄養素です。
BCAAの効果には、筋肉の材料となる、運動パフォーマンスの向上、筋疲労の軽減などがあります。
BCAAを多く含む食品として「魚類」「肉類」「卵」「乳製品」「大豆」などがあります。
トリプトファン
トリプトファンとは、必須アミノ酸の一種であり、ヒトの体の健康維持に欠かせない栄養素です。
トリプトファンの効果として、メンタルの安定、幸福感、睡眠の質の改善などの効果があります。
トリプトファンはアミノ酸の一種であり、さまざまなホルモンを合成する材料となります。
とくに、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の材料となるため、メンタルの安定・幸福感につながり、不快感や興奮状態を抑える働きをします。
なお、「セロトニン」は夜になると「メラトニン」という睡眠ホルモンに変化します。
スムーズに入眠することや睡眠の質の向上につながります。
セロトニンが不足すると、夜に眠れない「入眠障害」、途中で起きてしまう「中途覚醒」、睡眠の質が低下し熟睡感が得られないなどの症状につながります。
トリプトファンを含む食品として、肉、魚、大豆・大豆製品、卵、牛乳・乳製品、バナナなどがあります。
リジン
リジンとは、必須アミノ酸の一種であり、米・小麦などの主食に足りないアミノ酸であり、不足しがちなアミノ酸です。
米や小麦などの主食には、タンパク質が含まれていますが、いずれも「リジン」というアミノ酸が少ないため「アミノ酸スコア」は低くなっています。
アミノ酸は一種類でも欠けてしまうと、目的のタンパク質は合成されないため、体の不調などを来してしまう恐れが出てきます。
リジンの効果として、糖代謝の促進、脂質代謝の促進、ヘルペスウイルスの再活性化抑制、体の組織の修復を促す、健康的な髪を育てる、カルシウムの吸収促進、肝機能の改善などの効果があります。
リジンを含む食品として、肉、魚、大豆・大豆製品、卵、牛乳・乳製品などがあります。
準必須アミノ酸
体内を構成するアミノ酸は、9種類の必須アミノ酸(バリン・ロイシン・イソロイシン・メチオニン・リジン・フェニルアラニン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン)と11種類の非必須アミノ酸(チロシン・グルタミン・グリシン・アラニン・セリン・システイン・アスパラギン・プロリン・グルタミン酸・アスパラギン酸・アルギニン)から成り立っています。
必須アミノ酸は、体内では合成することができないため、食事から摂取する必要があります。
一方、非必須アミノ酸は、体内で合成することができるアミノ酸になります。
しかし、実際には必須アミノ酸から合成されるアミノ酸や、不足しがちなアミノ酸もあるため食事から摂取することが望ましいものがあります。
グルタミン
グルタミンは、体内でも合成が可能なため非必須アミノ酸に分類されるアミノ酸であり、体内に最も多く含まれるアミノ酸です。
グルタミンは、体内に最も含まれるアミノ酸であり、とくに筋肉に含まれる遊離アミノ酸の中で最も多く含まれており「約40%」含まれております。
グルタミンは、通常の食事をしていれば不足することはありませんが、激しい運動やケガや風邪など体にストレスがかかると大量に消耗して不足しやすくなるため「準必須アミノ酸」になっています。
グルタミンの効果として、筋肉の材料・免疫機能の向上・胃腸の調子を整える・疲労回復・アルコール代謝のサポート・肝機能のサポートなどがあります。
アルギニンを含む食品として、レバー・豚肉、大豆、魚、卵、小麦粉、チーズ、乳製品、海藻、サトウキビ、トマト、ほうれん草などがあります。
アルギニン
アルギニンは、体内でも合成が可能なため非必須アミノ酸に分類されますが、体にとって不足しやすいことから、準必須アミノ酸(条件付きアミノ酸とも)になっています。
とくに成長期にある小児などでは必須アミノ酸に分類されるくらい必要なアミノ酸になり、「条件付きのアミノ酸」などと言われます。
アルギニンの効果として、成長ホルモン分泌・新陳代謝の促進・筋肉の増強・アンモニアの解毒・肌の保湿などがあります。
アルギニンを含む食品として、大豆、大豆製品、落花生、鶏肉、エビ、マグロ、ごま、煮干し、ゼラチンなどがあります。
システイン
システインは、体内でも合成が可能なため非必須アミノ酸に分類されるアミノ酸ですが、不足しやすいアミノ酸であるため準必須アミノ酸になっております。
システインは硫黄を含んでいる「含硫アミノ酸」であり、肝臓の解毒作用、皮膚の代謝に関係しています。
システインは、グルタチオン(グルタミン酸+システイン+グリシン)という物質の構成成分です。グルタチオンには、抗酸化作用や肝臓の解毒作用があり、システインを摂取することで、その作用が期待できます。
なお、システインが2コ結合したものを「シスチン」といいます。
シスチンには、抗酸化作用や皮膚の紫外線防御作用、メラニンをつくる酵素チロシナーゼのはたらきを抑える作用などがあり、皮膚のシミを抑える効果や皮膚のコンディションを整える働きが期待できます。
システインを含む食品として、肉類、魚類、鶏卵、にんにく、たまねぎ、ブロッコリー、芽キャベツなどがあります。
チロシン
チロシンは、体内でも合成が可能なため非必須アミノ酸に分類されるアミノ酸ですが、必須アミノ酸であるフェニルアラニンから合成されるアミノ酸です。
チロシンは、甲状腺ホルモン、神経伝達物質、皮膚のメラニンなどの合成材料となり、気分の安定、集中力の向上などの効果があります。
チロシンを含む食品として、納豆 、 豆腐、チーズ 、 バナナ、ナッツ類などがあります。
その他のアミノ酸
シトルリン
シトルリンは、体内のタンパク質を合成しませんが遊離アミノ酸として存在しており、体内で様々な効果を発揮します。
シトルリンの効果として、成長ホルモンの分泌促進、新陳代謝の促進、血流促進作用、アンモニアの解毒作用のサポートなどがあります。
摂取したシトルリンは、アルギニンに変換しますが、アルギニンよりも吸収効率が良く、摂取効率も高いです。
アルギニンは、脳の下垂体を刺激し、成長ホルモンの分泌を促し、新陳代謝の促進などの作用があります。また、一酸化窒素(NO)の生成を促進し、血管を拡張し、血流を促進する作用があります。
シトルリンを含む食品として、スイカ、メロン、きゅうり、ニガウリ、ヘチマなどウリ科の植物があります。
グリシン
グリシンは非必須アミノ酸であり、体内で合成することが可能です。
しかし、意識して摂取することによって、グリシンによる様々な効果を得られることができます。
グリシンの効果として、睡眠の質の向上、抗酸化作用、筋運動のエネルギーサポート、ポルフィリン・プリン体の材料になるなどがあります。
グリシンを含む食品として、ホタテやエビ、カニなどの魚介類や、牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類、食品の着香・着色剤などが挙げられます。
クレアチン
クレアチンは、グリシン、アルギニン、メチオニンの3種のアミノ酸より構成される物質であり、筋肉中でエネルギー産生をサポートする働きをします。
クレアチンは、非必須アミノ酸の「グリシン」「アルギニン」、必須アミノ酸の「メチオニン」から構成されるアミノ酸の一種です。
クレアチンは、生体内において「クレアチンリン酸」に変換されて、エネルギー源として貯蔵されます。
クレアチンリン酸は、筋肉が収縮する際にエネルギーとなる「ATP」(アデノシン三リン酸)を再利用するために使用されます。
なお、クレアチンの代謝産物である「クレアチニン」は、腎臓の機能を評価する物質として有名です。
クレアチンとクレアチニンは、名前が似ていますが違う物質であるため注意が必要です。
クレアチンは、運動パフォーマンス向上、疲労回復の促進、筋肉量の増加、ケガの予防、脳機能の向上などの効果があります。
クレアチンは、アミノ酸の一種であるため、基本的にはタンパク質が豊富な食品に多く含まれます。
とくにクレアチンが豊富に含まれている食品として動物性タンパク質があり、肉類(豚肉・牛肉)や魚類(ニシン・サケ・アジ)などに多く含まれます。
糖原性アミノ酸
糖原性アミノ酸とは
糖原性アミノ酸とは、体内でエネルギー源となる糖を生成するアミノ酸です。
タンパク質は、三大栄養素の一つです。
体の材料になる働き、酵素などの材料になる働きなどが有名ですが、それ以外にも、エネルギー源としても使われます。
タンパク質はアミノ酸がつながって出来た物質です。
そもそも、アミノ酸は「アミノ基」と「カルボキシル基」をもつ化合物のことをいいます。
アミノ酸がエネルギー源として利用されるときには、アミノ酸の構造から「アミノ基」が外れて炭素骨格に変換されます。
糖原性アミノ酸は、糖新生経路から「血糖」に変換されて、エネルギー源として利用されます。
なお、外れた「アミノ基」は、アンモニアになるが、オルニチン回路(尿素回路)において、無害な尿素に変換されて、尿中に排出されます。
糖原性アミノ酸とは、体内でエネルギー源となる糖を生成するアミノ酸です。
糖原性アミノ酸の例
糖原性アミノ酸には、アラニン、グリシン、プロリン、セリン、メチオニン、システイン、グルタミン酸、アスパラギン酸、トレオニン、 バリンなどのアミノ酸があります。
人の体内で利用される「アミノ酸」は20種類あります。
そのうち、エネルギー源として利用されるときに、糖代謝が利用される(オキサロ酢酸やピルビン酸が生じるもの)アミノ酸を「糖原性アミノ酸」、ケトン代謝が利用される(アセト酢酸やアセチルCoAが生じるもの)アミノ酸を「ケト原性アミノ酸」といいます。
糖原性アミノ酸には、アラニン、グリシン、プロリン、セリン、メチオニン、システイン、グルタミン酸、アスパラギン酸、トレオニン、 バリン。
他にも、スレオニン、アスパラギン、アルギニン、グルタミン、ヒスチジンなどがあります。
糖原性アミノ酸であり、ケト原性アミノ酸でもあるアミノ酸として、チロシン、イソロイシン、トリプトファン、フェニルアラニンなどがあります。
ロイシンとリシンが、純粋なケト原性アミノ酸になります。
アミノ酸の代謝経路
糖原性アミノ酸が、エネルギー源として利用される代謝経路として以下のようなものがあります。
①「ピルビン酸」から「オキサロ酢酸」になり糖新生に入るもの
→アラニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイン、トリプトファン
②「プロピオン酸等」から「スクシニルCoA」(コハク酸の誘導体)になりクエン酸回路の「オキサロ酢酸」から糖新生に入るもの
→イソロイシン、メチオニン、バリン
③「オキサロ酢酸」になり糖新生に入るもの
→アスパラギン酸、アスパラギン
④「αケトグルタル酸」になりクエン酸回路の「オキサロ酢酸」から糖新生に入るもの
→グルタミン、アルギニン、グルタミン酸、ヒスチジン、プロリン
⑤「フマル酸」になりクエン酸回路の「オキサロ酢酸」から糖新生に入るもの
→チロシン、フェニルアラニン
ケト原性アミノ酸
ケト原性アミノ酸とは
ケト原性アミノ酸とは、体内でエネルギー源として使われるときに脂質代謝経路からケトン体を生成するアミノ酸です。
タンパク質は、三大栄養素の一つです。
体の材料になる働き、酵素などの材料になる働きなどが有名ですが、それ以外にも、エネルギー源としても使われます。
タンパク質はアミノ酸がつながって出来た物質です。
そもそも、アミノ酸は「アミノ基」と「カルボキシル基」をもつ化合物のことをいいます。
アミノ酸がエネルギー源として利用されるときには、アミノ酸の構造から「アミノ基」が外れて炭素骨格に変換されます。
ケト原性アミノ酸は、炭素骨格が脂質代謝経路に入り「ケトン体」が産生されて、エネルギー源として利用されます。
なお、外れた「アミノ基」は、アンモニアになるが、オルニチン回路(尿素回路)において、無害な尿素に変換されて、尿中に排出されます。
ケト原性アミノ酸とは、体内でエネルギー源として使われるときに脂質代謝経路からケトン体を生成するアミノ酸です。
ケト原性アミノ酸
ケト原性アミノ酸には、フェニルアラニン、チロシン、ロイシン、イソロイシン、トリプトファン、リシンのアミノ酸があります。
人の体内で利用される「アミノ酸」は20種類あります。
そのうち、エネルギー源として利用されるときに、糖代謝が利用される(オキサロ酢酸やピルビン酸が生じるもの)アミノ酸を「糖原性アミノ酸」、ケトン代謝が利用される(アセト酢酸やアセチルCoAが生じるもの)アミノ酸を「ケト原性アミノ酸」といいます。
糖原性アミノ酸には、アラニン、グリシン、プロリン、セリン、メチオニン、システイン、グルタミン酸、アスパラギン酸、トレオニン、 バリン。
他にも、スレオニン、アスパラギン、アルギニン、グルタミン、ヒスチジンなどがあります。
ケト原性アミノ酸には、フェニルアラニン、チロシン、ロイシン、イソロイシン、トリプトファン、リシンのアミノ酸があり、いずれも必須アミノ酸です。
厳密にいうと、ケト原性アミノ酸ではあるが、一部糖原性アミノ酸の要素もあるアミノ酸として、チロシン、イソロイシン、トリプトファン、フェニルアラニンがあります。
ロイシンとリシンが、純粋なケト原性アミノ酸になります。
ケト原性アミノ酸の代謝経路
ケト原性アミノ酸が、エネルギー源として利用される代謝経路として以下のようなものがあります。
①アミノ基が外れて、炭素骨格ができる。(脱アミノ化)
②アセトアセチルCoAを経てアセチルCoAになる
※ロイシン、イソロイシンはアセトアセチルCoAへ
※チロシン、イソロイシン、トリプトファン、フェニルアラニン、リシンはアセチルCoAへ
③クエン酸回路で「アセチルCoA」が「オキサロ酢酸」と縮合して「クエン酸」になる
④クエン酸が順次、Cis-アコニット酸、イソクエン酸、2-オキソグルタル酸になる
⑤2-オキソグルタル酸がスクシニルCoA、コハク酸、フマル酸、リンゴ酸を経てオキサロ酢酸に戻る
まとめ
今回は「アミノ酸の種類」について説明しました。
この記事によって「アミノ酸の種類」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者