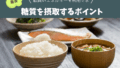糖質って何ですか?
このような疑問にお答えします。
とくに三大栄養素の一つである「糖質」はエネルギー源として必要な栄養素です。
糖質は、エネルギーを作り出すことに特化した栄養素です。
うまく活用することによって、生み出されるエネルギーが多くなり、運動強度を高めることや、トレーニングの質を高めてくれます。
では、糖質って何ですか?
ということで、今回は「糖質」について説明していきます。
糖質とは
糖質は、炭水化物から食物繊維を除いた成分であり、体のエネルギー源となります。
炭水化物は、炭素と水素の化合物であり、「たんぱく質」「脂質」と並ぶエネルギー産生栄養素の三大栄養素の一つです。
炭水化物は、体内に取り入れられエネルギー源となる「糖質」と、体内の消化酵素では消化できない「食物繊維」があります。
つまり、糖質は、炭水化物から食物繊維を除いた成分であり、体のエネルギー源となります。
糖質は「1g当たり約4kcal」のエネルギーがあります。
糖質は、エネルギー源としてすぐに利用されやすく、出力が高い運動で優先的に使われます。
マラソン競技においては、速いペース、スピードを出すときに主に糖質が使われます。
短時間の運動であれば、酸素を利用しないでエネルギーを生み出す「無酸素性エネルギー代謝」において、糖質はエネルギー源としておもに使われます。
長時間の運動において、酸素を利用してエネルギーを生み出す「有酸素性エネルギー代謝」においても糖質は使われます。
なお、その場で使われない糖質は、グリコーゲンとして、筋肉や肝臓に蓄えられます。
なお、グリコーゲンとして貯蔵される量は「約1600kcal」程度とされています。
糖質は、炭水化物から食物繊維を除いた成分であり、体のエネルギー源となります。
糖質の種類
糖質の種類として「単糖類」から「二糖類」「少糖類(オリゴ糖)」「多糖類」などがあります。
単糖類
単糖類
・ブドウ糖(グルコース)
・果糖(フルクトース)
・ガラクトース
糖質の種類として「単糖類」があります。
単糖類は、1つの単糖からできている糖質であり、それ以上は細かく分解できないものをいいます。
なお、単糖が何個か結合して「二糖」や「少糖(オリゴ糖)」「多糖」などが形成されます。
単糖類には、ブドウ糖(グルコース)・果糖(フルクトース)・ガラクトースがあります。
ブドウ糖は、ほとんどの食物に含まれており自然界に広く多く存在している糖質です。
果糖は、果物に多く含まれており、花の蜜などにも含まれています。
ガラクトースはブドウ糖と結合して乳糖として存在しています。
糖質の種類として「単糖類」があります。
二糖類
二糖類
・「麦芽糖」(マルトース)=「グルコース」*2
・「ショ糖」(スクロース)=「グルコース」+「フルクトース」
・「乳糖」(ラクトース)=「グルコース」+「ガラクトース」
糖質の種類として「二糖類」があります。
二糖類は、2つの単糖が結合してできた糖質です。
二糖類として、
「グルコース」が2つ結合した「麦芽糖」(マルトース)
「グルコース」と「フルクトース」が結合した「ショ糖」(スクロース)
「グルコース」と「ガラクトース」が結合した「乳糖」(ラクトース)
などがあります。
ちなみに、「マルトース」は、麦芽から作られており、水あめに多く含まれます。
また、「スクロース」は、ショ糖とも言われており、ほぼ砂糖のことです。
乳糖は、母乳や牛乳などに含まれます。乳糖不耐症では、消化ができず、腹痛・下痢などの症状が起こります。
糖質の種類として「二糖類」があります。
少糖類(オリゴ糖)
糖質の種類として「少糖類(オリゴ糖)」があります。
少糖類(オリゴ糖)は、単糖が2つ以上結合している糖類であり、多糖類よりも分子量が少ないものをいいます。
単糖が2~10個ほど結合したものをオリゴ糖とよばれますが、明確な定義がないようです。そして、単糖が2個結合したものを二糖類というため、実際には単糖が3つ以上結合したものを「少糖類(オリゴ糖)」というケースが多いです。
少糖類は、消化がされにくいため、腸の中にとどまります。
腸内細菌のエサとなったり、整腸作用などを発揮して腸内環境を整える働きをします。
糖質の種類として「少糖類(オリゴ糖)」があります。
多糖類
糖質の種類として「多糖類」があります。
多糖類は、単糖がおおむね10個以上結合している糖類のことをいいます。
多糖類は、消化性多糖類と難消化性多糖類に分類されます。
消化性多糖類は、エネルギー源として代表的な「デンプン」や「グリコーゲン」などがあります。
また、難消化性多糖類は、消化がほとんどできない多糖類のことであり、食物繊維と思ってほぼ間違いないです。
ちなみに、こんにゃくの「グルコマンナン」、寒天の「アガロース」、果物に多く含まれる「ペクチン」はそれぞれ食物繊維であり、多糖類に分類されます。
糖質の種類として「多糖類」があります。
果糖の特徴
エネルギー利用されやすい
果糖の特徴として「エネルギー利用されやすい」ということがあります。
果糖の腸からの消化吸収は、糖輸送担体(GLUT5)により濃度勾配によって受動的に輸送されます。一方、ブドウ糖は、糖共輸送担体(GLUT1)により能動的に輸送されるため、果糖の消化スピードは遅いとされます。
しかし、果糖は、腸から吸収された後は門脈を通って肝臓へと運ばれて「フルクトキナーゼ」という酵素の作用によって、「フルクトース-1-リン酸」という物質に変換されます。
「フルクトース-1-リン酸」は、ブドウ糖の解糖系の代謝経路の途中から利用されるため、エネルギー利用がされやすいです。
運動時に素早くエネルギー源が欲しい場合には、果糖は最適なエネルギー源となるといえるでしょう。
ただし、果糖を摂り過ぎてしまうと、余分なエネルギーが中性脂肪の増加、肥満につながるおそれもあります。
果糖の摂り過ぎには注意して適量を心がけましょう。
血糖値が上昇しない
果糖の特徴として「血糖値が上昇しない」ということがあります。
そもそも血糖値とは、「血液中のブドウ糖の濃度(mg/dl)」のことをいいます。
ブドウ糖も果糖も同じ単糖類ですが、違うものです。
血糖値を測定しても果糖の濃度は反映されないため、血糖値は上昇しないです。
繰り返しですが、果糖は、腸から吸収された後は、門脈を通って、肝臓へと運ばれてフルクトキナーゼという酵素の作用によって、「フルクトース-1-リン酸」という物質に変換されます。
基本的には、門脈以外の血液中には果糖は存在しないため、通常の末梢からの血液を測定しても果糖は分かりません。
果糖は、血糖値には反映されないとはいえ、エネルギー源として体には影響を与えております。
果糖の存在を血糖の測定で把握できないだけあるため、血糖値が上がらないからといって、過剰に果糖を摂取しないように注意しましょう。
インスリン分泌と関係ない
果糖の特徴として「インスリン分泌と関係ない」ということがあります。
ブドウ糖は、血液中の濃度が上がると(つまり血糖値が上がると)、膵臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。
インスリンの作用によって、肝臓や筋肉・脂肪細胞などにブドウ糖が取り込まれて、血糖値は下がります。
細胞内に取り込まれたブドウ糖は、解糖系・クエン酸回路などの代謝経路によってATPを産生しエネルギーを生み出します。
しかし、果糖は体内に取り込まれても、血糖値は上昇しないため「インスリン分泌」は起こりません。
繰り返しですが、腸から吸収された後は門脈を通って肝臓へと運ばれて「フルクトキナーゼ」という酵素の作用によって、「フルクトース-1-リン酸」という物質に変換されます。
「フルクトース-1-リン酸」は、解糖系の代謝経路の途中から利用されて、エネルギーが生み出されます。
乳糖の特徴
エネルギーになる
乳糖の特徴として「エネルギーになる」ということがあります。
乳糖は、ブドウ糖とガラクトースが結合してできた二糖類です。
乳糖(ラクトース)が摂取されると、ラクターゼという消化酵素によって、ブドウ糖とガラクトースに分解されて、腸において消化吸収されます。
分解されてできた「ブドウ糖」は体内でエネルギーとして利用されます。
また、「ガラクトース」は、肝臓でブドウ糖に代謝されて、エネルギーとして利用されます。
ちなみにガラクトースの一部は、脳や神経の構成成分として重要な役割をし、赤ちゃんにとって母乳から摂取する乳糖が必要になるのです。
ただし、乳糖はラクターゼの分泌が不十分であり消化されないケースもあるため、メインのエネルギー源としてはあまり期待しない方がいいとされています。
腸内環境の改善
乳糖の特徴として「腸内環境の改善」ということがあります。
繰り返しですが、乳糖(ラクトース)が摂取されると、ラクターゼという消化酵素によって、ブドウ糖とガラクトースに分解されて、腸において消化吸収されます。
ただし、十分に消化吸収されなかった「乳糖」は、腸内細菌のエサとなります。乳酸菌など善玉菌が存在する場合には、増殖し腸内環境が改善します。
反対に善玉菌などの腸内細菌が十分に存在しない場合には、消化不良の乳糖によって乳糖不耐症の症状が起こります。
とくに成人のラクターゼの分泌量は少なくなっております。
ラクターゼの分泌量は、母乳など飲む乳児で最大であり、大人になるにつれて分泌量は減っていきます。大人になって母乳を飲まなくなることが原因と考えられています。
乳糖不耐症に注意
乳糖の特徴として「乳糖不耐症に注意」ということがあります。
繰り返しですが、乳糖(ラクトース)が摂取されると、ラクターゼという消化酵素によって、ブドウ糖とガラクトースに分解されて、腸において消化吸収されます。
ラクターゼが十分分泌されないと、乳糖を消化吸収されず、軟便・下痢・腹痛などの症状が起こります。これを「乳糖不耐症」といいます。
腸内に善玉菌が十分いれば、消化されなかった乳糖を分解してくれて、乳糖不耐症の症状を軽減してくれます。さらに善玉菌は増殖して、腸内環境は改善することになります。
しかし、善玉菌が少なく、悪玉菌が多い場合には、反対に腸内環境は悪化してしまいます。
とくに日本人の成人では、ラクターゼの分泌量は少なくなっている方が多く、「25%程度」と言われております。
全世界では「10%程度」と言われており、日本人ではその頻度が多いため「乳糖」の摂取には注意しましょう。
オリゴ糖の特徴
オリゴ糖とは
オリゴ糖とは、単糖が2個から10個程度結びついた糖質の一種で、少糖類とも呼ばれます。
オリゴ糖とは、単糖が2個から10個程度結びついた糖質の一種で、少糖類とも呼ばれます。明確な定義はありませんが、一般的には3つ以上の糖が結びついたものを「オリゴ糖」と呼ぶことが多いようです。
単糖の種類として「ブドウ糖」(グルコース)、「果糖」(フルクトース)、「ガラクトース」などがあり、それらが結びついてオリゴ糖が形成されます。
なお、「ガラクトース」という単糖は、牛乳や乳製品、一部の野菜・くだものなどに含まれています。
オリゴ糖とは、単糖が2個から10個程度結びついた糖質の一種で、少糖類とも呼ばれます。
オリゴ糖の特徴
オリゴ糖の特徴として、腸内細菌のエサとなる、腸の蠕動運動を活発化する、ミネラルの吸収を促す、血糖値への影響が少ないなどがあります。
オリゴ糖は、腸内細菌のエサとなります。腸内にある乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を増やしてくれます。
また、善玉菌であるビフィズス菌が作り出す有機酸によって腸内が弱酸性になり、腸のぜん動運動が活発になるので、便秘や便臭の改善につながり、腸内環境が良好になります。
また、オリゴ糖によって、カルシウムなどのミネラルが溶けやすくなり、ミネラルが体内へ吸収されやすくなります。
さらに、オリゴ糖は、砂糖などの他の糖と比べて血糖値への影響が少ないため、糖尿病や血糖値管理が必要な人々にとって最適です。
オリゴ糖を含む食品
オリゴ糖を含む食品として、大豆、納豆、豆腐、味噌などの大豆製品、玉ねぎ、ねぎ、ごぼう、アスパラガスなど野菜、バナナ、リンゴ、キウイフルーツなど果物、牛乳、ヨーグルト、チーズなど乳製品などがあります。
糖質がランナーにとって必要な理由
エネルギー源となる
糖質がランナーにとって重要な理由として「エネルギー源となること」があります。
糖質は、体を動かすためのメインのエネルギー源です。
とくに、瞬発系・パワー系・短時間の運動などのエネルギー源となります。
また、持久系の競技において、糖質だけでなく脂質もエネルギーとして使用されますが、出力が大きな運動を持続するためには「糖質」が大切になります。
よく例えられますが、車で例えると糖質は「ガソリン」に当たります。
ガソリンである糖質が不足すると、エネルギー不足によって、思うように動けなくなってしまいます。
糖質がランナーにとって重要な理由として「エネルギー源となること」があります。
タンパク質の分解を抑える
糖質がランナーにとって重要な理由として「タンパク質の分解を抑えること」があります。
繰り返しですが、糖質は、体を動かすためのメインのエネルギー源です。
エネルギー源である糖質が不足すると、糖質の代わりに「タンパク質」がエネルギーとして利用されるようになります。
すると、体内の筋肉などのタンパク質が分解されることにつながります。
糖質が不足してしまうと、トレーニングによって付いた筋肉が分解されてしまうおそれがあるのです。
糖質を十分に摂取することによって、トレーニングによって鍛えられた筋肉を守ることが出来るのです。
糖質がランナーにとって重要な理由として「タンパク質の分解を抑えること」があります。
細胞内への取り込みを促す
糖質がランナーにとって重要な理由として「細胞内への取り込みを促すこと」があります。
糖質(ブドウ糖を含む)を摂取すると、血糖値が上がります。
血糖値が上がると、血糖値を下げる作用のある「インスリン」というホルモンが分泌されます。
インスリンが分泌されると、血液中のブドウ糖は細胞内に取り込まれて、血糖値を下げてくれます。
このときに、「ブドウ糖」と一緒に「アミノ酸」などの物質も一緒に細胞内に取り込まれるため、細胞レベルでエネルギーが補給されて、細胞の修復に必要な物質も取り入れられるためリカバリーが促されます。
糖質がランナーにとって重要な理由として「細胞内への取り込みを促すこと」があります。
トレーニングの質が上がる
糖質がランナーにとって重要な理由として「トレーニングの質が上がること」があります。
糖質は、体を動かすためのメインのエネルギー源です。
エネルギー源をしっかりと摂取することによって、ランニングなどではより速いペースで、より長い距離を走ることができます。
産生させるエネルギーが多いほど、トレーニングにおける出力は上がり、トレーニングの質が上がります。
反対に、糖質などのエネルギー源が不足すると、思うように動けなくなってしまいます。
思うような負荷をかけることができず、トレーニングの質は下がってしまいます。いくらトレーニングを行っても、思うような成果に結びつかないのです。
糖質がランナーにとって重要な理由として「トレーニングの質が上がること」があります。
脂肪燃焼を促す
糖質がランナーにとって重要な理由として「脂肪燃焼を促すこと」があります。
マラソンなどの長い時間を運動するにあたって、糖質だけでなく脂質もエネルギー源として重要になります。
脂質は貯蔵量がたくさんあるため、多くのエネルギーを作り出すことが出来るのですが、それを利用するためには「糖質」の存在が必要です。
糖質が存在していることによって、脂質代謝が促されるのです。
つまり、糖質によって脂肪燃焼を促してくれます。
ちなみに、脂質は、体の中に体脂肪として存在しており、貯蔵されている糖質に比べると、はるかに多くのエネルギーを生み出してくれます。
ただし、瞬発系の出力が高い運動では糖質がメインに使われます。
脂質をうまく使い、糖質を温存しながら走るという発想もマラソンで記録を狙うために必要になります。
糖質がランナーにとって重要な理由として「脂肪燃焼を促すこと」があります。
利用可能エネルギー不足を防ぐ
糖質がランナーにとって重要な理由として「利用可能エネルギー不足を防ぐこと」があります。
体のエネルギー源として、「糖質」「脂質」「タンパク質」の三大栄養素が重要です。
運動量が多いアスリートの場合、運動量に見合ったエネルギーを食事から摂取できないと「利用可能エネルギー不足」が起こります。
とくに女性アスリートの場合、「無月経」「骨粗しょう症」「スポーツ貧血」などの病気につながるおそれがあります。
エネルギーをしっかりと補給しようとすると、「糖質」「脂質」「タンパク質」を十分に摂取することになります。
そのうち、「脂質」を多く摂り過ぎてしまうと、体脂肪として蓄積してしまいます。
「タンパク質」を多く摂り過ぎてしまうと、余分なタンパク質を処理するために「腎臓」や「肝臓」への負荷がかかります。
また、タンパク質が分解されてエネルギー源として使われやすくなり、タンパク質の摂取が少なくなったときに体の構造に必要なタンパク質の取り分がエネルギーとして消費されてしまい、タンパク質不足に陥るおそれがあります。
それに対して、「糖質」は多く摂り過ぎても、筋肉や肝臓にグリコーゲンとして貯蔵される程度ですが、その貯蔵量は限度があります。
なお、余分な糖質は基本的には、尿に排出されます。
これがひどくなると「糖尿病」になりますが、運動をたくさん行っているアスリートの場合、トレーニングによって、摂取された糖質のほとんどを運動によって消費されることになります。
よほど極端な糖質摂取をしない限り、安全に摂取することができ、体重もそこまで増やさずに、利用可能エネルギー不足を防ぐことができるのです。
糖質がランナーにとって重要な理由として「利用可能エネルギー不足を防ぐこと」があります。
糖質を摂取するポイント
糖質の摂取量
糖質を摂取するポイントとして「糖質の摂取量」があります。
アスリートの糖質摂取量は、1日に必要なエネルギーの60%以上が望ましいとされています。
また、体重1kgあたり6~10gの糖質を摂取することも推奨されています。
ちなみに、体重60kgの場合、必要な糖質量は「360~600g」となり、「1440~2400kcal」に相当します。
白米100gあたり糖質は「約35g程度」含まれるため、「白米1kg~1.7kg」に相当します。
強豪校では、白米を1日2kg以上食べるように指導されるケースもありますが、体格の良い選手であればそのくらいの量になります。
これは、あくまで糖質の摂取量の目安であり、競技内容やトレーニング内容、トレーニング時期、それぞれの身長・体重などの体格によって、糖質を摂取すべき量は異なります。
なお、強度の高い運動後には、枯渇した糖質を補給するために、
1時間以内に体重1kgあたり「約1~1.2g」
4時間以内に体重1kgあたり「約1~1.2g/1時間」程度の糖質を補給すると効果的です。
競技時間が長時間に及ぶ持久系スポーツでは、パフォーマンス維持のために、
競技中に「約60g/1時間」程度の糖質を摂取することがすすめられています。
糖質を摂取するポイントとして「糖質の摂取量」があります。
糖質の種類
糖質を摂取するポイントとして「糖質の種類」があります。
糖質の種類として「単糖類」から「二糖類」「少糖類(オリゴ糖)」「多糖類」などがあります。
これらの順番に結びついている分子の数が多くなっていき、消化までの時間が遅くなっていきます。
つまり、「単糖類」が一番消化が早く、「多糖類」が消化に時間がかかります。
なお、単糖類の中でも「果糖」は、すぐにエネルギーとして利用されやすく、インスリン分泌と関係ないため、反発性の低血糖が起こりにくいため、運動前の糖質摂取でオススメします。
一方、単糖類の「ブドウ糖」は、血液中のブドウ糖濃度が上昇(血糖値が上昇)し、インスリンが分泌されて、細胞内にブドウ糖が取り込まれて利用されるとともに、血糖値は低下します。
糖質を摂取するタイミングが悪いと、トレーニング中に低血糖を起こしてしまう「大福餅症候群」が起こる可能性があるため注意が必要です。
多糖類であるデンプンを含む「ごはん」や「小麦(パン・パスタ・うどんなど)」「いも類」などの主食は、運動する2~3時間くらい前に済ませておきたいです。
また、単糖類であるブドウ糖や果糖、二糖類であるショ糖(砂糖)などが含まれているスポーツドリンクやエナジージェル等では、消化吸収が早いため、運動する前や、運動中に摂取してもいいでしょう。
ただし、糖質を摂り過ぎてしまい血糖値の上昇の後にくる低血糖には十分注意するようにしましょう。
なお、スポーツ用のフーズやドリンクの中には、マルトデキストリンなどのすぐに消化吸収されるものや、パラチノースなどのゆっくりと持続的に消化吸収されるものがあります。
自分の取り組む競技やトレーニング内容によって、使い分けると良いでしょう。
糖質を摂取するポイントとして「糖質の種類」があります。
GI値
糖質を摂取するポイントとして「GI値」があります。
GI値とは「Glycemic Index」の略であり、食事をした後の血糖値の上昇度を表す指標のことです。
食事をすると、糖質(ブドウ糖)が消化吸収されて血糖が上昇しますが、このときの「血糖値が上昇する程度」は食品の種類によってさまざまです。
食事をした後の血糖値の上昇度を表す指標のことを「GI(Glycemic Index)値」といいます。
GI値が高い食品「高GI食品」を食べると、食後の血糖が急激に上昇します。
そして、血糖値を下げる作用のあるインスリンというホルモンが分泌されて、血糖値の急下降が起こる「血糖値スパイク」と呼ばれる現象が起こります。
なお、血糖値スパイクの健康面への影響として「糖質の過剰摂取につながる」「低血糖症状」、「生活習慣病」「認知機能の低下」「免疫力の低下」などのリスクが上がるなどがあります。
血糖値スパイクを抑えるコツとして「糖質を最後に食べること」「よく噛んで食べること」「低GI値の食品」「栄養バランスの良い食事」などがあります。
トレーニングや運動を行う前後など、すぐに糖質が必要な時には、「GI値が高いもの」を、反対にゆっくりと糖質を補給したい場面では「GI値が低いもの」を選びましょう。
一日全体の流れを見た場合、トレーニング前後に糖質を多めに摂取すること、間食などで食事回数を増やすなどの工夫によって、血糖値スパイクをおさえながら糖質を摂取することができます。
糖質を摂取するポイントとして「GI値」があります。
糖質を含む食品
糖質を含む食品として「穀物類」「芋類」「砂糖類」「果物類」「菓子類」などがあります。
穀物類
白米…約33g(100g当たり)
小麦粉…約73g(100g当たり)
うどん(ゆで)…約52g(250g当たり)
そば(ゆで)…約48g(200g当たり)
食パン…約26g(60g当たり)
芋類
さつまいも…約30g(100g当たり)
じゃがいも…約16.3g(100g当たり)
長芋…約13g(100g当たり)
砂糖類
砂糖(ショ糖)…約8.9g(9g当たり)
はちみつ…約16.7g(21g当たり)
水あめ…約17.9g(21g当たり)
果物類
いちご…約5.3g(75g当たり)
バナナ…約21.4g(100g当たり)
りんご…約35g(250g当たり)
菓子類
どら焼き…約55.6g(100g当たり)
カステラ…約31g(50g当たり)
ようかん…約33.5g(50g当たり)
まとめ
今回は「糖質」について説明しました。
この記事によって「糖質」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者