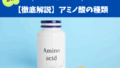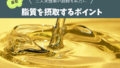・もっと速く走りたいです!
・アスリートは食事が大事と聞きますが、どうすればいいの?
・タンパク質って何ですか?
この記事を読むことによって、食事を武器にして、マラソンのタイムを伸ばすヒントが見つかります。
私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく食事・栄養バランスなどを記録して研究してきました。
自分自身を実験台にした結果、食事の内容が「走りの調子」と強く関係することを改めて実感しました。
とくに、タンパク質の摂取量や質によって、コンディションに明らかな違いが表れます。

体づくりの材料である「タンパク質」は、
速く走るための肉体をつくる上で大切です。
タンパク質を武器にできると、きっと自己ベスト更新につながるでしょう。

では、タンパク質って何ですか?
ということで、今回は「タンパク質」について説明していきます。
タンパク質とは

タンパク質は、アミノ酸が結びついてできた物質であり、主に体の材料となる栄養素です。
体内で利用される「アミノ酸」は全20種類ありますが、その組み合わせによって「タンパク質」が合成されます。
数十個から数百個以上のアミノ酸が集まって、約10万種類と言われている「タンパク質」が形成されます。
「20種類」のアミノ酸のうち、「9種類」は体内では合成できない「必須アミノ酸」(バリン・ロイシン・イソロイシン・スレオニン・メチオニン・リジン・フェニルアラニン・トリプトファン・ヒスチジン)があります。体内で合成されないので、食事などから摂取する必要があります。
それ以外の「11種類」のアミノ酸を「非必須アミノ酸」(グリシン・アラニン・グルタミン酸・グルタミン・セリン・アスパラギン酸・アスパラギン・チロシン・システイン・アルギニン・プロリン)とよばれます。
タンパク質は、「筋肉」「皮膚」「臓器」「毛髪」「骨」など体のあらゆる場所に存在しており、体の組成は水分を除くと「タンパク質」と「脂質」で大部分を占めています。
また、体の機能を調整している「ホルモン」「酵素」「抗体」などの材料にもなっています。
つまり、アミノ酸やそれから合成されるタンパク質は「体をつくる材料」と言えます。
タンパク質の働き
エネルギー源になる

タンパク質の働きとして「エネルギー源になること」があります。
タンパク質は、糖質・脂質と並び、三大栄養素の1つであり、エネルギー源となります。
糖質や脂質によるエネルギー供給が不十分なときに、タンパク質がエネルギー源として使われます。
タンパク質は1gあたり約4kcal程度のエネルギーが発生します。
なお、タンパク質はアミノ酸がつながって出来た物質です。
そもそも、アミノ酸は「アミノ基」と「カルボキシル基」をもつ化合物のことをいいます。
アミノ酸がエネルギー源として利用されるときには、アミノ酸の構造から「アミノ基」が外れて炭素骨格に変換されます。
炭素骨格から「ピルビン酸」や「アセチルCoA」などが産生されて、クエン酸回路(TCA回路)において、エネルギー通貨であるATPが作られます。
なお、外れた「アミノ基」からアンモニアが発生しますが、肝臓内のオルニチン回路(尿素回路)において、無害な尿素に変換されて、尿中に排出されます。
そのため、タンパク質をエネルギー源として使われると、肝臓や腎臓に負荷がかかるため、
タンパク質は、エネルギー源としてなるべく使いたくないところです。
タンパク質の働きとして「エネルギー源になること」があります。
筋肉の材料になる
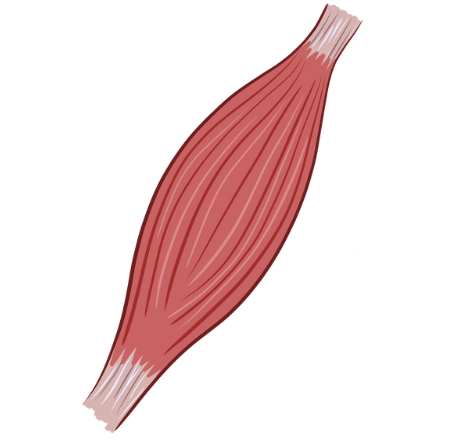
タンパク質の働きとして「筋肉の材料になること」があります。
体内で利用される「アミノ酸」は全20種類ありますが、その組み合わせによって「タンパク質」が合成されます。
数十個から数百個以上のアミノ酸が集まって、約10万種類と言われている「タンパク質」が形成されます。
タンパク質が分解されて、体内に消化吸収されたアミノ酸は、体内の血液・細胞内・細胞間などに「アミノ酸プール」として存在します。
そして、アミノ酸を材料にして「筋肉」が合成されます。
体内のアミノ酸濃度が高まると、筋肉の合成が促進されます。
反対に、アミノ酸濃度が低くなると、筋肉の分解が進みます。
筋肉は絶えず、合成と分解を繰り返しているのです。
「合成>分解」で筋肉肥大が起こります。(アナボリック)
「合成<分解」で筋肉量は少なくなってしまいます。(カタボリック)
ボディビルダー・ボディメイクなど、筋肥大させたい方はカタボリックな状態を避けることが重要です。
反対に、筋肥大による体重増加でパフォーマンスに影響があるようなマラソンランナーなど筋肥大させたくない方では、ある程度のカタボリックを許容しながらトレーニングに励むことになります。
タンパク質の働きとして「筋肉の材料になること」があります。
皮膚や爪などの材料になる
タンパク質の働きとして「皮膚や爪などの材料になること」があります。
繰り返しですが、体内で利用される「アミノ酸」は全20種類ありますが、その組み合わせによって「タンパク質」が合成されます。
数十個から数百個以上のアミノ酸が集まって、約10万種類と言われている「タンパク質」が形成されます。
プラモデルの部品が「アミノ酸」
完成したプラモデルが「タンパク質」
みたいなイメージです。
体内は水分を除くと、そのほとんどが「タンパク質」と「脂質」で出来ています。
タンパク質を材料にして、皮膚・爪・髪など体のあらゆる構造が作られます。
タンパク質の働きとして「皮膚や爪などの材料になること」があります。
タンパク質の働きとして「エネルギー源になる」「筋肉の材料になる」「皮膚や爪の材料になる」「ホルモンや酵素の材料になる」「神経伝達物質の材料になる」「ヘモグロビンの材料になる」などがあります。
ホルモンや酵素の材料になる
タンパク質の働きとして「ホルモンや酵素の材料になること」があります。
ホルモンは、体の様々な働きを調節する物質であり、タンパク質や脂質などを材料にして作られます。
脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵臓、生殖腺などの内分泌腺でホルモンは作られます。
また、酵素は、体の中で様々な化学反応を促進するタンパク質です。
たとえば、
消化、吸収、代謝などの働きを調節する
体内で起こる化学反応を引き起こす
体内の有害物質を処理し尿などと一緒に排泄する
体の成長
免疫反応
体の調節機能
などの反応に関わります。
とくにエネルギーを産生する反応や、体にとって不要なものを排出するような生きていく上で必要な生命活動のことを「代謝」と呼ばれます。
代謝を促すためにも、「酵素」の存在は必要不可欠です。
タンパク質の働きとして「ホルモンや酵素の材料になること」があります。
神経伝達物質の材料になる
タンパク質の働きとして「神経伝達物質の材料になること」があります。
神経伝達物質とは、神経細胞同士が情報を伝達する化学物質です。
神経細胞は直接つながっていないため、シナプスという接点で「神経伝達物質」を使って情報を伝えています。
脳内の精神現象のコントロール、記憶・感情・意識などの活動、筋肉の収縮などさまざまな働きをサポートします。
ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、ヒスタミン、γ-アミノ酪酸(GABA)、グルタミン酸、 グリシンなどがあります。
タンパク質の働きとして「神経伝達物質の材料になること」があります。
ヘモグロビンの材料になる
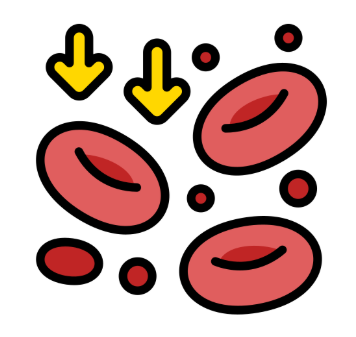
タンパク質の働きとして「ヘモグロビンの材料になること」があります。
ヘモグロビンは、赤血球に含まれるタンパク質であり、酸素と結合し、酸素を運ぶことができます。
ヘモグロビンは、赤血球に含まれるタンパク質です。
「鉄を含むヘムという色素」と「グロビンというタンパク質」によって構成されています。
赤血球の「約1/3」はヘモグロビンによって出来ており、赤血球の赤い色は、ヘモグロビンの色によります。
赤血球が酸素と結びつくためには、このヘモグロビンというタンパク質の存在が不可欠です。
ヘモグロビン値が低下すると「貧血」と診断されます。
鉄欠乏性貧血が有名ですが、ヘモグロビンの材料であるタンパク質が不足しても貧血につながります。
とくに持久系スポーツをしている方がパフォーマンス低下したときに、「貧血」が隠れているケースがあるので注意が必要です。
タンパク質の働きとして「ヘモグロビンの材料になること」があります。
タンパク質不足の症状
筋力が低下する
タンパク質不足のサインとして「筋力が低下すること」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になります。
食事などから摂取されたタンパク質はアミノ酸に分解されて、消化吸収されます。
消化吸収されたアミノ酸は、門脈を通って肝臓に入り、体に必要なタンパク質が作られます。
アミノ酸は、筋肉を合成する材料になります。
タンパク質が不足すると、筋肉の材料が不足してしまうため、筋肉量は低下しますし、筋力も低下してしまいます。
せっかくトレーニングを行っても、十分なタンパク質がなければ、残念ながらトレーニング効果も落ちてしまいます。
タンパク質不足のサインとして「筋力が低下すること」があります。
集中力が低下する
タンパク質不足のサインとして「集中力が低下すること」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になりますが、神経伝達物質の材料にもなります。
神経伝達物質を作る上で必要なタンパク質が不足すると、集中力の低下などにつながります。
なお、神経伝達物質には、
やる気を高める「ドパミン」
精神を安定させる「セロトニン」
などがあります。
これら神経伝達物質が不足すると、脳の働きが低下し、集中力や思考力が低下してしまい、競技パフォーマンスの低下にもつながります。
タンパク質不足のサインとして「集中力が低下すること」があります。
疲れやすくなる

タンパク質不足のサインとして「疲れやすくなること」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になりますが、体の中でさまざまな代謝に関わる酵素や神経伝達物質の材料にもなります。
タンパク質が不足すると、代謝に関わる酵素や神経伝達物質などの物質も不足することになります。
酵素が不足すると、糖質・脂質などからエネルギーをうまく産生されなくなります。
エネルギー不足から疲労感につながります。
また、ドパミンやセロトニンなどの神経伝達物質が不足すると、脳の働きが低下し、やる気が起こらず疲労を感じやすくなってしまいます。
なお、セロトニンは夜になるとメラトニンという睡眠ホルモンに変化します。
セロトニンやメラトニンが不足してしまうと睡眠の質が低下して、リカバリー不足から日中の疲労感につながります。
タンパク質不足のサインとして「疲れやすくなること」があります。
免疫力の低下
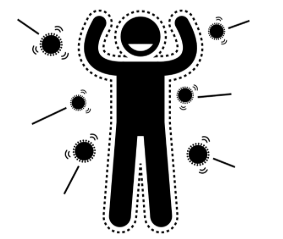
タンパク質不足のサインとして「免疫力の低下」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になります。
食事などから摂取されたタンパク質はアミノ酸に分解されて、消化吸収されます。
消化吸収されたアミノ酸は、門脈を通って肝臓に入り、体に必要なタンパク質が作られます。
アミノ酸やタンパク質は、免疫細胞を合成する材料にもなります。
免疫細胞は、白血球の一種であり、マクロファージ、好中球、NK細胞、樹状細胞、T細胞、B細胞などの種類があります。
これらの免疫細胞は、骨髄の中にある血球を作るもとになっている「造血幹細胞」という細胞から作られます。
さらに、免疫細胞の活性化や免疫力の維持には、さまざまなアミノ酸が重要な働きをします。
タンパク質が不足すると、免疫細胞の数が減り、免疫細胞の活性化もうまくうかず、免疫力は低下してしまいます。
タンパク質不足のサインとして「免疫力の低下」があります。
睡眠の質の低下

タンパク質不足のサインとして「睡眠の質の低下」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になりますが、神経伝達物質の材料にもなります。
とくに、精神を安定させる働きのある「セロトニン」が産生されますが、夜になると「メラトニン」という睡眠ホルモンに変化します。
とくに、トリプトファンというアミノ酸は、セロトニンやメラトニンの材料になるため、睡眠にとって重要な働きをします。
また、グリシンというアミノ酸は、末梢の血流を増加し、熱放散を促すことによって、深部体温を下げる働きをします。
徐波睡眠に達するまでの時間が短縮したり、より深い睡眠が増加したりして、睡眠を安定化させる効果が期待できます。
タンパク質不足のサインとして「睡眠の質の低下」があります。
貧血になる

タンパク質不足のサインとして「貧血になること」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になりますが、赤血球の材料にもなります。
赤血球は酸素を全身に運搬する役割をしますが、赤血球の中のヘモグロビンという色素成分がとくに重要になります。
ヘモグロビンは、おもに鉄分とタンパク質から構成されています。
タンパク質が不足すると、ヘモグロビンが低下してしまい、貧血につながります。
貧血になると、疲労感・倦怠感、動悸・息切れなどの症状が起こります。
スポーツ選手であれば、競技パフォーマンスが低下し、集中力の低下、トレーニング効果が低下してしまうことなどにつながります。
タンパク質不足のサインとして「貧血になること」があります。
肌荒れ
タンパク質不足のサインとして「肌荒れ」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になります。
食事などから摂取されたタンパク質はアミノ酸に分解されて、消化吸収されます。
消化吸収されたアミノ酸は、門脈を通って肝臓に入り、体に必要なタンパク質が作られます。
アミノ酸やタンパク質は、肌の細胞やコラーゲンを構成する重要な栄養素で、肌のハリやツヤを与える効果があります。
タンパク質不足によって、肌の乾燥、肌のハリ不足、肌のターンオーバーの周期の乱れ、 ニキビなどの肌トラブルなどにつながります。
タンパク質不足のサインとして「肌荒れ」があります。
骨が脆くなる
タンパク質不足のサインとして「骨が脆くなること」があります。
タンパク質やアミノ酸は、体の構造を作る材料になります。
そして、「骨」は、カルシウムやタンパク質などを材料として作られます。
タンパク質が不足すると、骨密度が低下してしまい、骨がもろくなり、骨粗鬆症や骨折のリスクが高まります。
さらに、筋肉量が減ってしまい、 体力や免疫力が低下し、運動刺激による骨を強化する効果が低下してしまい、骨が脆くなることにつながります。
タンパク質不足のサインとして「骨が脆くなること」があります。
むくみ
タンパク質不足のサインとして「むくみ」があります。
血液中のアルブミン(タンパク質の一種)の濃度が低下し、浸透圧を維持できなくなり、水分が血管外に移動することによって「むくみ」(浮腫)につながります。
血液中には、アルブミン・グロブリン・フィブリノゲンなどのタンパク質が存在します。
そのうち、アルブミンは、最も多く存在する血液中のタンパク質であり約60%を占めています。
アルブミンは血管内に水分を維持する働きをし、浸透圧を維持しています。
タンパク質が不足し、血液中のアルブミンが不足すると、血液中のアルブミン濃度が低下します。
すると、血管内に水分を保持できなくなり、水分が血管外に移動することによって「むくみ」(浮腫)が起こります。
タンパク質不足のサインとして「むくみ」があります。
髪・爪のトラブル
タンパク質不足のサインとして「髪・爪のトラブル」があります。
タンパク質は、体の構造を作る材料になります。
食事などから摂取されたタンパク質はアミノ酸に分解されて、消化吸収されます。
消化吸収されたアミノ酸は、門脈を通って肝臓に入り、体に必要なタンパク質が作られます。
アミノ酸やタンパク質は、髪や爪を構成する重要な栄養素であり、不足すると髪や爪のトラブルを引き起こします。
タンパク質不足によって、髪のハリやツヤが失われる、髪が細く痩せてしまう、枝毛や切れ毛が増える、分け目が広がる、髪のボリュームがなくなる、ヘアセットがきまらないなどの髪のトラブルにつながります。
また、タンパク質不足によって、爪が割れる・欠ける、爪が薄くなる、爪に縦筋が入る、爪が二枚爪になるなどの爪のトラブルにつながります。
タンパク質不足のサインとして「髪・爪のトラブル」があります。
冷え
タンパク質不足のサインとして「冷え」があります。
タンパク質が不足すると、筋肉量が減少し、体が冷えやすくなる可能性があります。
これは、筋肉や肝臓などにおいて、熱エネルギーが産生されますが、タンパク質が不足すると筋肉量が減少し、代謝が低下し冷えやすい体になります。
また、タンパク質を消化吸収するにあたって、「食事誘発性熱産生」(DIT)が発生し、熱エネルギーが発生します。
タンパク質は、体内で熱を発生させるのに、とても重要な栄養素となっており、不足すると冷えにつながるのです。
タンパク質不足のサインとして「冷え」があります。
月経異常
タンパク質不足のサインとして「月経異常」があります。
女性の場合、タンパク質が不足することによって、月経に関係するホルモンを産生することができず、「月経異常」が引きおこります。
アミノ酸やタンパク質は、体の構造だけでなく、ホルモンなどの材料にもなります。
タンパク質が不足すると、脳から分泌される「LH」「FSH」、卵巣から分泌される「エストロゲン」「プロゲステロン」などの月経に関係するホルモンの分泌が低下します。
すると、月経が不規則になる、月経回数が減る、月経量が減るなどの無月経を来します。
タンパク質不足のサインとして「月経異常」があります。
タンパク質の摂りすぎの症状
腎機能の低下
タンパク質の摂り過ぎの影響として「腎機能の低下」があります。
腎臓には、体内で出てくる「老廃物」をろ過する役割があります。
そして、その老廃物のひとつに、たんぱく質を分解した時に作られる「尿素」や「窒素」があります。
ちなみに、尿中の細菌などによって、尿の成分の尿素が分解されて「アンモニア」などが作られて、おしっこ特有の臭いがします。
たんぱく質を多く摂り過ぎてしまうと、「尿素」や「窒素」が多く出来てしまうため腎臓に負担がかかってしまいます。
腎臓の機能が低下すると「全身倦怠感」「動悸」「息切れ」「尿量の低下」「むくみ」「吐き気」などの症状や、「高血圧」「貧血」などの病気につながります。
なお、血液検査では、「尿素窒素」(BUN)という項目の値が上昇します。そして、腎臓の機能が低下すると、「Cr」(クレアチニン)も上昇してくるのです。
ちなみにタンパク質の摂り過ぎによって「尿路結石」のリスクが上がることも知られています。おしっこの通り道に石が出来てしまう病気で強烈な痛みを伴います。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「腎機能の低下」があります。
消化不良
タンパク質の摂り過ぎの影響として「消化不良」があります。
一度の食事で消化吸収されるタンパク質の量は、おおよそ「20~40g程度」と言われています。
それ以上のタンパク質をとっても、消化・吸収されずに腸の中に残ってしまいます。
腸内に残ったタンパク質によって、腸内細菌のエサとなり、悪玉菌が増殖してしまうおそれがあります。
そのため、腹満感、腹痛、下痢、便秘などの症状につながることもあります。
とくに、「糖質制限ダイエット」「ケトジェニックダイエット」「ファットアダプト」などで、炭水化物の摂取を抑えていることがセットになっていると、食物繊維が不足しがちになります。
食物繊維が不足すると、便が硬くなり便秘がちになりますし、腸内環境は悪化してしまいます。
カロリーオーバー
タンパク質の摂り過ぎの影響として「カロリーオーバー」があります。
タンパク質は、炭水化物・脂質と並んで三大栄養素と言われており、エネルギー源として重要です。
ちなみに、タンパク質1gあたり4kcalのエネルギーがあります。
タンパク質を摂り過ぎると、カロリーオーバーとなってしまい、余分なエネルギーは体脂肪として蓄積されてしまいます。
また、タンパク質を多く含む「肉」「さかな」「乳製品」「大豆製品」などには脂質も豊富に含まれています。
脂質は1gあたり9kcalと高カロリーであるため、タンパク質と一緒に摂り過ぎてしまうと、カロリーオーバーにつながります。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「カロリーオーバー」があります。
体重増加
タンパク質の摂り過ぎの影響として「体重増加」があります。
「タンパク質」は、「脂質」「炭水化物」と並んで三大栄養素の一つです。
「タンパク質」「脂質」「炭水化物」のことを「PFC」といいますが、体を動かすときのエネルギーを産生する働きがあります。
ちなみに、
タンパク質は、1g当たり4kcal
炭水化物は、1g当たり4kcal
脂質は、1g当たり9kcal
のエネルギーを産生します。
タンパク質を必要以上に摂取すると、カロリーオーバーとなってしまいます。
余分なカロリーは、体脂肪として蓄えられ、体重増加につながります。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「体重増加」があります。
腎臓・肝臓への負担
タンパク質の摂り過ぎの影響として「腎臓・肝臓への負担」があります。
タンパク質は摂取されて消化吸収されると、アミノ酸という形になります。
アミノ酸を材料にして、体の臓器や筋肉などを構成するタンパク質に再合成されるのです。
この過程において、アンモニアという毒素が生まれます。
肝臓において、アンモニアは無毒化されて尿素となり、腎臓において尿中に排出されるのです。
タンパク質を摂り過ぎてしまうと、アンモニアを処理する肝臓や腎臓に負担がかかってしまいます。最悪、肝障害や腎不全につながるのです。
また、尿中の尿素が多くなると、尿のにおいがきつくなります。さらに、尿の成分が変化するため、尿路結石などが引き起こされることもあります。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「腎臓・肝臓への負担」があります。
消化にエネルギーを要する
タンパク質の摂り過ぎの影響として「消化にエネルギーを要すること」があります。
「タンパク質」は、「脂質」「炭水化物」と並んで三大栄養素の一つです。
なお、「タンパク質」「脂質」「炭水化物(糖質)」のことを「PFC」といいますが、体を動かすときなどのエネルギーを産生する働きがあります。
食事を消化吸収するのに当たって、エネルギーが必要であり、食後に熱エネルギーが発生しますが、「DIT」(食事誘発性熱産生)と呼ばれます。
食後、安静にしていても熱産生されてエネルギーが作られるのです。
糖質のみであれば、摂取エネルギーの「約6%」
脂質のみであれば、摂取エネルギーの「約4%」
タンパク質のみであれば、摂取エネルギーの「約30%」
となっており、圧倒的にタンパク質の熱産生が高いことがわかります。
糖質や脂質は、消化吸収するのにエネルギーがそこまで必要ありませんが、タンパク質を消化吸収するのにエネルギーが必要となります。
タンパク質を摂り過ぎることによって、体内で消費されるエネルギーが増えることになるのです。
ダイエットやボディメイクをされている方は、タンパク質の消費エネルギーを利用して、カロリーを消費するメリットが得られます。
スポーツなどでエネルギーが膨大に必要になる方は、食事によってエネルギーを消費されてしまうため、注意が必要になります。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「消化にエネルギーを要すること」があります。
アンモニアが発生する
タンパク質の摂り過ぎの影響として「アンモニアが発生すること」があります。
タンパク質は、アミノ酸に分解されて体内に消化吸収されます。
そして、門脈を通って、肝臓に入り込んで、アミノ酸を材料にしてタンパク質が作られます。
また、糖質や脂質などからのエネルギーが不足する場合、タンパク質(アミノ酸)もエネルギー源として利用されます。
このときに、アミノ酸からアミノ基が分離して、ブドウ糖やケトン体に変換されてエネルギー源として利用されます。
分離したアミノ基から「アンモニア」が産生されることになります。
アンモニアは体にとって有害な物質であり、肝臓で代謝されて尿素に変換し、尿中から体外に排出します。
尿中の尿素が多くなると、尿のにおいがきつくなります。さらに、尿の成分が変化するため、尿路結石などが引き起こされることもあります。
タンパク質を摂り過ぎると、糖質や脂質などのエネルギー源が不足しがちになります。
アミノ酸もエネルギー源として使われることが多くなるため、アンモニアがより多く発生してしまうことになり、肝臓や腎臓に負荷がかかることになります。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「アンモニアが発生すること」があります。
腸内環境が悪化する
タンパク質の摂り過ぎの影響として「腸内環境が悪化すること」があります。
一回の食事で消化吸収されるタンパク質の量は決まっており、おおよそ「20g~40g程度」と言われています。
それ以上のタンパク質をとっても、消化・吸収されずに腸の中に残ってしまいます。
腸内に残ったタンパク質によって、腸内細菌のエサとなり、悪玉菌が増殖してしまうおそれがあります。
なお、タンパク質が悪玉菌の作用によってアンモニアが発生するためガスが多くなり、排ガスが多くなり、おならのニオイがきつくなる、腹満感、腹痛、下痢、便秘などの症状につながることもあります。
さらに、アンモニアが血液中に入り込むと、解毒するために肝臓や腎臓に負担がかかります。
とくに、「糖質制限ダイエット」「ケトジェニックダイエット」「ファットアダプト」などで、炭水化物の摂取を抑えていることがセットになっていると、食物繊維が不足しがちになります。
食物繊維が不足すると、便が硬くなり便秘がちになりますし、腸内環境は悪化してしまいます。
タンパク質の摂り過ぎの影響として「腸内環境が悪化すること」があります。
まとめ
今回は「タンパク質」について説明しました。
タンパク質は、速く走るための体づくりに必要不可欠な栄養素です。
「タンパク質を摂取するポイント」の記事もあわせて確認頂ければ幸いです。

この記事によって「タンパク質」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者