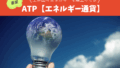トレーニングの3原理・5原則って何ですか?
このような疑問にお答えします。
これからマラソントレーニングを行う初心者の方は、「なぜ、トレーニングを行うのか?」その本質について分かった上で、トレーニングすることで効率的にタイムを伸ばすことができます。
また、ベテランランナーで伸び悩んでいる方は、一度、「トレーニングの本質」を見直すことによって、現状を打破するヒントが見つかるでしょう。

では、トレーニングの本質である3原理・5原則って何ですか?
ということで、今回は「トレーニングの3原理・5原則」について説明していきます。
トレーニングの3原理
過負荷の原理
トレーニングの3原理の一つに「過負荷の原理」があります。
過負荷の原理は、トレーニングにおいて一定以上の運動負荷を与えることで、運動機能が向上するという原理であり、「オーバーロードの原理」とも言われます。
つまり、いつもできているトレーニング内容のままであれば、パフォーマンスは変わらず、同じ結果しか出ないということです。
いつも以上の負荷を体にかけてトレーニングすることによって、運動機能が向上します。

ただし、トレーニング後には体力レベルが低下するため、その後しっかりとリカバリーさせることが大事です。
十分なリカバリーをとることによって、今以上の体力レベルに回復し(超回復)、より高いパフォーマンスを発揮することが出来るのです。
つまり、リカバリーによって成長するのです。
過負荷(オーバーロード)の原理を実践するためには以下のようなものがあります。
回数を増やす
オーバーロードの具体例として、いつもより回数を増やして多くします。
たとえば、今まで腹筋は10回しかできないとしたら、12回など回数を増やします。
ウエイトトレーニングではさらにわかりやすく、いつもはスクワットを10回しかできないとしたら12回など回数を増やします。
運動負荷を増やす
オーバーロードの具体例として、いつもより運動負荷を増やします。
たとえば、ウエイトトレーニングにおいて、いつもはベンチプラスを「40kg」持ち上げていたものを「50kg」に重量を増やします。
運動の量を増やす
オーバーロードの具体例として、いつもより運動の量を増やします。
たとえば、マラソンの練習において、いつもは「10km」のジョギングのところを「12km」に走行距離を増やします。
運動の質を上げる
オーバーロードの具体例として、いつもより運動の質を上げます。
たとえば、ランニングマシーンにおいて、いつもは「時速8km」のペースで走っていたものを「時速10km」にペースを上げます。
特異性の原理
トレーニングの3原理の一つに「特異性の原理」があります。
トレーニングの特異性とは、トレーニングの種類や強度によって効果が異なり、目的や目標に合わせたトレーニングを行う必要があることを指します。
例えば、脚を鍛えたいのに腕のトレーニングをしても意味がないです。
フルマラソンの場合では、42.195kmの距離をより速く走るということが目標となります。
走る動作に関係する筋肉を鍛えるとともに、それを維持するための心肺機能、42.195km維持するための筋持久力、途中でエネルギーが枯渇しないような栄養素を利用する能力など様々な能力をトレーニングによって鍛えることになります。
自分が行う競技に求められる能力をトレーニングで鍛えることが大切なのです。
可逆性の原理
トレーニングの3原理の一つに「可逆性の原理」があります。
トレーニングの可逆性とは、トレーニングを中断すると、得られた能力や体力などが元の状態に戻ってしまう原理です。トレーニングの効果は永続的ではなく、継続してトレーニングを行うことで維持・向上させる必要があります。
トレーニングを短期間でやめた場合は、元に戻るまでの時間も短くなります。
トレーニングを長期間続けた場合は、筋肉が失われるスピードも遅くなります。
つまり、体力やパフォーマンスを維持するためには、トレーニングを定期的に継続する必要があります。
とくに、維持したい、伸ばしたい部位があれば定期的にその部分に対して負荷を与え続けることが大事になるのです。
トレーニングを継続するために、「スポーツ障害」(ケガ)や「オーバートレーニング症候群」「バーンアウト」などに陥らないように、自分自身のキャパシティに見合ったトレーニングの量や負荷を心がけることが大切です。
トレーニングの5原則
漸進性の原則
トレーニングの5原則の一つに「漸進性の原則」があります。
漸進性の原則は「少しずつレベルアップすることが大切」という原則です。
トレーニングの強度や時間、頻度などを少しずつ上げていくことが重要です。
また、難易度が高いもの、特殊なスキルが必要なものなど難しいものに挑戦するときには、小さな課題をクリアしながら少しずつステップアップすることが大切です。
一気に負荷をかけすぎると、体が適応できず、ケガなど危険を伴います。
少しずつ順を追って、段階的に育てることによって、ケガのリスクを抑えられますし、すぐに失われにくい体力やスキルを身につけることができるのです。
全面性の原則
トレーニングの5原則の一つに「全面性の原則」があります。

全面性の原則は「全身をバランスよく鍛えることが大切」という原則です。
ランニングであれば、下半身を中心に鍛えることになりますが、体幹部や上半身も含めて全身をバランスよく鍛えることが重要です。
また、持久系の運動、有酸素運動だけでなく、瞬発系の運動、筋力トレーニング、柔軟性など様々な体力要素もバランスよく高めることが大切です。
鍛える体の部位や鍛える要素が偏ると、全身のバランスが崩れて、怪我や痛みの原因になりやすくなります。
偏り過ぎず、バランスの良く体を鍛えていくことが重要なのです。
個別性の原則
トレーニングの5原則の一つに「個別性の原則」があります。
個別性の原則は「個人の特性や能力に合わせたトレーニングが大切」という原則です。
人それぞれ、骨格や体力、得意な部分、トレーニングに耐えられるキャパなどが違います。
とくに、「年齢、性別、体力、生活環境、習慣、性格、運動の好み」など個人差があります。
自分が得意とする分野、自分に合ったやり方がわかれば、より効率的に体を鍛えることができますし、モチベーションも継続することにつながります。
自分自身に合った競技を、自分に合ったトレーニング量や質を見定めて、トレーニングをすることが重要なのです。
意識性の原則
トレーニングの5原則の一つに「意識性の原則」があります。
意識性の原則は「トレーニングをするときに意識の持ち方が大切」という原則です。
運動の内容や目的、意義をよく理解して、トレーニングに取り組むことが大切です。

筋力トレーニングにおいて、どこの筋肉を鍛えているのか意識しながら行うことによって、トレーニング効果がアップします。
マラソントレーニングにおいて、
キツイ場面で粘る練習なのか?
余裕のあるペースで押し切る練習なのか?
動き作りの練習なのか?
トレーニング目的を意識することによって、トレーニング効果が高まります。
反対に、何も意識しないでトレーニングに取り組むと、得られるものが少なくなりますし、長期的にみて方向性も見失ってしまう可能性もあります。
「頑張っても、成果につながらない」なんてことになりかねません。
トレーニング目的を意識して、取り組むことによって、より効率的に鍛えることができるのです。
反復性の原則
トレーニングの5原則の一つに「反復性の原則」があります。
反復性の原則は「トレーニングを継続することが大切」という原則です。
「継続は力なり」という言葉があるように、トレーニングを継続的に行うことによって、大きな効果が得られます。
体力やパフォーマンスを向上させるためには、トレーニングを続けることが必要であり、少なくとも週3回以上の頻度、規則的に、長期間行うようにしましょう。
反対に、トレーニングが中断すると、得られた能力や体力などが元の状態に戻ってしまいます。
トレーニングを「短期間」でやめた場合は、元に戻るまでのスピードは速いです。
トレーニングを「長期間」続けた場合は、元に戻るまでのスピードも遅くなります。
トレーニングの効果は永続的ではなく、継続してトレーニングを行うことで体力を維持・向上させることが重要なのです。
まとめ
今回は「トレーニングの3原理・5原則」について説明しました。
トレーニングの本質を理解した上で、日々の練習を行うことによって、トレーニング効果を引き出すことができます。
とくにベテランランナーになるにつれて、自分の限界を感じる場面が多くなります。
伸び悩んでいる時こそ、一度トレーニングの本質に立ち返ることが大切なのです。
この記事によって「トレーニングの3原理・5原則」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者