・体重を落として、軽くなった状態で走りたいです!
・どのようにしたら体重を落とせますか?
・そもそも体重を落としてもいいですか?
この記事を読むことによって、ランナーの体重コントロールについて理解することができます。
こういうと元も子もないですが、
ランナーは体重をあまり気にしない方がいいです。
日々のトレーニングや、食生活の結果が今の体重や体格に反映されています。
その部分を変えてしまうと、コンディションを崩してしまうおそれがあるからです。
自分自身の体を実験にして、体重を増やしたり、減らしたりしましたが、結局コンディションを崩してしまい、うまく走れない状態に陥りました。

ランナーが、体重を意識的に落とそうとすることは基本的にはオススメしません。
とはいえ、より速く走るために体重をどうしてもコントロールしたいというランナーは多いでしょう。
では、「ランナーの体重コントロール」についてみていきましょう。
ランナーの体重コントロールについての考え方
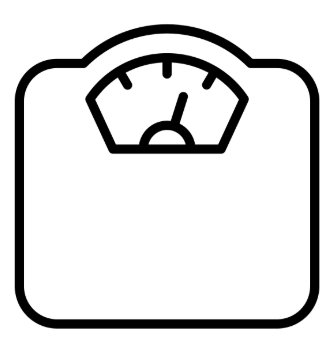
体重とマラソンタイム
体重が1kg増えると、フルマラソンのタイムは約3分遅くなる
とされております。
同じ体力レベルであれば、体重は軽いほど、速く走ることができます。
トレーニングによって、体力レベルを上げることによって、速く走ることができます。
また、体重を落とすことでも、速く走ることができるのです。
ランナーにとって、「体重コントロール」は速く走る上で重要になります。
体重をコントロールするには
「食事で摂取するカロリー」-「運動で消費するカロリー」が体重の増減に
「食事で摂取するカロリー」から「運動で消費するカロリー」を引いたものによって体重の増減に反映されます。
つまり、体重を落とすことを考えると…
・食事で摂取するカロリーを減らす
・運動で消費するカロリーを増やす
ことになります。
走行距離を増やすと消費カロリーは増える
走行距離1kmで、体重1kgあたり「約1kcal」消費します
たとえば、体重60kgのランナーが10km走ったら、「約600kcal」消費します。
これは走る速度に関わらず、同じくらいのカロリーが消費されます。
正確にいうと、
走る速度が速ければ、糖質が多めに消費される
走る速度が遅ければ、脂質が多めに消費される
という事実がありますが、トータルの消費カロリーは、ほとんど変わりません。
つまり、食事が変わらなければ、走行距離を増やすことで消費カロリーは多くなるため、体重を落とすことにつながります。
体力レベルが上がるとともに、走行距離が自然と伸びていき、体重も自然と落ちていくのが理想的です。
摂取カロリーを減らすと体力レベルは落ちやすい
食事による摂取カロリーを減らすと、体力レベルは落ちやすい
体力レベルを維持しながら、体重を落とすのは非常に難しいです。
運動量を変えない場合、体重を落とすためには、食事の摂取カロリーを少なくする必要があります。
摂取カロリーが少ないと、使えるエネルギーも少なくなるため、トレーニングの出力が低下します。
さらに、リカバリーに回すエネルギーも少なくなるため、トレーニング効果をうまく得られないおそれがあります。
体重を落とすために、摂取カロリーを減らすと、体力レベルが落ちやすいので注意が必要です。
三大栄養素のいずれを減らすべきか
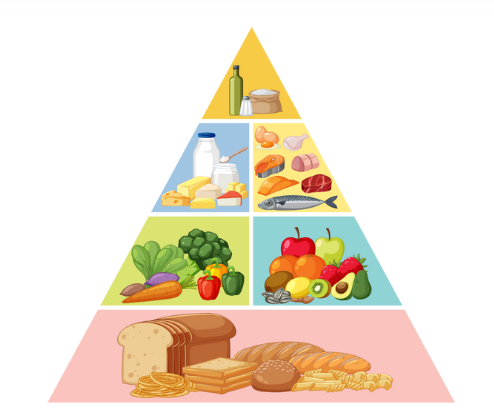
エネルギー源である「糖質」「脂質」「タンパク質」のいずれかを減らすことに
運動量やトレーニング自体変えない場合は、食事から摂取するカロリーを減らすことになります。
体のエネルギー源となる三大栄養素があります。
体重を落とすためには、糖質、脂質、タンパク質のいずれかを減らすことになります。
体力レベルを維持しながら、体重を落とすためには、どの栄養素を減らすか考えなくてはなりません。
個人的な意見になりますが…
「糖質」は、短期間で体重を落とせますが、意識して制限すべきではないです。
「脂質」は、体重を落とすのに時間がかかりますが、ある程度制限してもいいでしょう。
「タンパク質」は、筋肥大をおさえるために、ある程度制限してもいいでしょう。
以下、具体的にみていきましょう。
三大栄養素で体重を落とす
糖質を制限する

糖質を制限すると、「短期間で1~2kg程度の体重を落とすこと」ができます。
糖質の貯蔵は、グリコーゲンとして「1g当たり約3gの水分」も引き込みます。
体内には肝臓に「約100g」、筋肉に「約400g」のグリコーゲンが貯蔵されています。
水分も合わせると、グリコーゲン約500g+水分約1500gで合計「約2000g」の重量になります。
糖質はエネルギーになりやすいため、すぐに消費されます。
そのため、糖質制限によって比較的短期間で体重を落とすことができます。
さらに、グリコーゲンと一緒に水分も抜けるため、短期間で「約1kg~2kg程度」の体重を落とすことが可能です。しかし、それ以上の体重を落とすことができません。
また、糖質摂取を再開すると、すぐに体重が増加するため、リバウンドしやすいです。
なお、糖質はエネルギー源となる重要な栄養素です。
さらに、脂質をエネルギー源として使う場合に、ある程度の糖質の存在が必要です。
糖質を制限すると、トレーニング強度は上がらず、体力レベルは落ちやすいため、オススメしません。
糖質は多量の水分とともに動く
糖質は多量の水分とともに動くため、体重の変化が激しくなります。
スピード練習の時には、多くの糖質が使われるため、多くの汗をかく(寒い日にはおしっこの量が多くなる)かと思います。
また、糖質を多く摂取しているときには、水分を求めて喉が渇きやすくなるでしょう。
甘いものをたべると、喉がかわくのです。
糖質は水分とともに動くため、短期間で大きく体重が変化します。
脂質を制限する

脂質を制限することで、体内に蓄えられている体脂肪を落とすことができます。
ランナーにとって一番落としたいのが体脂肪になるかと思います。
「脂肪1kgあたり約7000kcal」のエネルギーがあります。
一日あたり200kcalのカロリーを制限すると、35日(約1ヶ月)で、やっと約1kgの体脂肪を落とすことになるため、時間がかかります。
なお、体脂肪が少なくなってくると、糖質やタンパク質などの他のエネルギー源が優先的に使われやすくなるため、体脂肪が落ちにくい体になります。
ただし、脂質の摂取量が極端に少なくなり過ぎると、体を守る反応が起こり、体脂肪が落ちにくい体質になります。
さらに、満腹感をもたらす「レプチン」というホルモンが少なくなり、食欲が爆発してリバウドしてしまうおそれがあります。
脂質は悪者にされやすく、食事コントロールによって脂質不足に陥りやすいので、最低限の脂質は確保するようにしましょう。

タンパク質を制限する

タンパク質を制限することで、筋肉量を落とすことができます。
ランナーにとって、基本的には筋肉は落としたくないかと思います。
しかし、筋肥大しすぎてしまっている方は、筋肉量を落とすことも考慮してもいいかと思います。
筋肉量の多いマッチョの方では、長時間走り続けるのは明らかに不利です。
筋力は維持しながら、筋肉量を減らす
これがキーワードになります。
筋力トレーニングする場合、「高負荷・低回数」もしくは「低負荷・高回数」のトレーニングを行えば、筋肥大をおさえながら、筋力レベルを高めることができます。
なお、筋力トレーニング後に有酸素運動を組み合わせることで筋肥大を抑えることができます。
また、タンパク質の摂取量を制限することによって、筋肉の合成を抑えることができます。
普段から高タンパク質食のランナーは筋肥大しがちです。
タンパク質の摂取量が多い人は、とくにタンパク質の量を抑えてみてもいいでしょう。
ただし、タンパク質は、体作りやリカバリーなどに必要な栄養素なので、不足しないよう注意しましょう。
塩分と体重変化

塩分を制限すると、「短期間である程度体重を落とすこと」ができます。
塩分を多めに摂取すると、体内に水分を引き込みやすくなります。
専門的にいうと、体内の塩分濃度が高まると浸透圧が高まり、水を引き込みやすくなります。
そして、細胞間質に水がたまると「浮腫(むくみ)」となります。
「塩分1gあたり、体重100g程度」増えるといわれています。
さらに、塩分の多い食べ物は、喉が渇きやすいです。
そのため、水分も多く摂りがちですし、口や消化管の粘膜を刺激して炎症が起こり水分がたまりやすい状態となります。
塩分を制限すると、体内の余分な水分は排出されるため、短期間で体重を落とすことができます。
フィットネス業界では、いわゆる「塩抜き」として知られています。
まとめ
今回は、「ランナーの体重コントロール」について説明しました。
体重を意識することは大事ですが、あまり気にしないで走ることも大切です。
体重を意識的に落とそうとすると、コンディションを崩してしまうおそれがあります。
とくに、毎日のトレーニングを継続しているような真面目なランナーは、体重の増減に関してあまり気にしない方が良いかと思います。
それよりも自分にとって調子がいい食事のバランスを探っていく方が速く走るためには重要だと個人的には考えます。
体重コントロールしようとすると、コンディションを崩すリスクが高めるため、今回の話は、頭の片隅に参考までに入れておくようにしてください。
この記事によって「ランナーの体重コントロール」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
この記事の著者




